特別支援学級に入る基準としては、知的障害、肢体不自由、弱視、難聴、言語障害、自閉症・情緒障害などが対象となります。 ただし、特別支援学級のある学校とない学級がありさらに、すべての障害種が設置されているわけではありません。
障害の有無や等級だけで判断されるのではなく、子どもの個性や学校側の状態などを色々検討したうえで判断されます。さらに詳しくどのような手続きを行なって、小学校特別支援学級に入るのかを解説していきます。
学校や地域によっては、より具体的な基準や条件が設けられている場合があります。詳細な情報は所属する学校や教育機関にお問い合わせください。
この記事で扱うのは、主に小学校特別支援学級の知的障害についての詳細の記事です。通級や中学校、高校については言及していません。
\ 一人で抱え込まないで! /
小学校特別支援学級について

小学校特別支援学級とは?
小学校特別支援学級は、障害のある子供に対して、個別の支援や適切な教育を提供するために設けられる学級です。
特別支援学級は、国や地方公共団体が障害のある子どもたちの教育を適切に行うために設けられています。以下に、特別支援学級の設置の理由や根拠を示します。
- 平等な教育機会の実現: 特別支援学級は、障害のある児童や生徒が通常の学級と同じように教育を受ける機会を提供することにより、平等な教育機会の実現を目指しています。
- 個別の支援の提供: 特別支援学級では、児童や生徒の個別のニーズや発達段階に合わせた支援が行われます。教育プランや教育課程が個別に編成され、専門の教員や支援スタッフが適切な支援を提供します。
- 社会参加の促進: 特別支援学級は、障害のある児童や生徒が社会参加や自立した生活を送るために必要な能力を育む場として機能します。適切な支援を受けながら学ぶことで、社会での活動や就労への準備が進められます。
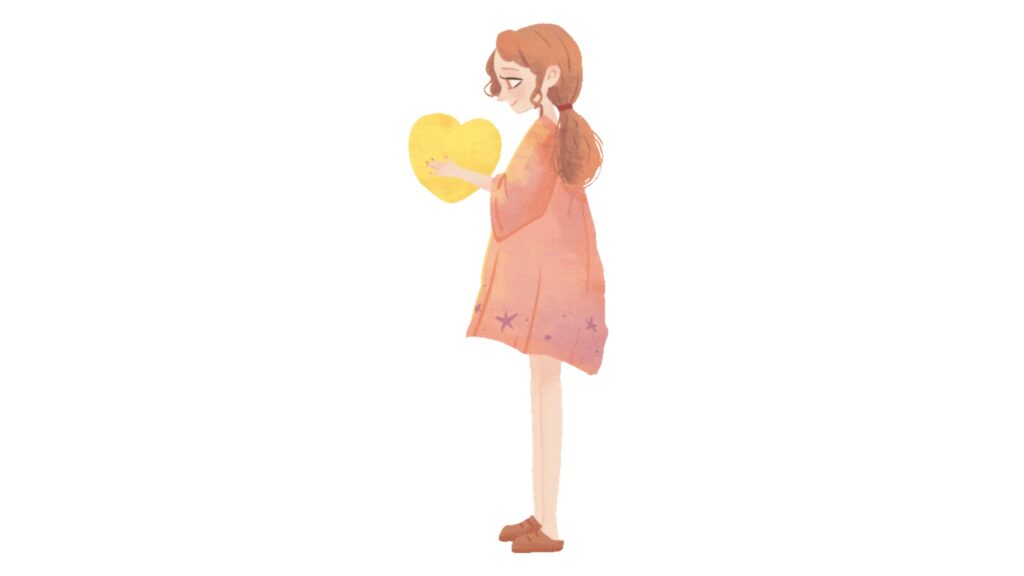
特別支援学級は、障害のある子供に対して「個別の支援」や「適切な教育」を提供するために設けられる学級です。平等な教育機会の実現や個別のニーズに応じた支援の提供、社会参加の促進などがその目的となっています。特別支援学級があることで子供の個別の特性や障害に適切に対応し、学びや成長を支えていきます。
特別支援学級は、多様な障害を持つ児童や生徒が個別のニーズに合わせた支援を受けながら学ぶ場であり、その役割は非常に重要です。保護者や教員は、特別支援学級について理解を深め、子供の教育環境に適切な支援を提供するために協力していきましょう。
○学校教育法(昭和二十二法律第二十六号)
第八十一条 (略)
2. 小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。
一 知的障害者
二 肢体不自由者
三 身体虚弱者
四 弱視者
五 難聴者
六 その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの3. 前項に規定する学校においては、疾病により療養中の児童及び生徒に対して、特別支援学級を設け、又は教員を派遣して、教育を行うことができる。
文部科学省 特別支援学級及び通級指導に関する規定
特別支援学級の編成

特別支援学級の編成は、子供の特性やニーズに基づいて行われます。個々の子供の発達レベルや支援の必要度に応じてクラス編成が行われ、適切な学習環境と支援が提供されます。
特別支援学級の編成は、日本の教育法や教育行政に基づいて行われています。教育委員会や学校教育法によって特別支援学級の設置基準や編成方法が示されており、児童の特性やニーズに合わせた適切な支援を提供するために編成が行われています。
以下、2通りの編成の例をあげて解説します。
例えば、自閉症スペクトラム障害を持つ子供を集めたクラスや、知的障害を持つ子供を集めたクラスなどがあります。これにより、子供の特性に合わせた個別の支援が行われます。
知的障害や学習障害、発達障害など、異なるニーズを持つ子供が一つのクラスに混在する場合もあります。これにより、子供同士の学び合いや社会的な関係の構築が促されます。
特定の障害やニーズに特化したクラス編成をするには、子供の人数が多い地域でしか対応できないことです。私の経験では、基本的には学年で編成。特別支援学級全体の人数が多い場合(2〜3学級)は、教科グループでの能力別の編成や生活グループ、学習グループで分けることもありました。
特別支援学級の編成は、子供の特性やニーズに基づいて行われます。国や公共団体が示すガイドラインや指導要領を参考にしながら、個別のニーズを把握し、適切なクラス編成が行われます。特別支援学級の編成は、子供の成長と発達を支援するための重要な取り組みであり、教員や専門家の知識と経験に基づいた判断が求められます。特別支援学級の編成は、子供一人ひとりの個別のニーズに合わせて行われるため、柔軟性が重視されます。
学級編成の最終判断は校長がします。地域にもよりますが、私の経験では学年で編成することが多いように思いました。柔軟にということなので、途中で子ども同士の相性が悪いとか、宿泊に行くため担任の性別などにより変わったこともありました。
(※注意:上記の内容は一般的な特別支援学級の編成に関する情報であり、具体的な状況や地域によって異なる場合があります。現地の教育委員会や学校における指針や基準に基づいた情報収集や相談が必要です。)
特別支援学級の教育課程について

特別支援学級の教育課程は、子供の個別のニーズや発達段階に合わせて柔軟に設定されます。学習内容や教育方法は、子供が最大限の成長と発達を遂げるために工夫されています。
特別支援学級の教育課程は、児童生徒の発達レベルに合わせて組まれます。例えば、言語やコミュニケーションの困難を抱える子供には、言語療法やコミュニケーションスキルの向上を重視したプログラムが組まれることがあります。また、学習の遅れや困難を抱える児童生徒には、小集団での学習支援や補完的な教材を活用した学習が提供されることがあります。
特別支援学級の教育課程は、子供の個別のニーズに合わせて設計された柔軟なものです。子供が自己肯定感を高め、学習や社会生活において最大限の成果を上げるために、個別の目標やプログラムが設定されます。教員や専門家は、継続的な評価や観察を通じて子供の成長を把握し、適切な教育プランの見直しや調整を行います。

- 個別の指導計画: 子供の発達レベルやニーズに基づき、個別指導計画が設定されます。これにより、子供が自身の能力を伸ばし、課題を克服するための支援が提供されます。
- 適切な学習支援: 特別支援学級では、子供の学習困難や障害に合わせた適切な学習支援が行われます。教員や専門家が教材や教授方法を選択し、個別のニーズに合わせた学習環境を提供します。
- 豊かな教育活動: 特別支援学級では、学習だけでなく、子供の社会的なスキルや生活技能の向上も重視されます。例えば、コミュニケーション能力や協調性の養成、自己表現の促進などのために、様々な教育活動が取り入れられます。
- 個別の評価とフィードバック: 子供の進捗状況や成果を評価し、定期的にフィードバックを行います。教員は子供の強みや成長のポイントを把握し、適切なサポートや次のステップの計画を立てます。
- 保護者との連携: 特別支援学級では、保護者との緊密な連携が重要視されます。教員や専門家との定期的な面談や情報共有を通じて、子供の成長や課題について共有し、家庭と学校が連携して支援を行います。
これら教育課程の作成については、基本的には特別支援学級担任が行います。このことにより、各学級の格差がおこり、平等な教育機会の実現や教員不足による専門の教員や支援スタッフの質の保障がされないという課題があります。
また、細かいことですが教育課程の年間計画案や学級経営案の提出期日が5月初旬のため、子供の実態把握ができる期間が1ヶ月弱で、途中で変更することも多々あります。むしろ、変更しないとおかしなことになります。計画案はあくまでも「案」なので、気軽に考え、実態に応じて適宜変更するつもりでいましょう。
特別支援学級の指導内容

小集団による個別のニーズに合わせた学習支援が提供されます。子供たちの発達レベルや学習スタイルに応じて、教材や教授方法が適切に選定されます。
基本的な学習科目(国語・算数・生活)のほかに、生活技能や社会的なスキルの向上も重視されます。具体的には生活単元学習や自立活動があります。以下生活単元学習や自立活動について解説します。
生活単元学習
生活単元学習は、日常生活で必要なことを学ぶ学習です。例えば、
- 買い物の仕方
- 料理の仕方
- 掃除の仕方
- 友だちと遊ぶ方法
- 困ったときの対処法
など、生活の中で役立つことを学びます。生活単元学習では、ただ教わるんではなくて、自分で体験しながら学ぶことが大切なので、
買い物の仕方を学ぶときは、実際にスーパーマーケットに行って、自分で買い物をしてみる。
料理の仕方を学ぶときは、自分で料理を作ってみる。
掃除の仕方を学ぶときは、自分で掃除してみる。
友だちと遊ぶ方法を学ぶときは、友だちと一緒に遊んでみる。
困ったときの対処法を学ぶときは、困ったことが起きたときに、自分で考えながら対処してみる。
このように、自分で体験しながら学ぶことで、より実践的に学ぶことができるのが生活単元学習です。
生活単元学習を通して、子ども達に日常生活で困らない力を身につけさせていきます。
 1年生の男の子
1年生の男の子生活単元学習を略して「生単」って言ってるよ!
自立活動
もう一つの特別支援学級ならではの教科領域「自立活動」について、解説します。
自立活動の内容は、人間としての基本的な行動を遂行するために必要な要素と、障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服するために必要な要素で構成されており、以下の六つの区分に分類・整理されています。
- 健康の保持
- 心理的な安定
- 環境の把握
- 身体の動き
- コミュニケーション
具体的な例としては、
- 健康の保持:食事や排泄の指導、健康管理の指導
- 心理的な安定:ストレス対処法の指導、自己肯定感を高める指導
- 環境の把握:時間や場所の把握の指導、道具の使い方の指導
- 身体の動き:基本的な動作の指導、運動能力の向上の指導
- コミュニケーション:話す力や聞く力の指導、表現力の向上の指導
などが挙げられます。
自立活動は、児童生徒一人ひとりの障害や特性に応じて、個別の指導計画に基づいて指導が行われます。また、各教科等の指導を通しても適切に行われる必要があります。
自立活動を通して、障害のある児童生徒が、日常生活や社会生活において自立して生きていくための力を身につけることができます。
授業内容の詳細はこちらの記事をお読みください。
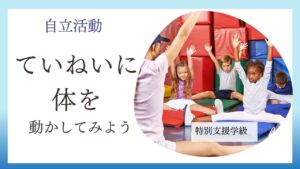
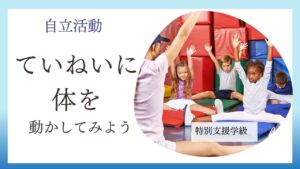
特別支援学級の指導内容は、子供の発達段階やニーズに合わせてカスタマイズされ、幅広い領域での学びを促すことを目指しています。その結果、子供の学習意欲や自己成長を支援し、社会的な適応や自己肯定感の向上にも寄与します。
特別支援学級の指導内容は、子供の個別のニーズや発達段階に合わせて柔軟に展開されます。その結果、子供は自己肯定感を高めながら学びの成果を上げることができます。
特別支援学級の種類


小学校の特別支援学級は、障害のある子供たちが通常の小学校に通いながら、個々の障害に応じた指導を受けることができる学級です。特別支援学級には、知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、弱視、難聴、言語障害、自閉症・情緒障害の7種類があります。
特別支援学級
小学校、中学校等において以下に示す障害のある児童生徒に対し、障害による学習上又は生活上の困難を克服するために設置される学級。
学びの場の種類と対象障害種
【対象障害種】
知的障害者、肢体不自由者、病弱者及び身体虚弱者、弱視者、難聴者、言語障害者、自閉症者・情緒障害者
特別支援学級の目的は、障害のある子供たちが、通常の学級の子供たちと一緒に学び、成長し、社会に自立して参加できるようにすることです。そのため、特別支援学級では、通常の学級と同じカリキュラムを学ぶだけでなく、個々の障害に応じた指導を受けることができます。また、特別支援学級では、通常の学級の子供たちとの交流や共同学習を通して、社会性を身につけることができます。
特別支援学級は、障害のある子供たちにとって、通常の小学校に通うための重要な選択肢の一つです。特別支援学級に通うことで、障害のある子供たちは、個々の障害に応じた指導を受けながら、通常の学級の子供たちと一緒に学び、成長し、社会に自立して参加することができます。
以下に、特別支援学級の種類とその特徴をまとめます。
| 障害の種類 | 特徴 |
|---|---|
| 知的障害 | 知的障害とは、知的発達がゆっくりしているという障害です。知的障害には、軽度、中度、重度の3つの程度があります。軽度から中度の知的障害の子供は、特別支援学級で学習することができます。重度の知的障害の子供は、特別支援学校で学習することができます。特別支援学校には重複障害学級もあり、より手厚い環境で学習することができます。 |
| 肢体不自由 | 肢体不自由とは、手足が動かない、または動かしにくいという障害です。肢体不自由には、生まれつきの障害と、後天的な障害があります。 肢体に障害のある子供たちが、身体機能に応じた適切な支援を受けながら学び、身体的な制約を克服し自立や社会参加を促すことを目指します。 肢体に障害のある子供で、通常の学級での学習や日常生活の活動が困難な場合や支援が必要な場合に該当します。身体機能に合わせた環境整備や支援具の提供が行われ、個々の子供の能力やニーズに合わせた教育プログラムや学習支援が提供されます。 |
| 病弱・身体虚弱 | 病弱や身体虚弱な子供が、健康状態に応じた適切な支援を受けながら学び、成長・発達することを目指します。 個々の子供の身体的特性や健康状態に応じた配慮が行われ、教育プログラムや学習支援が提供されるという特徴があります。子供を対象とする病院と併設されていることが多いです。子供の健康状態を把握し、医療的なサポートやケアを提供できます。医師や看護師との連携を図り、定期的な健康チェックや必要な医療措置を行うこともできます。 |
| 弱視 | 視覚障害とは、目が見えにくい、または見えないという障害です。視覚障害には、生まれつきの障害と、後天的な障害があります。 弱視の子供たちが、視覚に応じた適切な支援を受けながら学び、視覚機能の発達や学習能力の向上を促すことを目指します。 視覚に障害のある子供たちが、通常の学級での学習が困難な場合や視覚に関する支援が必要な場合に該当します。視覚に適した環境が整えられ、視覚補助具や視覚支援技術が活用されながら、適切な教育プログラムや学習支援が提供されます。 |
| 難聴 | 難聴を抱える子供たちが、聴覚に応じた適切な支援を受けながら学び、コミュニケーション能力や学習能力を発展させることを目指します。 聴覚に障害のある子供たちが、通常の学級での学習が困難な場合や聴覚に関する支援が必要な場合に該当します。子供の 聴覚に適した環境が整えられ、手話や補聴器などの支援具やテクノロジーが活用されながら、適切な教育プログラムや学習支援が提供されます。聴覚に障害のある子供たちが適切に聞こえる環境を整えるために、補聴器や聴覚支援機器の使用や手話を活用します。 |
| 言語障害 | 対象は、言語に関する困難を抱える子供たちです。具体的な障害としては、言語発達遅滞、発音障害、文章理解や表現の困難、コミュニケーション障害などがあります。これらの障害が子供の学習や社会生活に支障をきたしている場合、特別支援学級での支援が提供されます。言語障害の特別支援学級の特徴は、言語環境の整備が重要なポイントとなります。言語刺激の豊富な環境を提供し、子供たちの言語理解や表現能力の発達を促します。 |
| 自閉症・情緒障害 | 対象は、自閉症スペクトラム障害や情緒面の困難を抱える子供たちです。自閉症スペクトラム障害の特徴としては、社会的な相互作用やコミュニケーションの困難、制限された興味関心、繰り返し行動などがあります。情緒障害の特徴としては、感情の制御や調整の困難、不安や怒りの表出、対人関係の困難などがあります。自閉症・情緒障害の特別支援学級の特徴は、専門的な支援が挙げられます。 教員や専門職員(心理士、臨床心理士、ソーシャルワーカーなど)がチームを組み、個別の教育計画や支援プランを作成します。 |
特別支援学級は、障害のある子供たちが、通常の学級の子供たちと一緒に学び、成長し、社会に自立して参加できるようにするための重要な選択肢の一つです。
文部科学省の特別支援教育特別支援教育については何かと学びになります。特に新着情報では新しく変わったことを知ることができます。
これらの手厚い支援を受けられる特別支援学級ですが、実際は指導する教員が足りない、専門性がないということもあり、近年の学校を取り巻く課題となっています。
また「知的障害」があることを受け入れられない保護者の中には「情緒障害」なら・・・などと、適切ではないけど困っていることが解決できればという思いで、本来行くべき適切な判定ではないところに行かせるケースも多くあるように思います。
いずれにしても、困るのは子どもと指導する教員にしわ寄せが行ってしまうのが現状であること、子どもの進路が心配であるとともに、適切な判定で入っている子どもの学習を受ける権利を保障することも大事であると思います。
特別支援学級に入る対象の子供
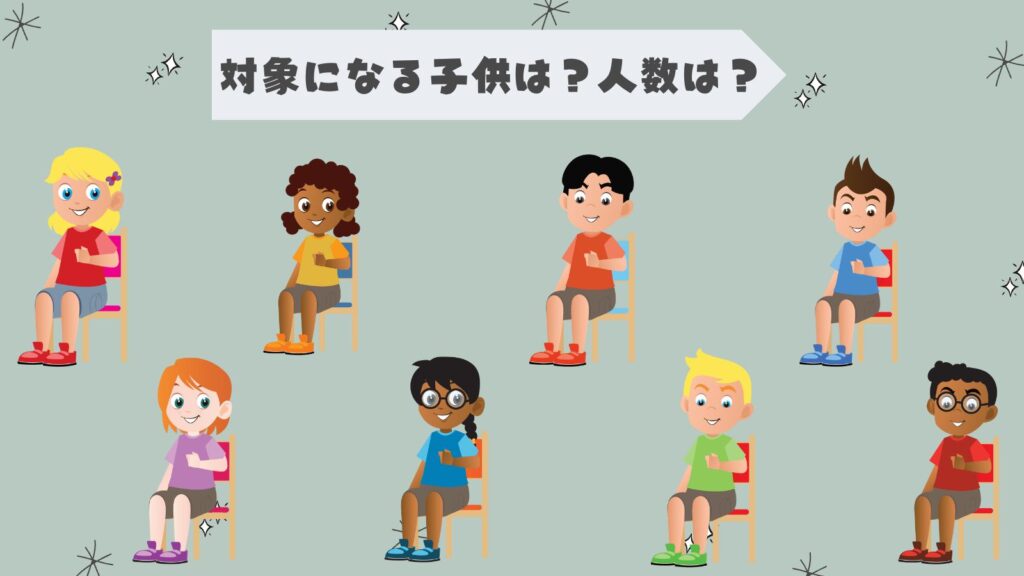
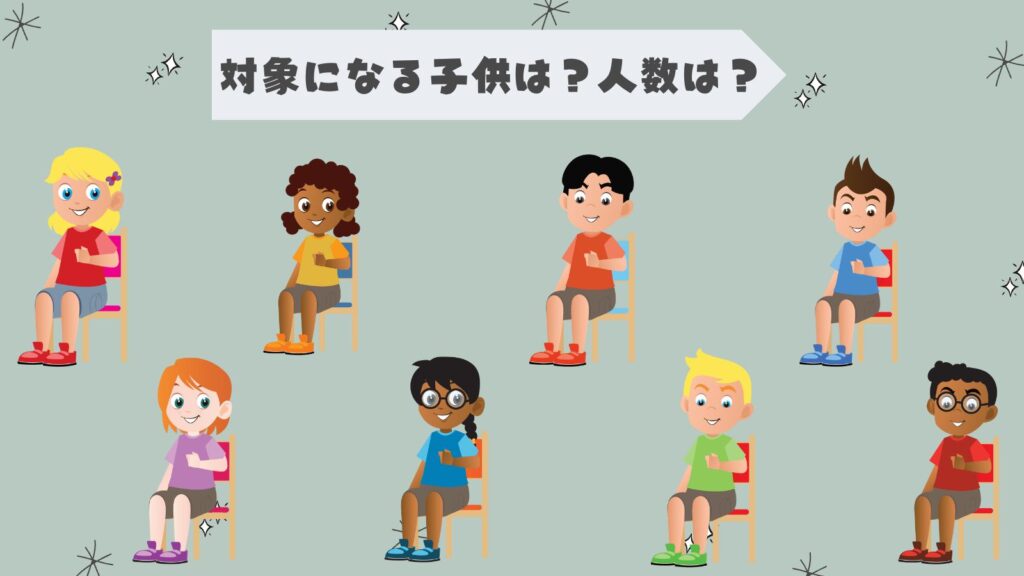
まとめると、特別支援学級の対象は、上記でも述べましたが、以下の8つの障害です。
弱視、難聴、知的、肢体不自由、病弱・身体虚弱、言語、情緒、自閉症
なお、情緒、視覚、聴覚などと、知的障害が重なる重複障害の場合は「知的障害が優先」されます。
次に知的障害の特別支援学級に入るための基準について、解説します。
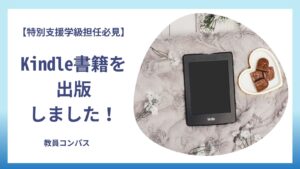
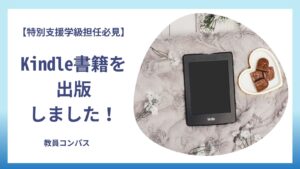
特別支援学級への入学基準や流れ
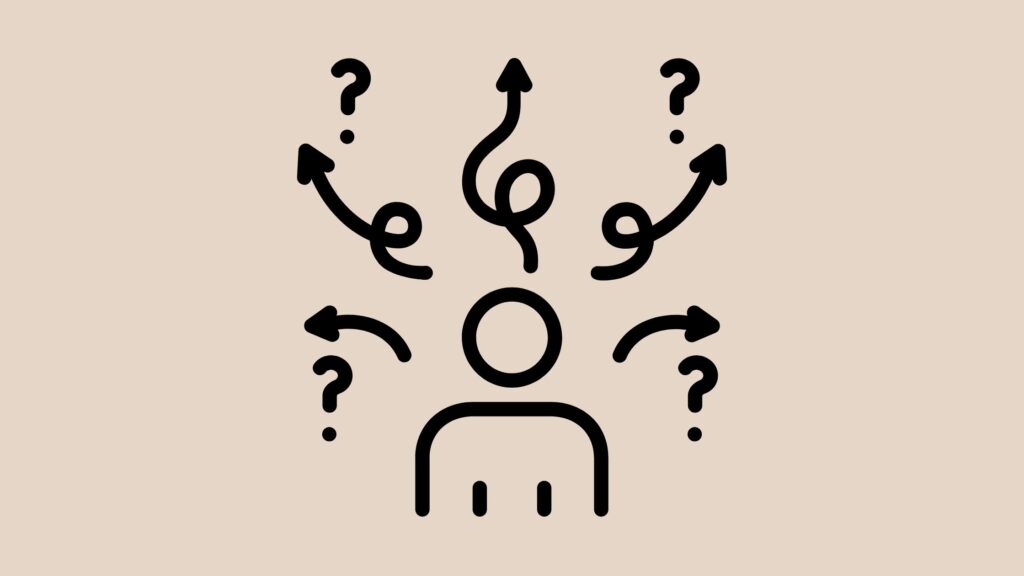
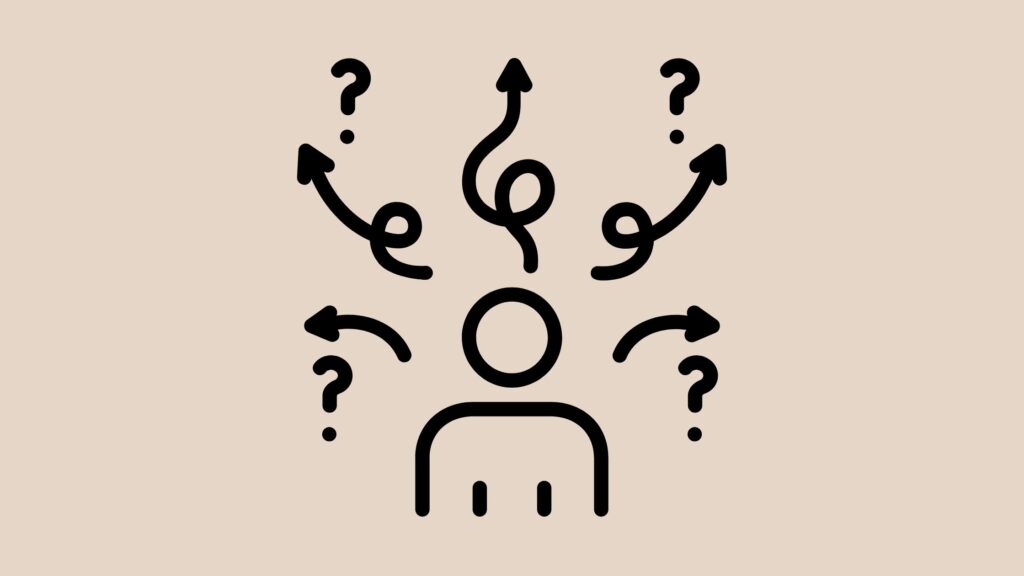
特別支援学級の入学基準
小学校特別支援学級に入るための基準は以下のようになります。これらの基準は、知的障害の特別支援学級に入るためのケースです。
繰り返しになりますが、実際の入学条件は地域によって異なる場合がありますので、具体的な情報は学校や教育機関にお問い合わせください。
- 専門家による知的機能の評価結果が必要です。一般的に、知的機能指数(IQ)が70以下の範囲に入ると言われています。ただし、家庭環境や本人や保護者の希望で、IQが高い子供も在籍することができます。
- 学習が困難であることの証明が必要です。児童精神科の医師による診断結果が求められます。児童精神科等の医療機関については、お住まいの自治体の教育センターや教育委員会で紹介されます。
- 個別の支援計画が作成されていることが求められます。保護者が必要性や内容を理解した上で、療育機関や保育園、学校で作成の依頼をします。学習目標や支援方法、評価方法などが記載された計画です。今すぐに作ったから効果があるものではなく、次の機関や外部の機関と繋げるために活用するものです。
- 特別な教育的ニーズがあることが求められます。知的障害に関連する、学習や社会的な困難を抱えていることが入学基準となります。
- 小学校特別支援学級への入学は、教育委員会の承認が必要です。教育委員会の機関である教育センターで審議して「特別支援学級入級が適切である」といった判定が必要です。学校や担当の教育委員会に入学手続きについて相談してください。
以上が、一般的な小学校特別支援学級への入学基準です。具体的な条件や手続きについては、所属する学校や教育機関の担当者にご相談ください。
特別支援学級に在籍するまで
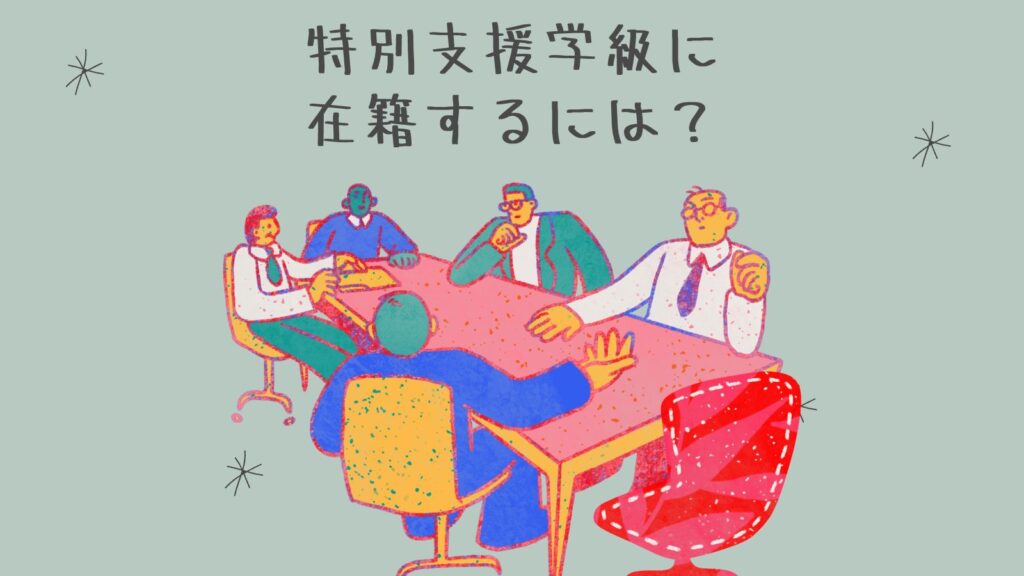
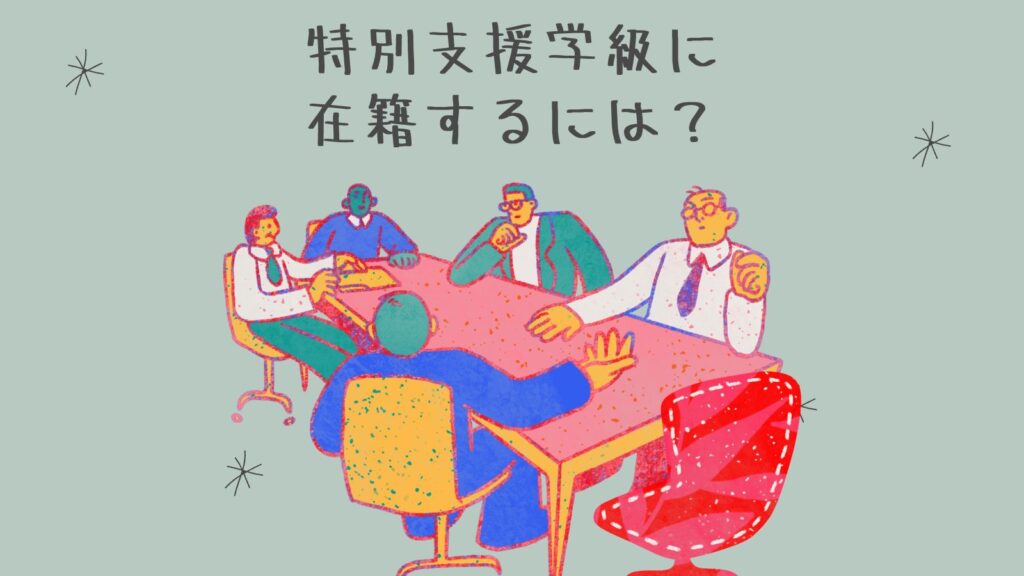
入学後の1年生が学校探検をした時に、「どうしたら〇〇学級に入れるの」とよく質問されます。通常学級の担任も正確には知らない方が多いのですが、私の自治体では以下の手順で行われます。


①保護者が教育センターに相談依頼する
→教育センターで相談の結果、保護者が特別支援学級を希望する
②保護者が教育支援委員会での審議の依頼をする
③教育委員会が教育支援委員会の調査員を派遣依頼して担当の調査員が該当の子供の調査をする
④保護者が指定された児童精神科に子供を連れて行き診察を受ける
⑤保護者が教育センターに面談の予約を取り、子供は知能検査を受け、保護者は面談する
⑥教育支援委員会が開かれ審議をする
⑦「知的の特別支援学級が適切である」という判定を受ける
⑧地域の特別支援学級に入る
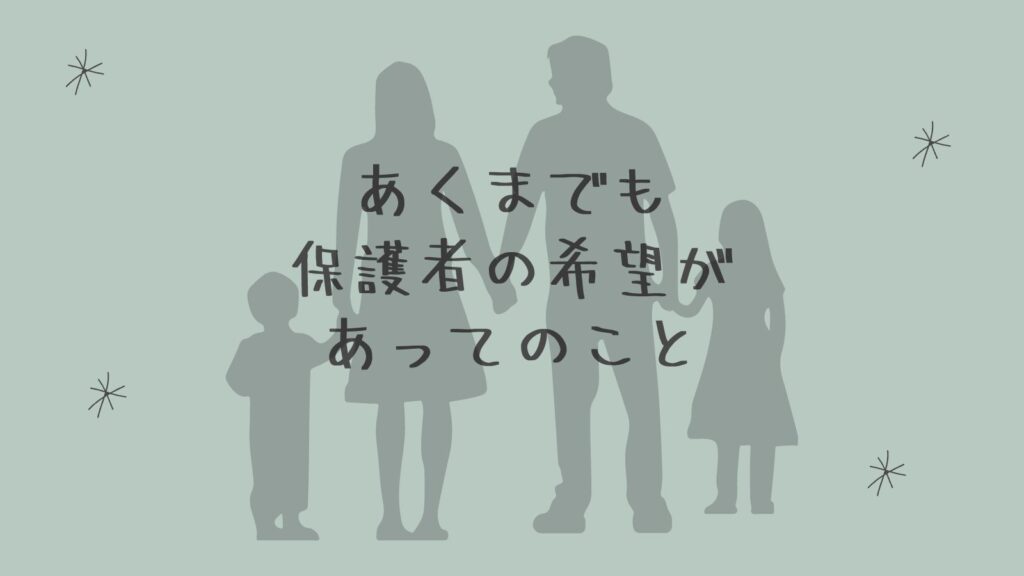
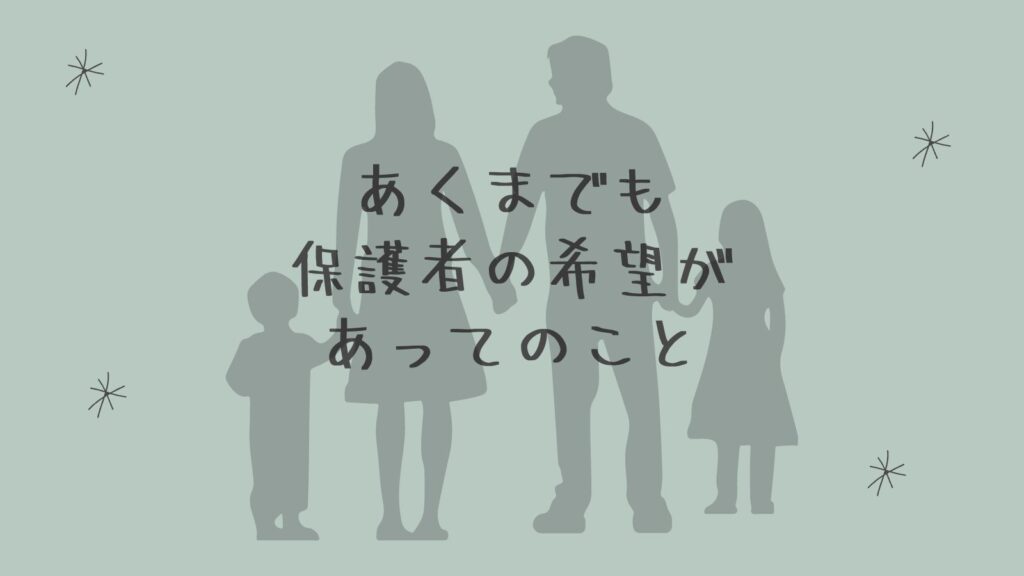
あくまでも「保護者の希望が優先される」ことがポイントです。
教育支援委員会での調査と判定基準
「就学指導委員会」と呼ばれていた名称が「就学支援委員会」「教育支援委員会」などと変更になりました。ここでは、児童の障害の程度や特性、通常の学級で十分な教育を受けられない理由などを検討し、特別支援学級への就学を勧告するかどうかを決定します。
私の勤務していた自治体では、特別支援学級の担任はほぼ全員調査員として自分の学級を自習にして保育園や幼稚園、小学校に調査に行きました。
教育センターから電話で「○○保育園の△△くんの調査をお願いします」「教育支援委員会は○月○日なのでその2週間前には調査を完了してください」と言われます。
調査員は、電話帳やネットで園の電話番号を調べ都合の良い日時を調整して園長に相談します。自分の学級の自習計画を立て、教材を準備し、調査に行きます。調査はだいたい2〜4時間くらいで、帰ったから調査用紙を書くのに1〜2時間かかります。さらに教育支援委員会の会議にも行かなくてはならないと、また自習計画・・・です。
仕事が増えても、何の手当てもありません。正直、就学時検診と一緒で「就学調査は教育委員会の仕事」だと思います。
調査員をしていた時に担当者から「8人の小集団にいて教師の指示が理解できること」を念頭に調査するよう言われていました。小集団で指示理解が難しいと個別対応をする必要があり、「特別支援学校が適切である」と判定されます。ですが、先ほどの通り「保護者の希望が優先される」ため重度重複の子供も入ってきます。



ただでさえ、引率が多い特別支援学級担任なのでできたら自習にはしたくありません。
「保護者の希望が優先」と言っても
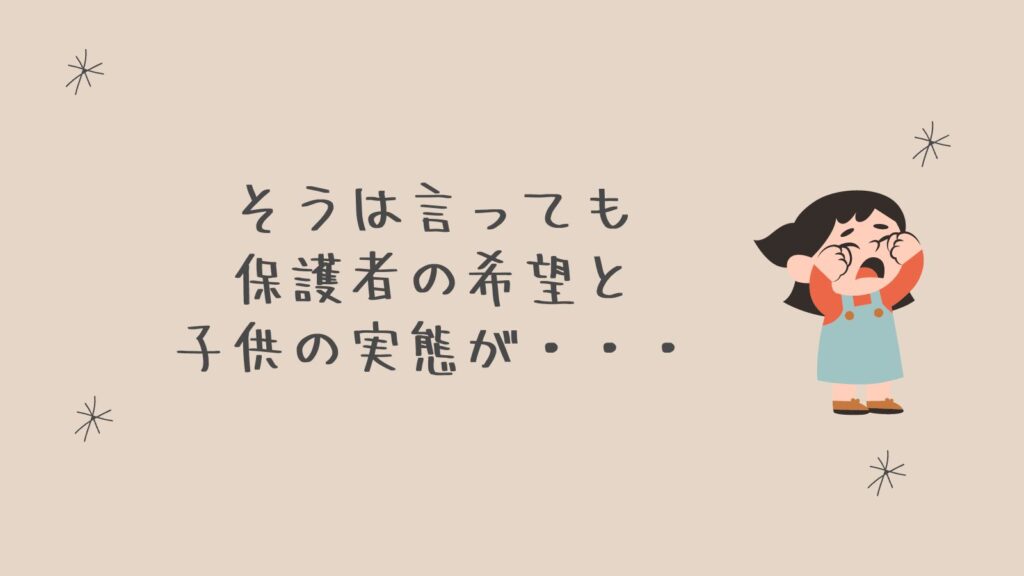
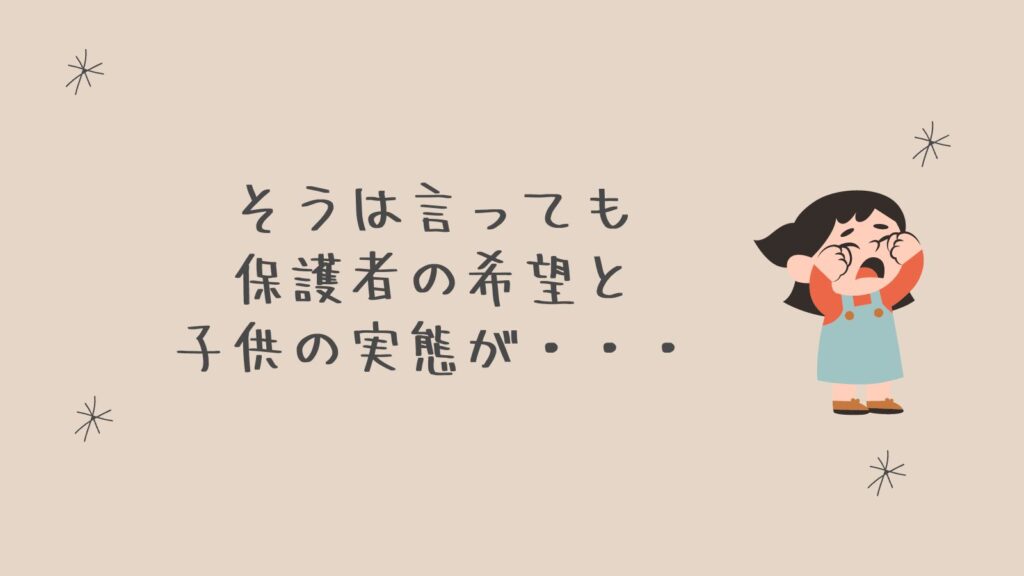
実際のところ、「保護者の希望が優先」と「子供の実態」、この2つが噛み合わないことが多々あります。その場合は保護者の希望が優先されるため、現場は大変です。私は入学前の面談で保護者に「特別支援学級は常時個別の対応はできません。あくまで小集団の学級です」とお伝えしてきました。出来るだけこの場に、管理職や特別支援コーディネーターなど担任外の教員も同席してもらいましょう。



小集団と言っても、最大8人の集団なんです。普通の家族より人数は多いんですよ〜!!
1年生は、実態がまだ分からないところが多いので、特別支援学級でもいろいろな経験を積むのは良いと思いますが、「学習の保障」という面では難しいと思っています。
過去に「重度知的障害で自閉重複障害もあり常時見守りが必要」という児童Aくんが在籍してた時に、全面保護者の付き添いをお願いしました。基本的にどの新1年生にもしばらく付き添いをお願いし、大丈夫な子供は付き添いを「徐々になし」にしていきました。もちろんお仕事の関係など家庭の事情は考慮しますが、安全を確保することを優先すると、教員がつきっきりになる必要があり他の児童の指導ができなくなります。


この辺りは非常にデリケートなことであり、児童の実態や学校の様子、管理職の考えもあるため、慎重な対応が必要になります。他の保護者の目も気になりますが、事例を通した方が分かりやすいためAくん(仮名)の事例で詳細をお伝えしたいと思います。



20年近く前、合理的配慮がまだない時代です。今はここまで保護者にお願いできないと思います。
4月入学式では体育館を走り回る。
他の1年生はすぐに昇降口から1人で教室に入ることができたため、すぐに保護者付き添いはなしに。
Aくんだけ新しい場所は不安。毎日情緒不安定になり教室から出ることがある。食事、トイレなど常時介助が必要。
母にできるだけ付き添いをお願いした。その際、他の児童の学習面について口外しないようお願いする。
1学期間終えて母より「体調が悪い」とのこと。付き添いを体育と校外に出る時のみにする。
学習は1人でできる課題(型はめ、パズルなど)とみんなと一緒にできそうなことのみにする。→マンツーマンで、つきっきりでしか出来ないことはしない!!
| Aくん | その他の1年生 | |
|---|---|---|
| 入学式 昇降口から教室まで 身辺面 学習 自立活動・体育 校外学習 | 走り回る 教室に行かず、目に入った方へ行く 食事、トイレなど常時介助 型はめ、なぐり書き 具体物のマッチングなど 1人で印の場所に立てない 模倣できない 母と一緒に | 他の児童と一緒にいられる 1人で行く 1人でできる 自分の名前が分かる 文字の視写ができる 高学年を模倣して体操する 他の児童とグループで行動する |
目に入った「もの」や「こと」に気を取られやすく、どこに行くか分からなかったため、支援員さんが付き添っていました。給食も付きっきりとなるため、支援員さんは別の時間に給食をとってもらいました。Aくん自身学校に慣れてきたところはありましたが、2学期からは支援学校の見学を勧め、3学期にはお母さんが3月で転校することを決断しました。


Aくんのケースは支援員さんがついてくれたことで、保護者の付き添いをなしにすることができました。当時7人の児童で他に身辺の介助が必要な児童Bくんもいたため、Aくんのお母さんとしては「Bくんもいるのに・・・」と思われていたことと思います。が、Bくんは模倣ができて、好きな題材を使った学習なら参加できます。
このことから、調査員をしているとき、「粗大な模倣ができる」ことも判定材料にしていました。
通常学級から特別支援学級への転級について


通常学級から特別支援学級への転級の目的は、学習困難や発達上の障害を抱える子供たちに対し、適切な支援と教育を提供することです。特別支援学級では、子供の個別のニーズに合わせた教育プログラムが実施され、最適な学習環境を提供することが目指されます。
通常学級から特別支援学級への転級の対象は、学習困難や発達上の障害を抱えた子供たちです。具体的な対象としては、知的障害、自閉症スペクトラム障害、情緒・行動障害などが挙げられます。子供の個別のニーズや発達段階に応じて、転級が検討されます。
通常学級から特別支援学級への転級の特徴は以下のようになります。
- 個別の学習ニーズへの対応→特別支援学級では、子供の個別の学習ニーズに合わせた教育プログラムが提供されます。教育カリキュラムや指導方法が個別化され、子供が自身のペースで学ぶことができます。
- 専門的なサポートの提供→特別支援学級では、専門の教員や支援スタッフが子供をサポートします。特定の障害に特化した知識やスキルを持った専門家が教育プロセスに参加し、子供の発達や学習を支援します。
- 小集団の学習環境→特別支援学級は、一般的な通常学級よりも少人数で構成されるため、子供にとってより支援的な学習環境を提供します。小集団の学習グループによって、教育者と子供との密な関係が築かれ、より個別化された指導が可能となります。
- 社会的な学びの促進→特別支援学級では、子供の社会的なスキルやコミュニケーション能力の発達も重視されます。グループ活動や協力学習の機会が提供され、子供が相互に支え合いながら成長することが期待されます。
- 必要な支援の提供→特別支援学級では、子供の学習に必要な支援が総合的に提供されます。個別の支援計画や個別の目標設定が行われ、学習支援だけでなく、心理的なサポートやリハビリテーションサービスなども提供されることがあります。
通常学級から特別支援学級への転級は、学習困難や発達上の障害を抱えた子供たちに対して、より適切な教育環境を提供できます。特別支援学級では、子供の個別の学習ニーズに合わせた教育プログラムや専門的なサポートが提供され、小規模な学習環境での学びが促進されます。子供の発達や学習を総合的に支援するために、個別の支援計画や個別の指導計画も作られます。
私の経験から、4年生で転級するケースが非常に多く感じています。それは、通常の学級の授業が抽象的な内容が多くなり、学習に遅れを感じることで転級を検討するきっかけになると考えられます。
Cくんの事例
4年生男子の保護者のCさんからは、悩みに悩み抜いて「転級させた」と伺いました。
「この子の人生を狂わせてしまったのではないだろうか」
「私が決断してよかったのだろうか」
と本当に苦しかったことと思います。
しかし、子どもが卒業する時に
「ぼくを○○組に入れてくれてありがとう」
という言葉に、安堵したとのこと。
正解が分からないからこそ、教員としてもしっかり受け止めたい事例です。
特別支援学級から通常学級への転級について


特別支援学級から通常学級への転級の目的は、子供たちが通常の学級での学習や社会生活に適応し、可能な限り自立した生活を送ることです。特別支援学級での支援を経て、子供たちが通常学級での学習や社会的な関係を築く能力を身につけるられたと考えられます。
私自身、小学校特別支援学級担任歴22年のなかで、特別支援学級から通常学級への転級のケースは1度だけです。
特別支援学級から通常学級への転級の対象は、就学時の判定から時間が経過し、子供の知的発達が伸びて通常の学級での授業を理解できること、大人数での集団の中で過ごせること、子供本人や保護者の希望がある子供です。
特別支援学級から通常学級への転級の特徴
特別支援学級から通常学級への転級は、以下の特徴を持っています。
- 適切なサポートの提供→転級の際には、子供たちが通常学級で必要なサポートが適切に提供されます。これには、個別の学習支援や特別な教育計画の作成、必要な補助具や支援者の手配などが含まれます。
- 転級支援の実施→転級のプロセスでは、子供と関係する教育者、専門家、保護者、学校関係者などが協力し、スムーズな転級を支援します。個別のニーズに応じた適切な移行計画や指導方針が策定され、子供が適切なサポートを受けながら通常学級での学習に取り組めるようになります。
- 社会的な適応の支援→通常学級では、子供は異なる環境や友達との関係を築く必要があります。そのため、転級支援では社会的な適応のサポートも重要です。コミュニケーションスキルや人間関係の構築、自己表現能力など、社会的な適応力を高めるための指導やプログラムが提供されます。また、必要に応じて学級内の配慮や合理的な配慮の提供も行われます。
特別支援学級から通常学級への転級は、特別なニーズを持つ子供が一般の学級での学習や社会生活に適応するための過程です。個別の学習支援や転級支援の実施、社会的な適応の支援が行われます。これにより、子供は自己成長や自立を促進し、通常学級での学習や社会的な関係を築く能力を身につけることが期待されます。
なお、私が経験した子供は、知的障害が超軽度で情緒障害の子供が、年齢が上がって情緒が落ち着き、特別支援学級から通常学級への転級があるというケースになるように思います。
Dくんの事例
他県から転入してきたため就学調査の結果は不明。長期欠席で週1回程度の登校。学習に取り組む姿勢はなく、実態がわからない。
徐々に登校するようになり、時々キレて友達につかみかかる場面があるが、学力は順調に伸びる。
6年生へ進級の際に中学への進学のため、就学調査。知的障害なしのため通常学級へ。週に1日から通常学級での授業に参加をしたが問題なくいられた。
他県の調査の基準が不明なのと、家庭環境が不安定なこともあり、小学校入学時は知的障害の判定を受けたが、本当は情緒障害だったと考えられる。情緒も年齢とともに落ち着き学習面も取り戻せたのであろう。
通常学級か特別支援学級か、選ぶときのポイント


通常学級か特別支援学級かを選ぶ際のポイントは、子供の個別のニーズと能力に基づいて判断することが重要です。以下の要素を考慮すると良いでしょう。
- 子供の特性とニーズ→子供の発達レベルや学習ニーズ、社会的な適応力などを評価しましょう。特別支援学級は個別のニーズに合わせた小集団での教育や支援が提供されます。
- 学習環境→学級の規模、教員と生徒の比率、教育プログラムなど、学級環境の違いを考慮しましょう。特別支援学級は専門的な教育環境と支援体制が整っています。
- 教育目標と進路→通常学級では一般の学習進度に沿って進学や進路が考えられますが、特別支援学級では子供のニーズに応じた教育目標と進路が設定されます。
例えば、発達障害を持つ子供が学習や社会生活において支援が必要な場合、特別支援学級では専門の教育プログラムや支援体制が提供されます。一方、通常学級では一般の学習進度に合わせた教育が行われますが、個別の支援や教育プログラムは限られる場合があります。これらの要素を考慮し、子供のニーズに最も適した学習環境を選ぶことが重要です。
通常学級か特別支援学級かを選ぶ際には、子供の個別のニーズと能力を中心に判断しましょう。特別支援学級は専門的な教育環境と支援体制を提供しますが、通常学級では一般の学習進度に合わせた教育が行われます。子供の特性やニーズ、学習環境、教育目標と進路などを総合的に考慮し、最適な選択を行いましょう。
さらに、学区に特別支援学級がないケースもあります。通学方法や経路もしましょう。
特別支援学級卒業後の進路について


小学校特別支援学級を卒業した後は一般的に中学校特別支援学級、特別支援学校高等部に行くことが一般的な進路と言えます。しかし、子供の進路は多岐にわたります。適切なサポートや継続的な支援が提供されることで、子供は自身の能力や目標に応じた進路を選択することができます。
特別支援学級の卒業生の進路に関するデータは国や地方自治体によって収集されていますが、具体的なデータを示すことは難しいです。それぞれの子供の能力やニーズに応じて個別の進路が選ばれるため、統一的な統計データが存在しないことが一因です。
中学校特別支援学級卒業後の進路


- 高等学校進学→特別支援学校高等部に進学することが一般的です。また、特別支援学級の卒業生の中には、一般の高等学校へ進学する子供もいます。特別支援学級で培った学習スキルや自己管理能力を活かし、一般の学習環境での進学を目指すことがあります。
- 専門学校・職業訓練→特別支援学級では実践的な技能や職業訓練も重視されます。卒業後には専門学校や職業訓練機関に進学し、社会での就労や生活に向けたスキルを磨く子供もいます。
- 就労→一部の卒業生は直接就労することを選択します。就労支援のもと、社会的なスキルや職業訓練を受けながら、自立した生活を送るための就労先を見つけることがあります。
特別支援学級を卒業した子供たちの進路は多様です。子供の能力や目標に合わせて、高等学校進学や専門学校・職業訓練への進学、直接の就労など様々な選択肢があります。重要なのは、卒業後も適切なサポートや支援が継続されることです。個別のニーズに応じた進路選択と継続的な支援が子供たちの自立と幸福な未来への道を拓くのです。
特別支援学校高等部卒業後の進路


特別支援学校高等部を卒業した生徒の進路は、個々の能力や適性に応じて多岐にわたります。進学や就労、社会参加など、様々な選択肢があります。重要なのは、卒業後も適切なサポートや支援が提供されることで、生徒が自身の目標に向かって自立した人生を送ることができるようになることです。
特別支援学校高等部卒業生の進路に関する具体的なデータや統計は一般的には公開されていません。ただし、特別支援学校は就労支援や進学支援など、卒業生の社会参加を支援するプログラムや取り組みを行っています。また、国や地方自治体によって進路調査が実施され、一部のデータが収集されている場合もあります。
- 高等学校進学→特別支援学校高等部卒業生の中には、実態により一般の大学や専門学校へ進学する生徒もいます。特別支援学校で培った学習スキルや自己管理能力を活かし、一般の学習環境での進学を目指すことがあります。
- 職業訓練・就労→卒業生の一部は職業訓練機関へ進学し、職業スキルを磨いたり、就労支援を受けながら社会での就労を目指すことがあります。特別支援学校では、実践的な職業教育や就労支援を重視しています。
- 社会参加プログラム→卒業生の一部は、社会参加プログラムや就労移行支援などの取り組みを通じて、地域の活動やボランティア活動に参加したり、社会的な役割を果たすことを目指すことがあります。
特別支援学校高等部を卒業した生徒の進路は多様であり、個々の能力や目標に合わせた選択が行われます。高等学校進学や職業訓練、就労など、それぞれの生徒の個別のニーズと目標に基づいて進路が選ばれます。特別支援学校高等部は、生徒の自己実現と社会参加を支援するために様々なプログラムやサポートを提供しています。
特別支援学校高等部卒業生の進路決定のポイント


- 個別の能力と適性の評価→卒業生の能力や適性を総合的に評価し、適切な進路を選ぶための情報を収集します。これには、学力、社会的スキル、コミュニケーション能力、職業適性などが含まれます。
- 就労支援プログラム: 特別支援学校では、職業訓練や就労支援プログラムを提供しています。卒業生が職場で必要なスキルを習得し、就労に向けた準備を行うことができます。
- 進学支援: 一部の卒業生は、専門学校や大学への進学を選択する場合もあります。特別支援学校は、進学準備や必要なサポートを提供し、卒業生が学術的なキャリアを追求するための支援を行います。
- 地域の社会参加: 卒業生は地域の社会活動やボランティア活動に参加することを選択することもあります。特別支援学校では、地域との連携や社会参加プログラムを通じて、卒業生が自己実現や社会的な関与を果たすことを支援します。
特別支援学校高等部卒業後の進路決定には個別のニーズや能力を考慮し、適切なサポートや指導が必要です。家族や教育関係者との密な連携や相談が重要であり、各生徒が自己の能力を最大限に発揮し、自立した社会生活を送るための進路が選ばれることを目指します。
また、成人後も地域と繋がりが持てるような工夫や支援が様々あります。これらの工夫や支援を受けて、卒業生や家族が孤独にならないような社会を作っていくとともに、充実した社会生活が過ごせるようにしていきましょう。
障害のある子どものための支援


障害のある子どものための支援は、個別のニーズと特性に基づいた包括的なアプローチが重要です。特別支援学級や関連する支援サービスを通じて、教育、社会参加、自立などの目標を達成するための多様な支援が提供されます。
障害のある子どもへの支援に関しては、国や公共団体が数多くの法律やガイドラインを制定しており、その基盤が整っています。例えば、日本では「発達障害者支援法」があり、障害のある子どもへの教育と支援の権利を保障しています。また、教育委員会や学校によっても独自の支援方針やガイドラインが策定されています。
障害のある子どものための具体的な支援の例


- 個別支援計画の策定→障害のある子ども一人ひとりに合わせた個別支援計画が作成されます。これには、目標の設定や必要な支援内容、評価方法などが含まれます。
- 特別支援教室や通級指導教室→特別支援学級や通級指導教室など、学校内での専門的な支援が提供されます。ここでは、学習や社会的なスキルの向上を支援するためのプログラムや指導が行われます。
- 個別の補助やアセスメント→障害のある子どもに必要な補助具や支援技術が提供されます。また、専門家によるアセスメントや診断を通じて、適切な支援方法やアプローチが選ばれます。
- サポート体制の構築→学校や地域の専門職員、家族、地域の支援団体などが協力し、総合的なサポート体制が構築されます。これにより、子どものニーズに合わせた包括的な支援が実現されます。
特別支援学級は、まるでカラフルなレインボーのような支援です。普通の学級は1つの色で構成されているけれど、特別支援学級は多くの色が集まってできています。それぞれの色は、個々の子どもの特別なニーズや個性を表しています。
この特別支援学級のレインボーには、赤色のサポートがあります。赤色は困難なときに助けを借りることができるサポートの色です。例えば、難しい問題に取り組むときや友達との関係に悩んだとき、赤色のサポートが手を差し伸べてくれます。
また、青色の理解があります。青色は周りの人たちが子どもたちの気持ちや困難を理解しようとする色です。特別支援学級では、教師やクラスメートが子どもたちの状況を理解し、共感することが大切です。青色の理解があることで、子どもたちは安心して学ぶことができます。
そして、黄色の個別のサポートがあります。黄色は子どもたちの個々のニーズに合わせたサポートの色です。特別支援学級では、子どもたちが必要なサポートを受けながら成長していくことができます。例えば、学習のペースや方法、コミュニケーションのスタイルなど、黄色の個別のサポートが子どもたちをサポートします。
特別支援学級は、スペシャルな支援が詰まったカラフルなレインボーのような存在です。子どもたちの個々のニーズや困難に合わせて、様々な色が輝きます。そこで子どもたちは、安心して学び成長することができます。
支援についての私の考え


特別支援コーディネーターとして、心理士の方に相談した時に、「障害名を決めるのは医師だけど、教員側が暫定的に障害名を決めることで支援の見通しがつき支援しやすくなる」と言われたことがありました。
また、合理的配慮としてよく視覚的なサポートとして板書したり、ワークシートを用意したりしますが、これは通常の子供にも大いに役立つものです。
障害がある、なしに関わらず、できる支援は全部するのが最適解ではないかと考えます。ただし、学校現場は人手不足なので、十分な人手の確保は教育委員会に望まれますし、教員の働き方改革も進めていく必要があります。
特別支援学級に入る基準のQ &A
特別支援学級のIQ基準は?
知的障害の特別支援学級は、概ねIQ70以下を基準とします。
支援学級はどんな子が通うのですか?
特別支援学級は、比較的軽度の障害がある子供に対し、一人ひとりにきめ細かな教育を行うために、小学校の中に特別に設置された少人数の学級です。障害の種別ごとに学級が用意されており、知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、弱視、難聴、言語障害、自閉症・情緒障害があります。
グレーゾーン IQいくつ?
「グレーゾーン」とは、 知能指数(=IQ)で「平均的」「障がい」とされる部分の狭間(IQ71以上85未満)にあたるところが「グレーゾーン」(境界知能)と呼ばれています。
通常の学級(普通クラス)のIQはいくつですか?
IQ (知能指数)80以上と言われています。しかし、現状の就学時検診(次年度新1年生になる子供が受ける健康診断等)では、集団で簡単な知能検査をしていますが、正確な知能検査については保護者が希望した場合のみ受けています。
特別支援学級に入る基準のまとめ


特別支援学級に在籍するための最低限のポイントは、「集団参加」と「模倣」だと思います。
言い換えると、「みんなと一緒にいられること」「上手くできてなくてもいいので、やろうとすること」で、子供は伸びていきます。
Aくんのケースは1例ですが、もし
「この場合はどうなの?」
「個別にもっと詳しく知りたい」
という方はどうぞご相談ください。
\ 一人で抱え込まないで! /
公式からのお得なお知らせ
ぷーたのX (Twitter):https://twitter.com/aki2000oakp
Kindle出版:「特別支援学級の担任になって」と言われたら読む本
Kindle出版:「特別支援学級の担任になって」と言われたら読む本〜国語編〜
Kindle出版:「特別支援学級の担任になって」と言われたら読む本〜体育編〜
本で学びたい方はこちら。
Kindle出版:「特別支援学級の担任になって」と言われたら読む本

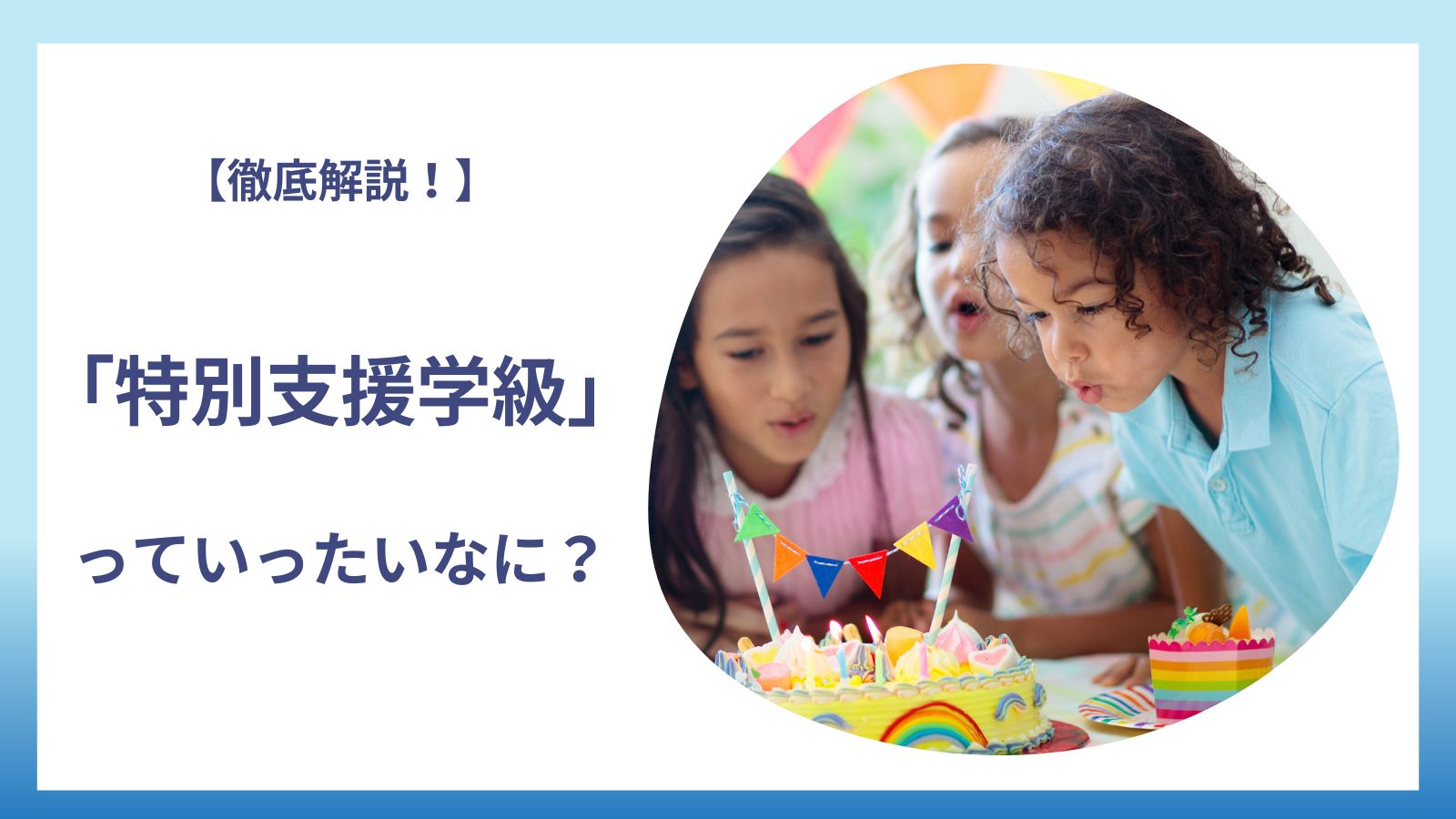




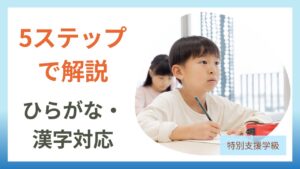
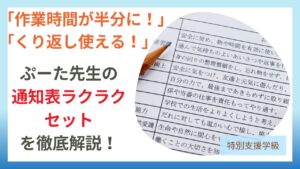
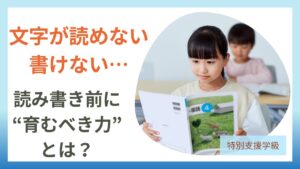
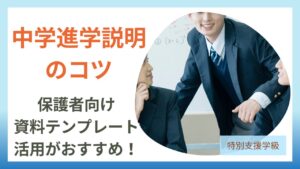
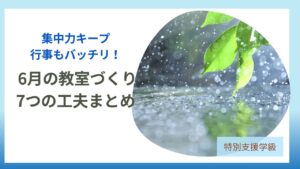
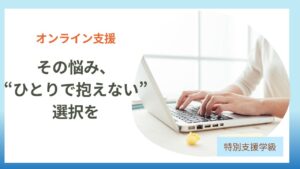
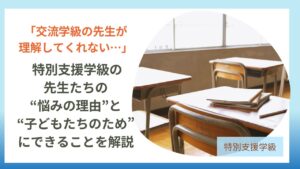
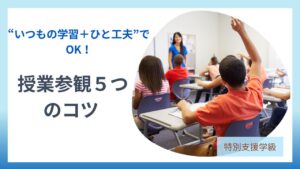
コメント