「夏休みの宿題、どうしよう…」
毎年この時期になると、そんな声が聞こえてきます。
プリント?絵日記?自由研究?──それだけで終わらせていませんか?
私が特別支援学級で実践していたのは、“暮らしそのもの”を宿題にする工夫です。
子どもが自分で考え、手を動かし、「できた!」を積み重ねられるように。
今回は、毎年好評だった封筒を使った宿題セットの作り方と、家庭での家事・調理を通じた「生きる力」アップのヒントをまるっとご紹介します。
夏休みを、ただの休みにしないために──
先生も保護者も、無理せず、子どもと一緒に楽しく過ごせるアイデアをお届けします。
最後までお読みいただくと今すぐ使える特典がもらえます!!
📦 ① 封筒を使った「宿題セット」の工夫
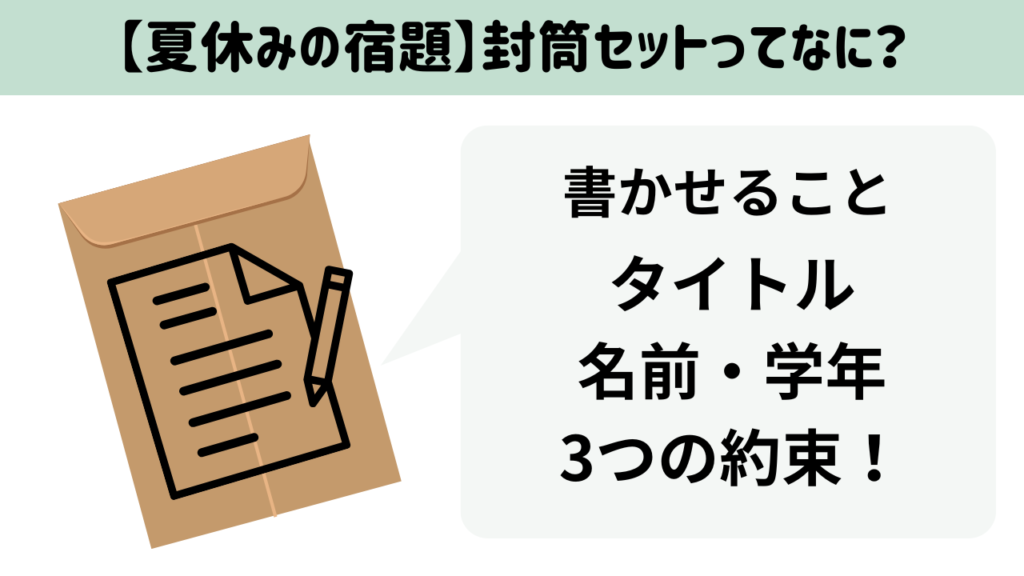
夏休みの宿題は、A4サイズの封筒を1人1枚用意するところから始めます。
私はリサイクルの封筒を使っていたので、A4の紙を貼っていました。もちろん作業は子供自身がします。
🔹封筒の表に書かせる内容
- タイトル:「夏休みの宿題 2025」
- 名前・学年
- 宿題に関する“3つの約束”を書かせます
🔸私がよく書かせていた「3つの約束」
- 宿題をする時間を決める
- 姿勢よく、集中して取り組む
- 丸つけはおうちの人にお願いする
「丸つけを保護者にお願いする」のには2つの理由があります。
- 子どもの実態を保護者にも知ってもらう
- 間違いや理解不足をすぐにフィードバックできるようにするため
学級だよりなどでも、こういった意図を保護者にしっかり伝えていました。
📚 ② 宿題の内容:復習+実生活を組み合わせて
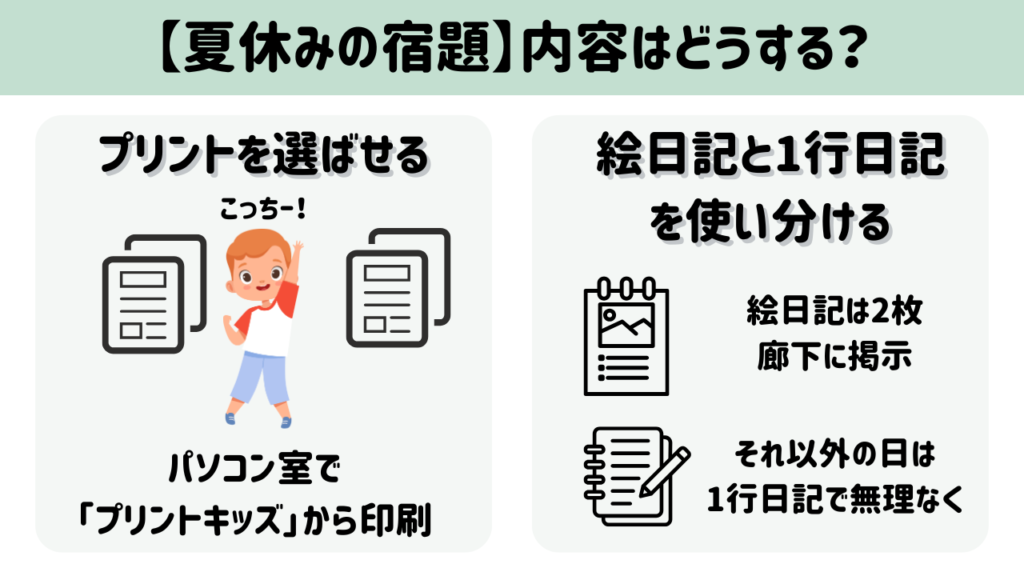
夏休みの宿題の中心は「復習プリント」ですが、その他私は以下のような工夫をしていました。
🔹プリント類はパソコン室で選ばせる
- 例えば:「プリントキッズ」などのサイトから印刷
- 学年をまたいで復習できる内容を指定(例:10枚など)
※自治体によってはパソコン室がないケースもあります。ここでお伝えしたいのは夏休みの課題を「子供自身に選ばせるということ」です。
🔹絵日記と1行日記の使い分け
- 絵日記:2枚提出、廊下に掲示
- その他の日は「1行日記」にして、無理なく継続できる形に
🧹 ③ 大切なのは「家庭での活動」も学びにすること

🔸家事を宿題に
お皿洗い・洗濯・掃除など、子どもができる家事を宿題に入れていました。
実際に、修学旅行で子どもが家にいなくなると「家事が回らない」と困っていた保護者もいるほど、しっかり家のことをしていた子もいました。
AIの時代になっても、生活スキルは絶対になくならない学びです。
🍳 ④ 調理も宿題に!かんたんレシピで家族と体験を
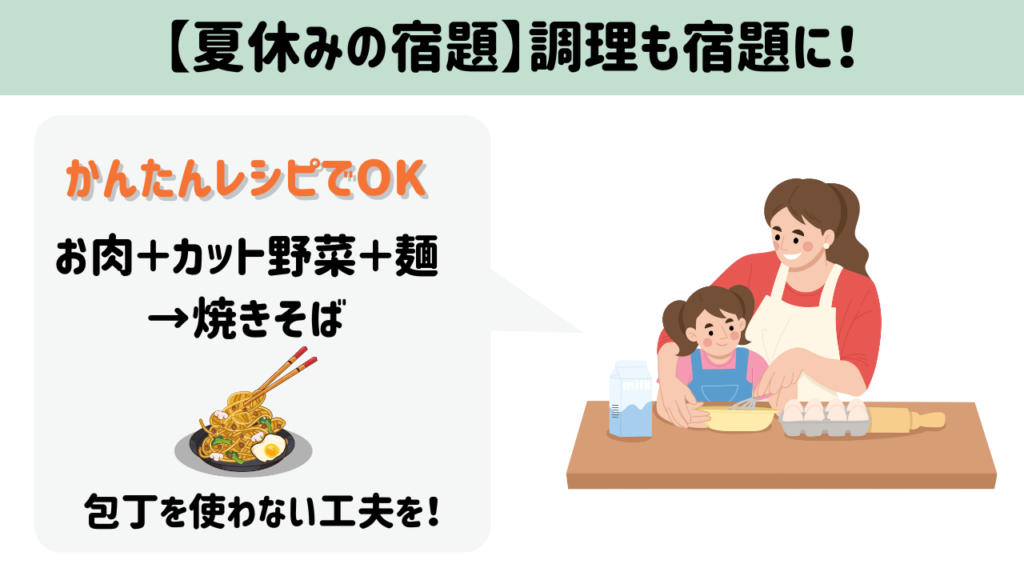
長期休みだからこそ、家族で一緒に料理する機会をもってほしい。
私は「休み中2回の調理活動」を宿題にしていました。
おすすめは…
- 豚こま+カット野菜+麺 → 焼きそば/焼きうどん
- 簡単レシピ:卵かけご飯・納豆ご飯
- 包丁を使わなくてもできる工夫を
災害時など「自分で食事をつくれる力」は命を守ることにもつながります。
以下に、動画やメルマガを見た先生や保護者から寄せられそうな「想定される質問」と、それに対する回答を5つご用意しました。先生にも保護者にも共通する視点で作成しています。
【夏休みの宿題どうしてる?】「封筒セット」と家庭での生活力アップの工夫のQ&A 5選

- 「丸つけを家庭でやってもらうのが難しいです。共働きで時間がとれません…」
-
ご家庭の事情により難しい場合ももちろんあります。その際は「○をつけること」よりも、「おうちの人と一緒にプリントを見返す」ことが目的だと伝えるのがポイントです。
朝食のときに1枚だけ見る、週末にまとめて一緒に確認する、など無理のない形でOKです。「見守ってもらえる環境」があるだけでも、子どもは安心して取り組めます。 - 「家事の宿題は、やらない家庭もあるのでは?」
-
もちろんあります。その場合も“やった・やらなかった”の評価ではなく、「やってみようとしたこと」「家庭での会話のきっかけになったこと」に意味があります。
プリントに「やった家事を書いてみよう」などの欄を設けておくと、「このくらいならできそう」と気づけたり、取り組みやすくなりますよ。 - 「調理活動が危ないのでは?火や包丁が心配です…」
-
安全面の不安がある場合は、「包丁を使わないメニュー」からスタートするのがおすすめです。
たとえば、
・おにぎりを握る
・トースターでパンを焼く
・レンジで温めるだけの野菜スープを作る
など、子どもが一人でできる「簡単だけど達成感のあるメニュー」から始めると安心です。 - 「絵日記2枚でいいんですか?もっと書かせたいです」
-
もちろん、意欲がある子はたくさん書いてもOKです!
ただ「毎日書かなきゃ」というプレッシャーで手が止まってしまう子もいます。
絵日記を2枚にするのは、“誰でも無理なく達成できる”ラインを設けるためです。
あくまで「最低ライン」ですので、もっと書きたい子はどんどん書いてもらって大丈夫です。 - 「特別支援学級の子たちには、宿題の量をどう決めればいいですか?」
-
基本は「できる量を一緒に決める」のがベストです。
学年や習熟度で一律にするのではなく、「その子にとっての達成感」が得られる範囲に調整してあげることが大切です。
たとえば、プリントを多めに配って「この中から選んで○枚やってね」と伝えるなど、選択肢のある出し方がおすすめです。
【夏休みの宿題どうしてる?】私のおすすめ「封筒学習セット」と家庭での生活力アップの工夫のまとめ
夏休みは、勉強だけでなく「生きる力」を育てるチャンスでもあります。
宿題を通して、子どもたちが自分で生活をまわせる力・家の役に立つ喜びを感じられるといいですね。
 ぷーた先生
ぷーた先生Canvaにあるテンプレを特別支援学級の子供用に修正しました!
夏休み絵日記のPDFをプレゼント中🎉

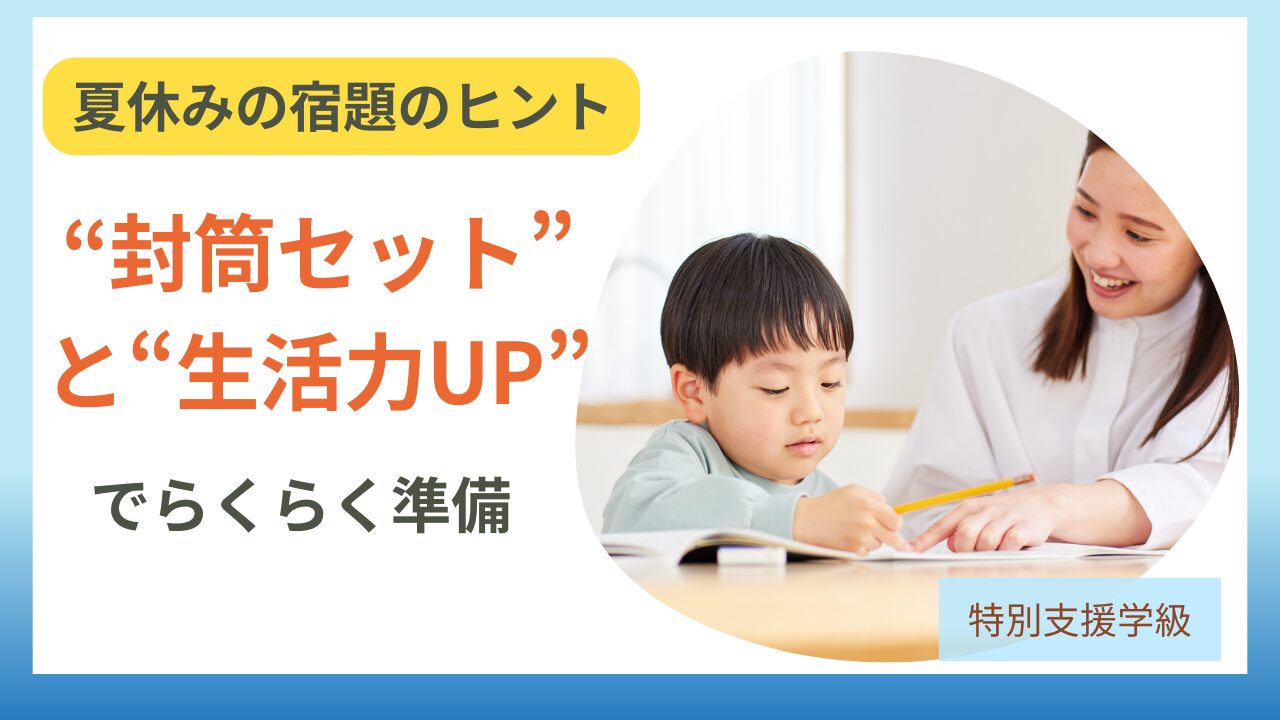




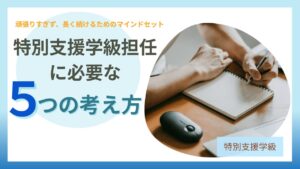
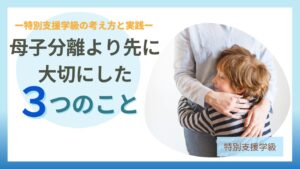

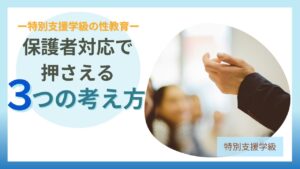
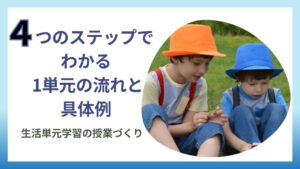

コメント