こんにちは、特別支援学級担任の先生向けにコーチングをしている、ぷーたです。
「文字がなかなか書けるようにならないんです…」
そんな相談を、現場の先生や保護者の方からよくいただきます。
確かに、ひらがなの習得は大きなステップ。でも、実は【書く】力は“いきなり”育つものではないんです。
今回は、「書く」をゴールとした、発達に応じた5つのステップをご紹介します。
「特別支援学級の担任になって」と言われたら読む本 〜国語編〜: 子どもの自尊心を高め 興味や関心を引き出す 国語の授業の作り方【教員】【教員採用】【講師】
ステップ1:まずは「見る」ことから
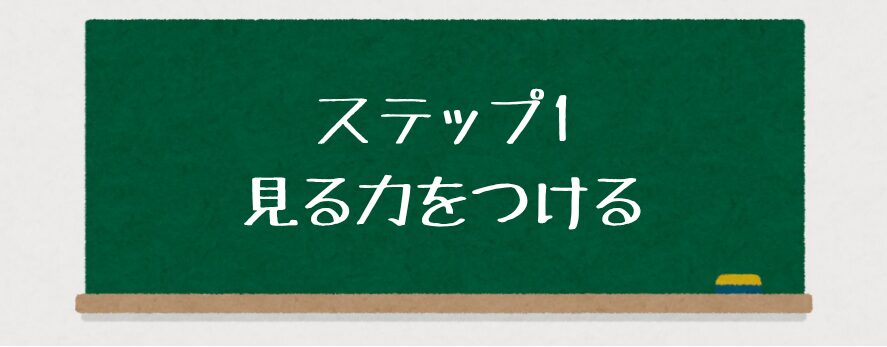
文字を覚えるには、形をしっかり“見る力”が欠かせません。
👀 どこが似ている?どこが違う?
👀 絵と文字を見比べるとどうかな?
このような「視覚的な気づき」を育てるには、絵文字カードや間違い探しが効果的です。遊びの中で自然と文字の輪郭が頭に入っていきます。
ステップ2:手を「動かす」ことに慣れる
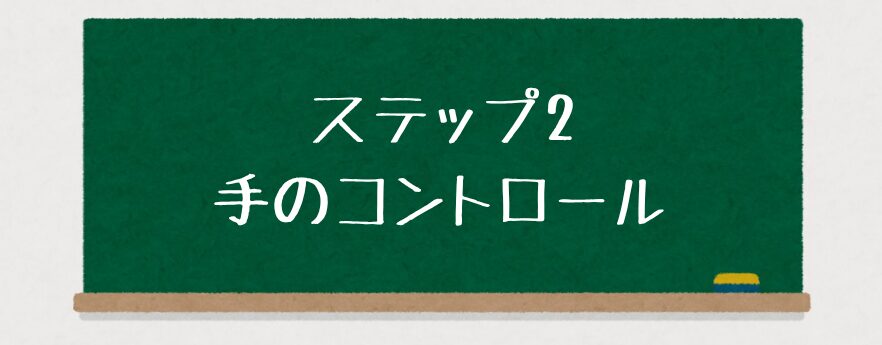
文字を書くには、目だけでなく「手のコントロール」も必要です。
✋ 指なぞり
✋ 迷路遊びやひも通し
✋ 空中に文字を書く“空書き”
こうした活動を通して、“思い通りに動かす力”が育ちます。運筆の土台づくりですね。
ステップ3:なぞって、書き順を体で覚える
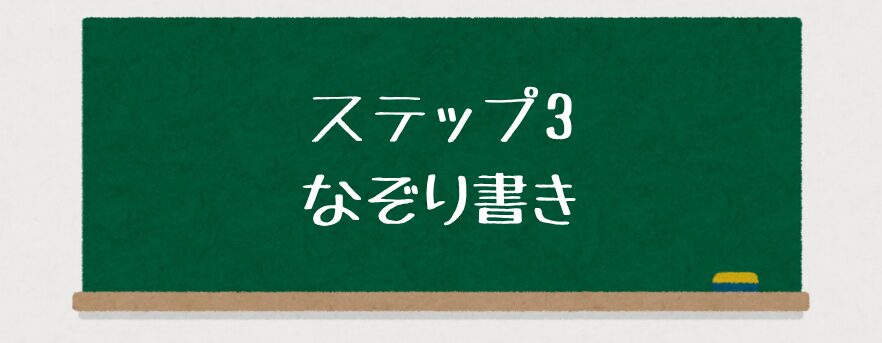
この段階でようやく「なぞり書き」が登場します。
でも、ただ形をなぞるだけでは意味がありません。できるだけ五感を使うために大きくor小さく、声に出しましょう。
💡 どこから始める?
💡 上?下?右?左?次はどの線?
そんな意識をもって取り組むことで、ただの“なぞり”が“学び”に変わります。
 ぷーた先生
ぷーた先生始点を赤、終点を青で色をつけておくと、なぞりの線が無くても書くことに近づきます。
ステップ4:お手本を見て写す
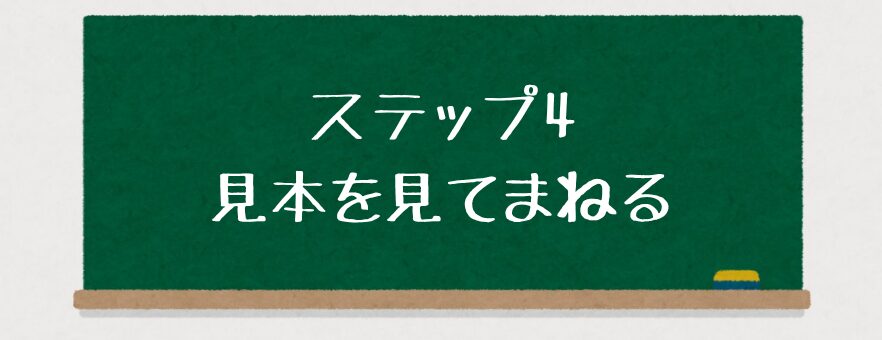
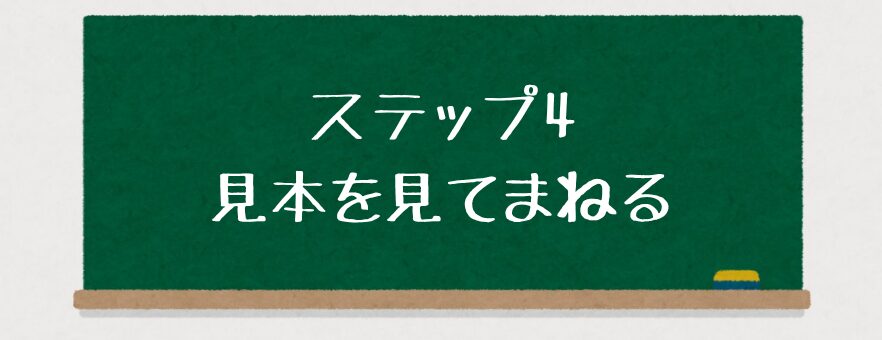
「見本を見て、まねして書く」ことができるようになると、いよいよ“書く力”に近づきます。
✍️ ひと文字ずつ、ゆっくり写す
✍️ 姿勢や持ち方も整える
このステップでは、「見てマネする力」「集中力」も育っていきます。



最初は「し」「つ」などの一文字から
ステップ5:自分の力で書く
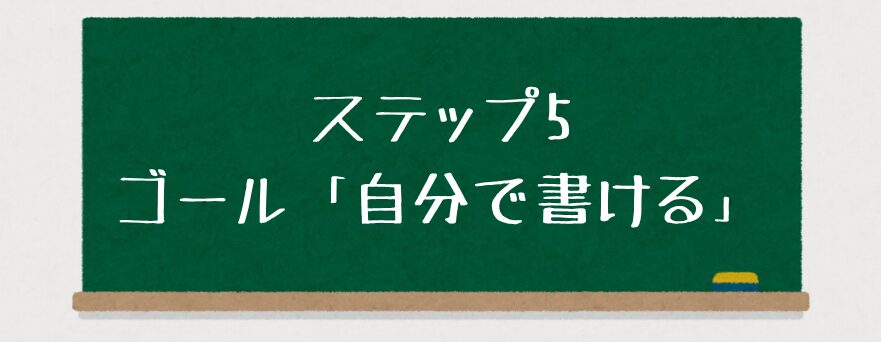
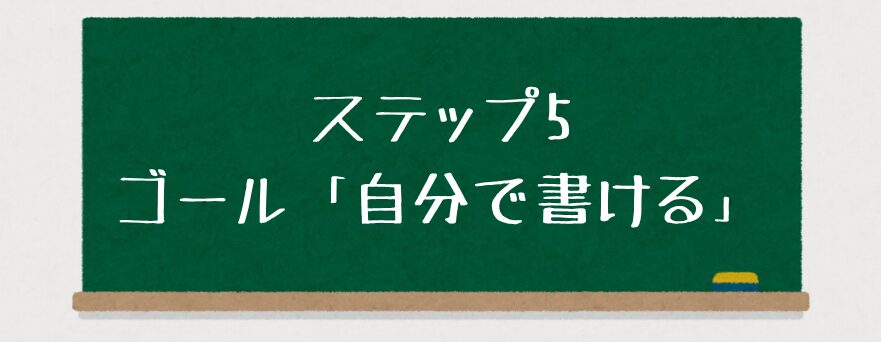
そして最後は、見本がなくても思い出して書ける状態。
これは、日々の積み重ねと小さな成功体験が導いてくれるゴールです。
📘 好きな言葉で書く
📘 名前や友達の名前を書く
📘 ひらがな日記に挑戦する
書けたことを認めてもらえると、「もっと書きたい!」気持ちが自然と育ちます。
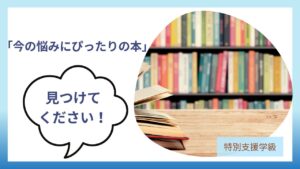
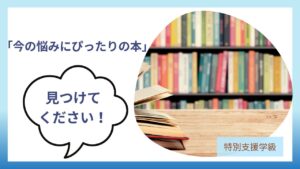
授業のヒント:漢字につなげる!6分割パズルと形あわせの工夫


ひらがなが読めるようになってきたら、漢字へのステップアップとして「6分割パズル」や「形あわせカード」がとても効果的です。
6分割漢字パズルとは?
漢字1文字を6つのパーツに切り分けたパズル。いきなり6分割が難しいようなら4分割や2分割も。
これをバラバラにして提示し、「どのパーツがどこ?」と考えながら組み立てていきます。
🟡 この活動のねらい
- 形の構成要素を理解できる
- 全体をイメージする力が育つ
- 見た目の違いに敏感になる
たとえば「雨」という字なら、上の“かさ”の部分と下の“しずく”に分けてみると、構造がよくわかります。
形あわせカード(6マスマッチング)
もうひとつのおすすめは、形の位置を一致させるマッチング活動です。
とくに書く力に課題がある子には、「形を見て、位置でとらえる」経験がとても大切です。
✅ やり方は簡単!
- 左側のマス:たて3マス × よこ2マス(全6マス)に
● 〇 △ □ などの簡単な図形を、ランダムに配置します。 - 右側のマス:同じ6マスの枠だけが描かれていて、図形は入っていません。
子どもには、「左と同じように右にも並べてね」と伝えます。
※慣れてきたら、時間を計ってゲーム形式にしても◎!
この活動で育つ力
- 図形を正確に見る力(視覚認知)
- 空間の位置を意識する力(空間認識)
- 記憶と再現の力(ワーキングメモリ)
これらはすべて、「書く」ことに必要な土台となる力です。
漢字が難しいときは「カタカナの理解」にも注目を
「漢字がなかなか定着しない」「何度練習しても覚えられない」
そんなとき、実はカタカナの理解があいまいなまま進んでいるケースがよくあります。
とくに特別支援学級では、
- カタカナとひらがなの見分けがつきにくい
- カタカナ語の意味がわかりにくい(例:バナナ、パン、テレビ)
- カタカナが「読めるけど書けない」「聞いてもイメージが浮かばない」
という声が多く見られます。
カタカナの定着が不十分だと…
- 漢字の形と混乱しやすい(例:カ・力、ロ・口)
- 文字の形への敏感さが育たず、全体を雑に捉える癖がつく
- 語彙の幅が狭まり、文章理解や作文にも影響する
支援の工夫
- ひらがなとカタカナのカードを並べて違いを比べる
- 身の回りのカタカナ語を探す遊び(パン・バス・アイスなど)
- ひらがな→カタカナ→漢字という“段階的な移行”を意識する
漢字でつまずいたら、あえて「前の段階」に戻って確認してみることが、
子どもたちの“できた!”につながる大きなヒントになることもあります。
書きが苦手な子ほど“形から入る”のがポイント
書きが苦手な子どもは、「全体をとらえる」ことに難しさがある場合が多いです。
だからこそ、まずは形を分けて見せる・組み立てるという支援が有効です。
✅ パズルで楽しみながら覚える
✅ 「見る」「分ける」「並べる」から「書く」へと段階的に進める
「ただなぞる」よりも、自分で構成した経験が、記憶と定着につながります。
書けないのではなく、“準備中”なだけ
子どもが書けないとき、つい「練習が足りないのかな…」と焦ってしまいます。
でも、本当は【どの段階でつまずいているか】に目を向けることが大切です。
書くことは、
👉「見る」
👉「動かす」
👉「なぞる」
👉「写す」
👉「自分で書く」
という小さなステップの積み重ねで、少しずつできるようになります。
つまずいているなら、ひとつ前のステップに戻ってあげればいいんです。
「書くこと」には2種類ある
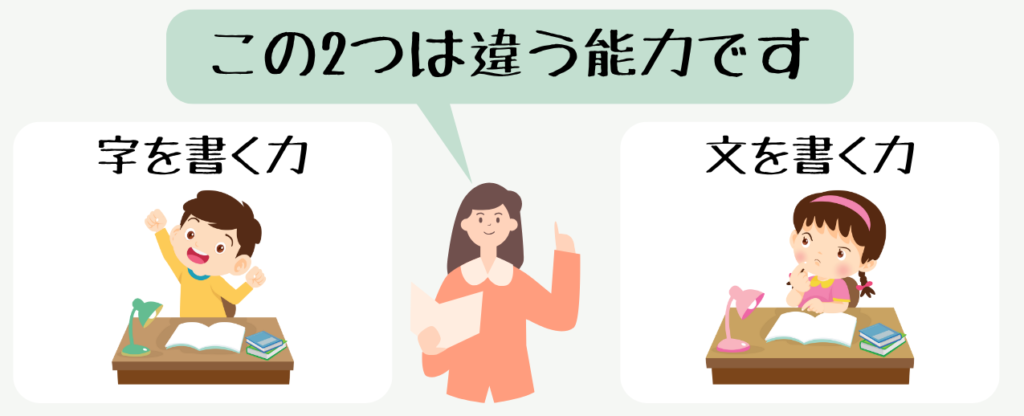
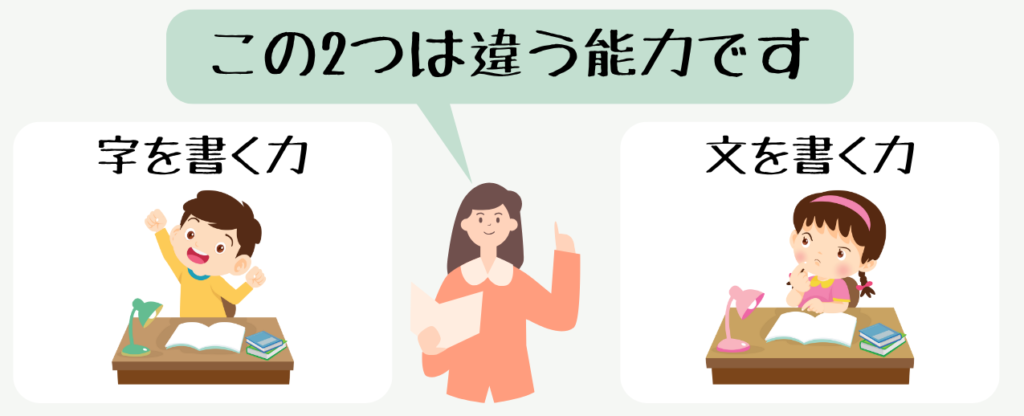
〜「字を書く」と「文を書く」は別の力〜
ひとことで「書く」と言っても、実は2つの異なる力があります。
🟦 1.「字を書く」=形を写す・再現する力
- ひらがな・カタカナ・漢字の形を正しく覚え、書く
- 手先の操作や空間認識、運筆の安定が必要
- 文字ごとの「形・書き順・向き」を記憶して再現する力
📌 この力は、「書字(しょじ)能力」とも呼ばれ、
視覚認知・手指の巧緻性・模写力などが土台になります。
🟨 2.「文を書く」=ことばを組み立てて伝える力
- 「○○がたのしかった」「わたしは○○がすき」など、
思ったことをことばで表現する力 - 語彙力・文法の理解・話す力が土台となる
- 話す・読む・聴く力と密接につながっている
📌 こちらは「構成力」「表現力」に近く、
自分の経験や気持ちを他者に伝えようとする力です。
🔍 なぜ区別が大事なの?
特別支援学級では、「文が書けない=書字ができていない」と思われがちですが、
実はどちらかだけが苦手、というケースがとても多いです。
たとえば…
- 字は書けるけど、自分の思いを言葉にできない
- 話はできるけど、文字として再現できない
など、それぞれ異なる支援が必要です。
✨ それぞれに合わせた支援を
| 種類 | 必要な力 | 支援のヒント |
|---|---|---|
| 字を書く | 形の認識・模写・運筆 | 文字カード・空書き・パズル・6分割マッチング |
| 文を書く | 経験・語彙・話す力 | 絵日記・一言作文・話してから書く支援 |
「書く=なぞり書き」だけにとらわれず、
子どもが“どの書く力でつまずいているか”を見極めることが大切です。
【よくある質問】文字が書けない子への支援 Q&A


以下は、特別支援学級で「文字が書けない」「漢字が定着しない」と感じる先生や保護者の方からよく寄せられる質問と、その答えです。
Q1. なぞり書きって本当に意味がないの?
A.
意味がないわけではありません。ただし、ただ線をなぞっているだけでは学習効果は低くなります。
「始点」「方向」「形の特徴」を意識させながら使うことで、初期段階の導入としては効果的です。
ずっとなぞりだけでは「自分で書ける」力は育ちません。
Q2. 漢字がなかなか覚えられません。どうすればよいですか?
A.
6分割パズルのように、漢字をパーツに分けて形の構造から理解する方法が効果的です。
また、似た形の文字と比べる・組み合わせてみるなど、視覚的に捉える工夫も大切です。
Q3. 書く練習を嫌がります。無理にやらせるべきですか?
A.
無理にさせるより、「できた!」が実感できる活動から始めることをおすすめします。
例:
- 絵文字カードでの読み練習
- 空書き(空中で書く)
- 形合わせパズル
こうした活動を通して、徐々に書く力を育てていくとスムーズです。
Q4. カタカナの練習って必要ですか?漢字だけでよいのでは?
A.
実はカタカナがあいまいなまま漢字に進んでしまうと、混乱やつまずきが起こりやすいです。
ひらがな・カタカナ・漢字は形の違いを認識する土台づくりとして、それぞれの役割があります。
とくに視覚的に似ているカタカナと漢字(例:ロ・口、カ・力)を区別する練習は、漢字学習にも役立ちます。
Q5. 書けるようになるまで、どれくらいかかりますか?
A.
個人差はありますが、「見る→動かす→なぞる→写す→書く」という5ステップを意識して支援することで、着実に力が育っていきます。
焦らず、子どもが自信を持てるようにサポートしていきましょう。
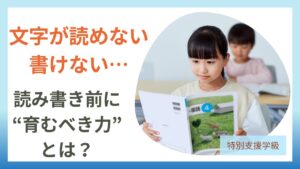
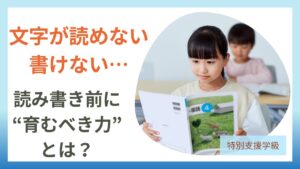
「書けない…」から卒業!特別支援で使える文字指導の5ステップ【ひらがな・漢字対応】のまとめ
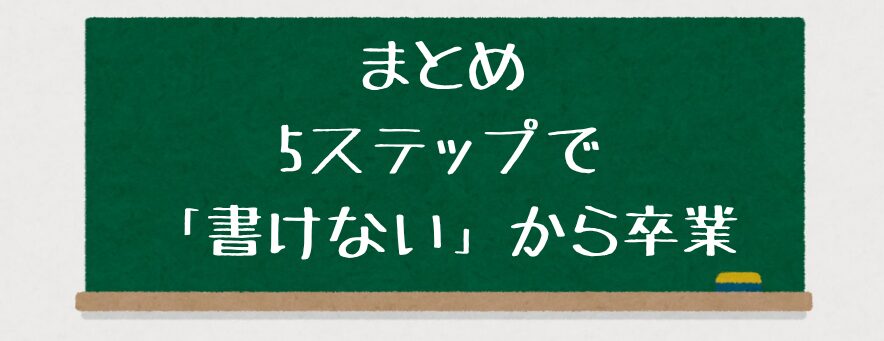
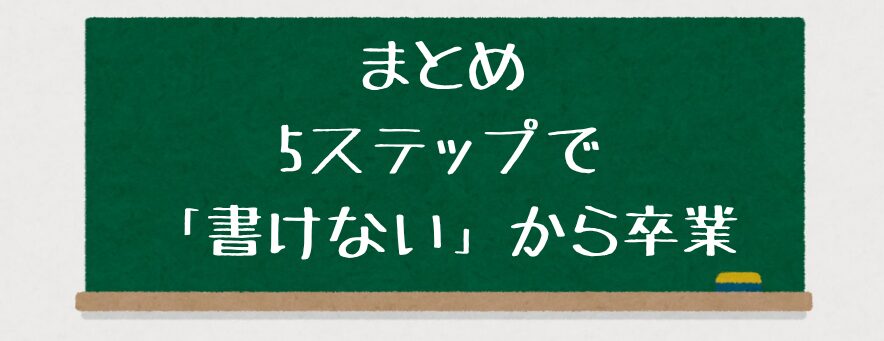
「書けるようになってほしい」という先生や保護者の想い。
それを叶えるために、一番大切なのは“焦らず待つ”ことかもしれません。
子どもたちの「できた!」を引き出せるよう、今日からできる小さな一歩を一緒に踏み出していきましょう😊

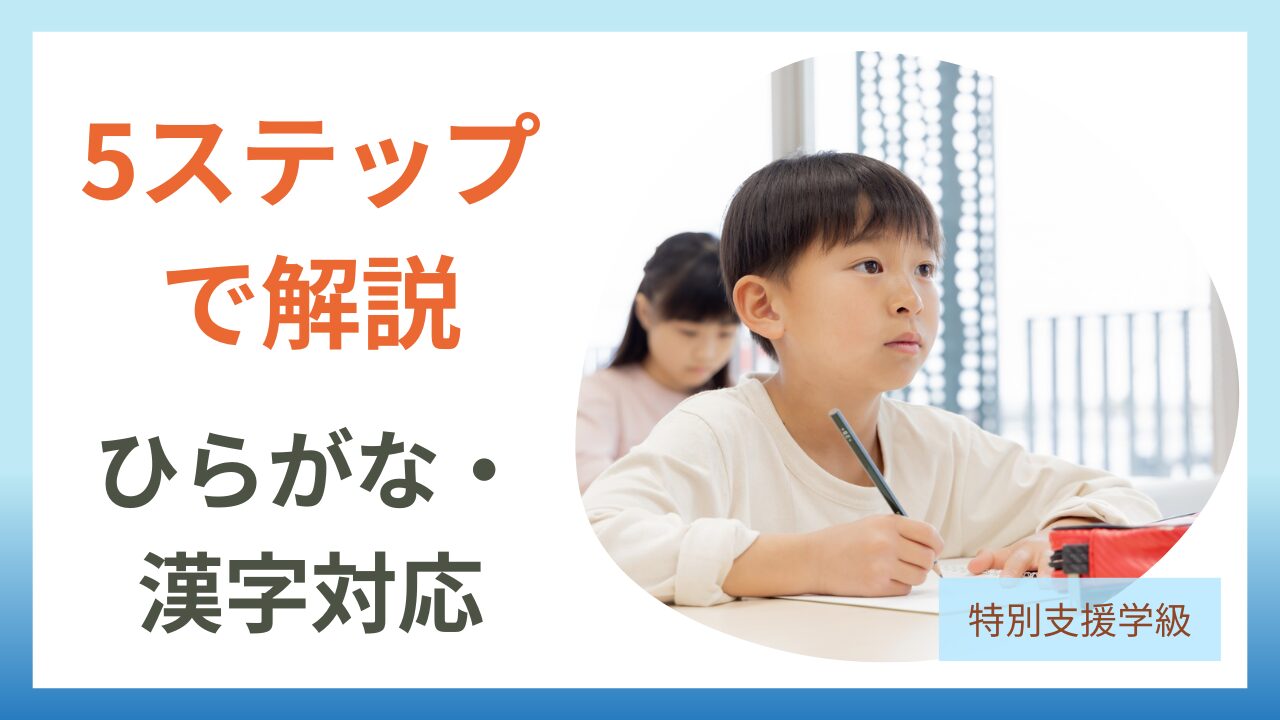




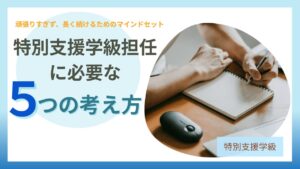
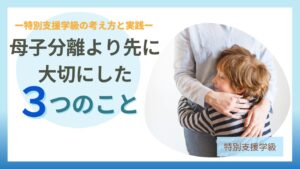

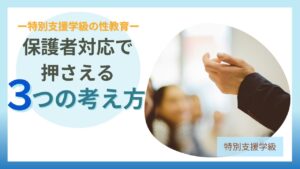
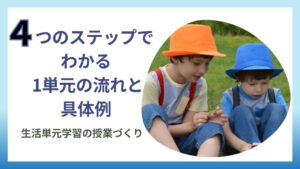

コメント