本格的な読みの力を育てる5ステップガイド
特別支援学級でも「検定本の教科書」を使用している自治体もあり、
国語の授業もいよいよ「本格的に読む」力が求められる学級も。
去年までは、絵本や読みやすい一般図書が中心だったのに…。
急にハードルが上がったようで、戸惑っている先生も多いのではないでしょうか。
今日は、そんな先生のために、
「登場人物の気持ちを込めて読む」 ことをゴールにした授業づくりを、
5つのステップでご紹介します😊
5段階ステップで進める「読みの授業」

①【安心して読む】音読に慣れる
まずは、文章に親しみ、「読むのがこわくない」と思えることが大切です。
- 教員の読み聞かせや、読み上げソフトを活用
- リズム読み、言葉あそびなど楽しいアプローチも◎
ポイント
最初は「読む楽しさ」を感じてもらうことを優先しましょう。
②【内容をつかむ】話の全体像を理解する
物語の場面や流れをざっくり把握します。
- 挿絵や絵カード、紙芝居、動画などを使ってイメージをふくらませる
- 「この場面はどんな感じかな?」と対話をしながら確認
ポイント
一気に読み進めず、場面ごとに立ち止まると理解が深まります。
③【人物に注目する】行動から考える
登場人物の「行動」を整理することで、
自然と気持ちの理解につながっていきます。
- 行動カードを作る
- フローチャートを使って流れを見える化
ポイント
「何をしたか」をシンプルに捉えるところからスタートしましょう。
④【気持ちを想像する】表現をふくらませる
行動をもとに、人物の「気持ち」を想像していきます。
- 気持ちカード、表情イラストを使う
- 「自分だったらどう思う?」と問いかける
ポイント
正解を求めず、いろんな感情を認め合う空気を大切に。
⑤【気持ちを込めて読む】声に感情をのせる
最後はいよいよ、感情を込めた音読にチャレンジ!
- 怒った声・悲しそうな声など表現あそびを取り入れる
- 録音して、自分の音読を振り返るのもおすすめ
ポイント
遊び感覚で声に出して、自然と表現力を育てていきましょう。
小学校特別支援学級向け|検定教科書で「読む力」を育てる5つのステップのQ &A

Q1.支援学級の子に検定教科書は難しすぎませんか?
A1.
はい、最初は難しく感じるかもしれません。
ですが、「読むことに慣れる」「全体をつかむ」など小さなステップに分ければ大丈夫です。
1単元で1つの感情がわかったら合格!くらいのペースで、安心して進めましょう。
Q2.一斉授業が難しい場合、どうしたらいいですか?
A2.
子どもたちに役割分担をするとスムーズです。
たとえば「Aさんは音読担当」「Bさんは気持ちを想像する担当」など。
それぞれが自分の力を発揮できる形を考えるのがポイントです。
Q3.どのくらいのペースで進めたらいいですか?
A3.
支援学級では、「1つの単元をじっくり取り組む」イメージが基本です。
早く進めることよりも、「この場面、どんな気持ちかな?」を丁寧に味わうことを大切にしましょう。
Q4.読むこと自体を嫌がる子にはどう対応したら?
A4.
まずは「聞く」「遊びながら読む」からスタートしてOKです。
リズム読み、言葉あそび、絵本の読み聞かせなど、音やリズムを楽しむところから始めると、抵抗感がやわらぎます。
Q5.成果はどう評価したらいいですか?
A5.
「できた/できなかった」で評価しなくて大丈夫です。
子どもが「こんな気持ちかも!」と少しでも想像できたら、大きな成長。
録音して自分の音読を聞くなど、小さな変化を一緒に喜び合う姿勢が、次へのやる気につながります。
小学校特別支援学級向け|検定教科書で「読む力」を育てる5つのステップのまとめ

「想像できたこと」「感じたこと」には、
正解も不正解もありません。
支援学級では、
「1単元で1つの感情がわかったら大成功!」くらいの
ゆったりしたペースで大丈夫です😊
もし一斉指導が難しい場合は、
- 「Aさんは音読だけ」
- 「Bさんは気持ちカード担当」
など、役割を分ける方法も効果的ですよ。
気持ちを込めて読むって、
実はとてもクリエイティブで、楽しい活動です。
焦らず、
子どもたちと一緒に「読むよろこび」を味わっていきましょう🍀

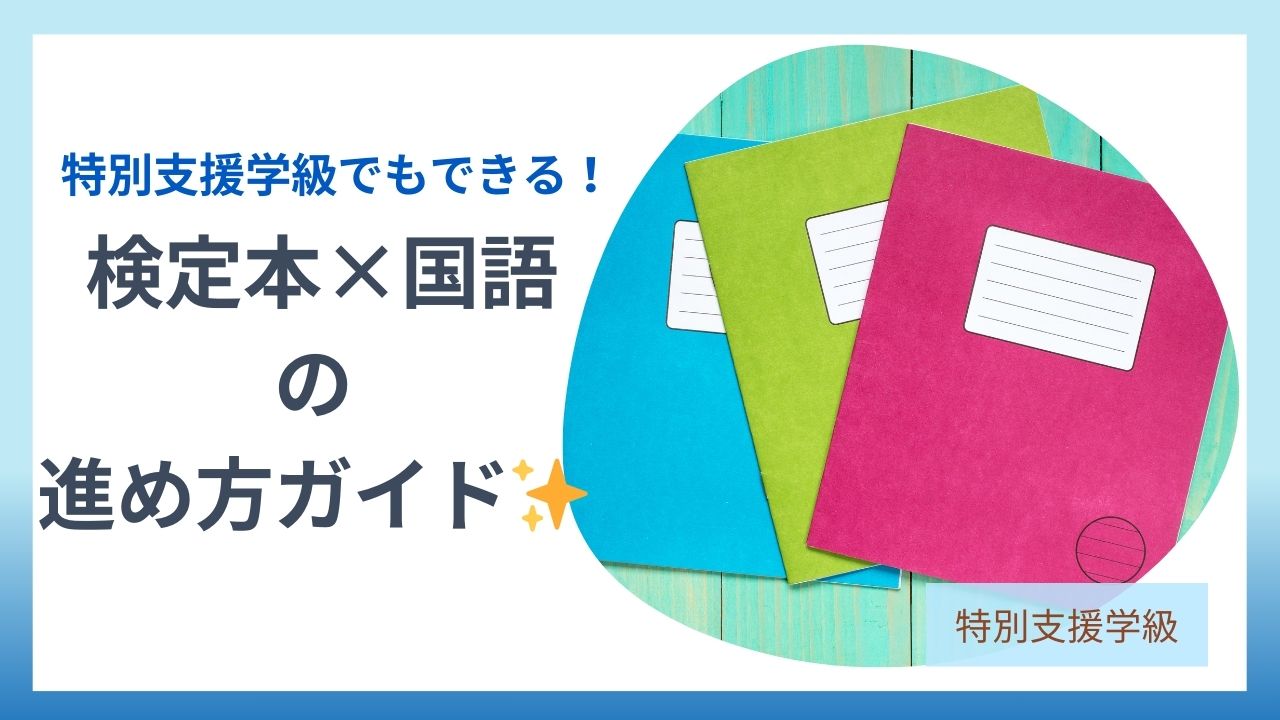




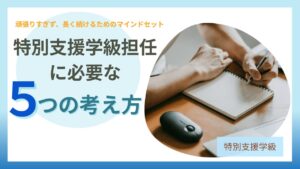
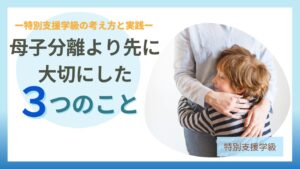

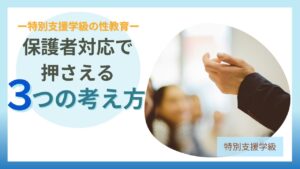
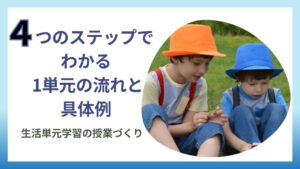

コメント