情緒の課題がある子どもへの指導に苦戦し、「文字を正しく書いてほしいだけなのに激しく反発される…」と悩む先生は少なくありません。
この記事では、交流級で見せる意欲的な一面を引き出しつつ、特別支援学級での「言うことを聞かない」といった行動にも寄り添いながら、適切に声をかけるポイントをご紹介します。
学期末の保護者面談を前に、信頼関係を崩さずに「一緒に支える仲間」として保護者に伝える具体的なフレーズも解説。子どもの未来につながる支援のヒントをぜひお役立てください。
1.現状の整理:子どもの“二面性”に込められた思い
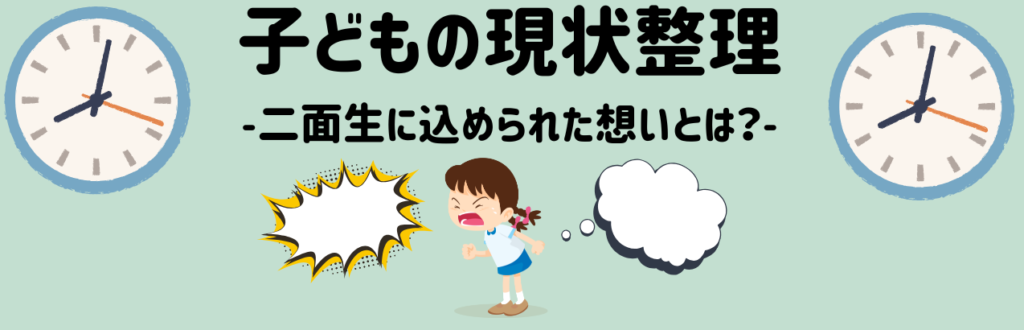
- 交流級で見せる前向きな姿
- 手を挙げて積極的に参加
- 答えを出すときの笑顔や達成感
- 特別支援学級での反発的態度
- お手本通りに書かない
- 注意すると「自分の精一杯」を主張
- 「字が下手って言うの?」と感情的になる
この二面性は、場面によって「見られたい自分」と「守りたい自分」が交錯している表れです。
2.なぜ反発するのか?子どもの気持ちを想像する
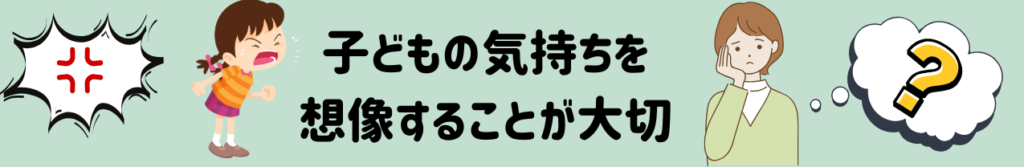
- 「失敗を認めたくない」気持ち
- 自分の不得意を大人に知られることへの恐れ
- 「コントロールしたい」欲求
- 自分のペースで進めたい自己主張
- 相手への期待値ギャップ
- 「先生には認めてほしいけど、直されると否定されたと感じる」
――大人が意図する「良くなってほしい」の裏で、子どもは「自分の存在を守りたい」と感じています。
3.声かけのポイント:否定せず、導く3ステップ
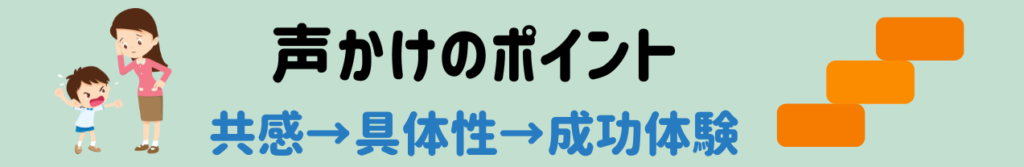
ステップ① まずは共感を示す
「交流級ではこんなに意欲的に取り組んでいるね。私もその姿、大好きだよ」
→ 安心感を与え、「認めてもらえた」という土台を築きます。
ステップ② 「できたところ」を具体的に伝える
「ここまで形を真似て書けているのはすごいよ。次はこの部分だけ一緒に練習しようか」
→ 全否定ではなく、一部改善へとつなげる意識付け。
ステップ③ 小さな成功体験を重ねる
「今日はこの1文字だけチャレンジしてみよう。できたらシールを貼ろうか」
→ 達成感が次の意欲を生みます。
4.保護者面談での伝え方:信頼を崩さない4つのポイント
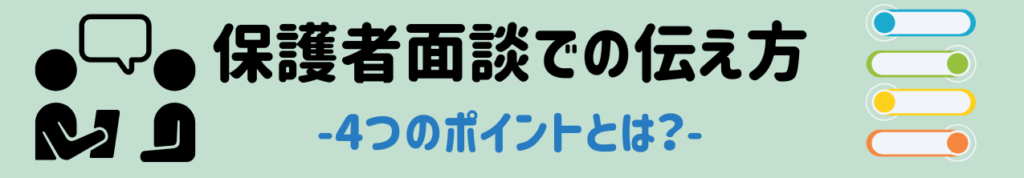
- ポジティブな観察から始める 例)「交流級ではこんなに前向きなんです」
—「先生はわが子の良い面も見てくれている」と安心感を生む。 - 行動の背景を「現象」として共有 例)「少人数になると拒否的になる場面が増えます」
—「先生の叱責」ではなく「子どもの状態」として伝える。 - 目的を「未来の自立」に置く 例)「正しく書く練習は、将来困らないためのステップです」
—今だけの指導ではなく「長い視点」を示す。 - 家庭との協力をお願いする 例)「お家でも『先生と一緒にがんばってみよう』と声をかけていただけると助かります」
—「依頼」の姿勢で、共同支援のパートナーとして迎える。
5.子どもとの関わりケース別フレーズ集
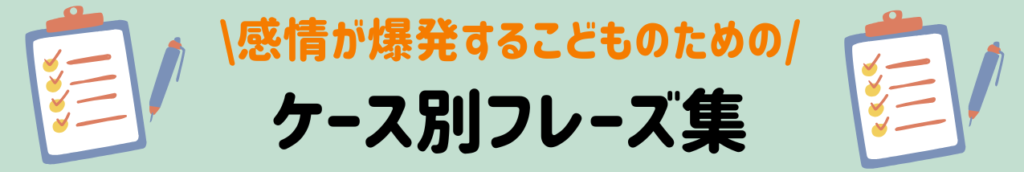
今回のケース
| シーン | 例 |
|---|---|
| 漢字のはね・はらいを直したいとき | 「ここのはね、こうするともっとすっきり見えるよ。やってみようか?」 |
| 拒否されたときのフォロー | 「無理しなくていいよ。このくらいで十分上手だよ」「何が苦手だった?」「何か困ってるのかな?」 |
| 保護者に協力をお願いしたいとき | 「私だけでは難しいので、ご家庭でも同じ声かけをお願いしてもいいですか?」「一緒により良い方向に、お子さんを伸ばしていきましょう」 |
その他想定されるケース
| シーン | 例 |
|---|---|
| 1. 書き始めに腰が重いとき | 「まずは一画(線)だけでいいから、鉛筆を持ってみようか。一緒に始めてみよう!」 |
| 2. 書いた字を見せるのをためらうとき | 「〇〇君の書いた字、ちょっと見せてくれる?そのままでも素敵だから安心してね」 |
| 3. 気持ちが落ち着かず集中できないとき | 「深呼吸してから、もう一度ゆっくりやってみよう。焦らなくて大丈夫だよ」 |
| 4. 他の子と比べて落ち込んでいるとき | 「〇〇くんは〇〇くんだからこそ、◇◇が得意だよね。他と比べなくていいんだよ」 |
| 5. 完璧を求めすぎて動けないとき | 「完璧じゃなくてもいいよ。少しずつやっていこう。一歩ずつで十分だからね」 |
| 6. 直しを提案したら傷ついたような反応をしたとき | 「ごめんね、傷つけるつもりじゃなかったよ。〇〇君の気持ち、大事にしたいんだ」 |
| 7. 「先生、ムリです」とすぐ諦めそうなとき | 「今日は1こだけでOK。それでできたら次の章に進もう。小さなゴールで大丈夫!」 |
| 8. 手を挙げて質問してくれたとき | 「いい質問だね!その気づきがあるから成長できるんだよ。一緒に考えよう」 |
| 9. 自慢気に見せてきたとき | 「見せてくれてありがとう!ここがすごくきれいだよ。次はここを一緒にチャレンジ」 |
| 10. 保護者に「言いすぎでは?」と言われたとき | 「私もそう思いました。〇〇君のために少しずつ慣れてほしくて…」「できたらこれから先の〇〇君のためにも、同じような声かけをお願いできますか?」 |
漢字の宿題で逆ギレ!?感情が爆発する子への関わり方と保護者面談の伝え方のQ &A
- 特別支援学級ではまったく話を聞かない子に、どう声をかければいいですか?
-
まずは共感から入るのがおすすめです。
「○○くん、今日はよくがんばってるね!」と、努力や意欲を認めてから具体的な改善点に移ると、子どもの心の扉が開きやすくなります。焦らないでじっくり関わっていきましょう! - 注意すると「自分はこれが精一杯」と言ってしまうのですが?
-
「できない」のではなく「まだ練習が必要」というスタンスで伝えましょう。
たとえば「今日はここだけチャレンジしよう」「一緒に練習したらもっと上手になるよ」と、「共に取り組む」姿勢を見せると安心感が生まれます。 - 交流級でがんばっているのに、なぜ特別支援学級では態度が違うのでしょうか?
-
環境や周囲の顔ぶれが変わると、緊張や不安が高まりやすくなります。
「見られたい自分」と「守りたい自分」のせめぎ合いが起きているので、少人数の場でも安心して自己表現できるよう、声かけや環境調整でサポートしましょう。 - 保護者面談で“反発する態度”をどう伝えれば角が立ちませんか?
-
行動を「現象」として客観的に伝え、先生と保護者が同じ目標(子どもの成長)を共有することが大切です。
「少人数の場面で拒否的になる場面があります。将来困らないために練習を重ねたいので、ご家庭でもご協力をいただけると助かります」と伝えると、協力的な雰囲気が作れます。 - 小さな成功体験を積ませる具体的な方法は?
-
シールやスタンプなどの「見えるごほうび」を取り入れてみましょう。
たとえば「今日はこの文字が合格だったらシールを貼ろう」と目標を小さく設定すると、子どもは達成感を感じやすく、次への意欲が湧きます。
漢字の宿題で逆ギレ!?感情が爆発する子への関わり方と保護者面談の伝え方のまとめ
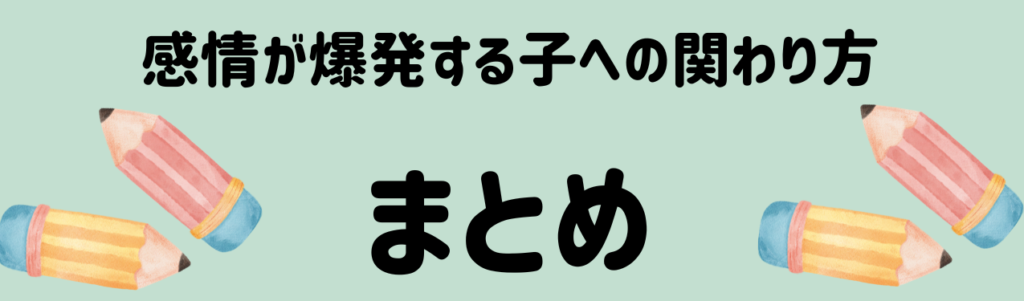
子どもの指導に「これが正解」というものはありません。大切なのは、毎回の関わりで「信頼」と「小さな成長」を積み重ねることです。今日の言葉かけが、明日の自信につながる――その思いを胸に、ぜひ面談と日々の支援に役立ててください。

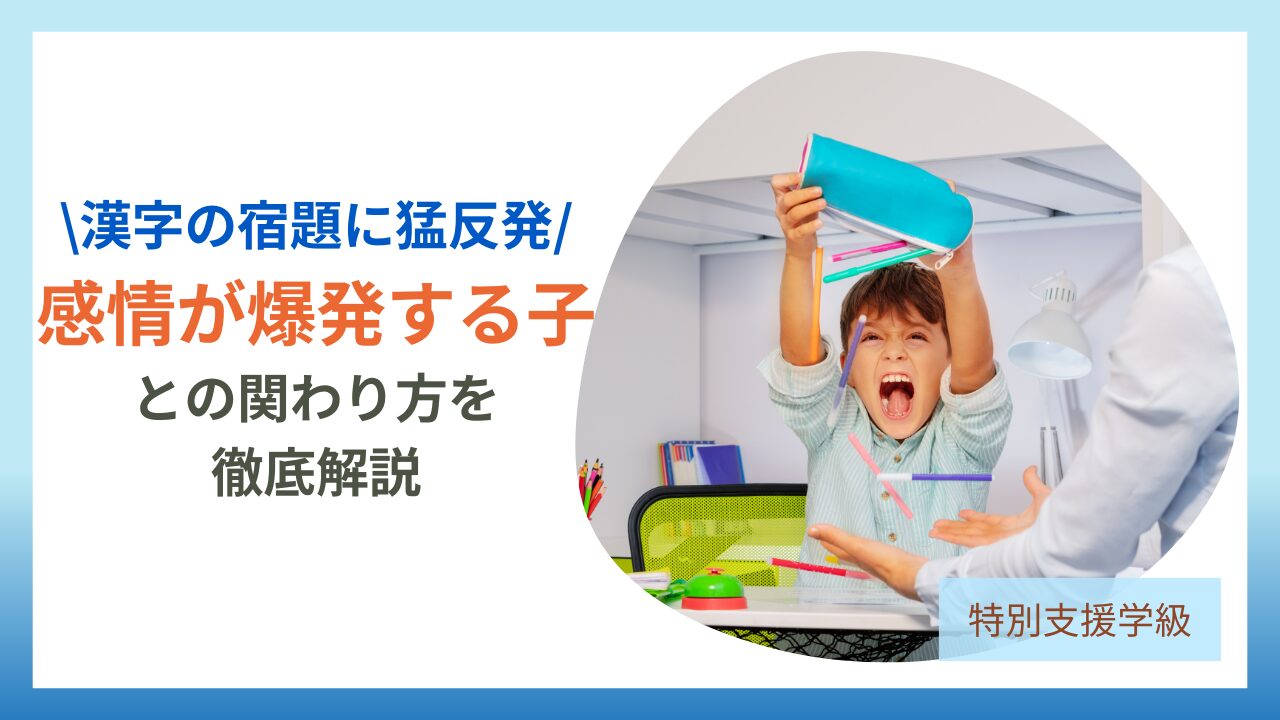




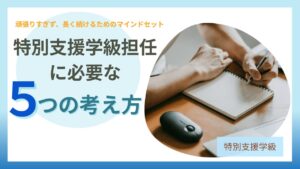
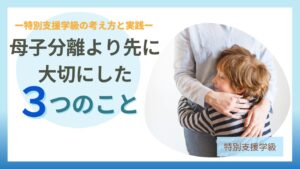

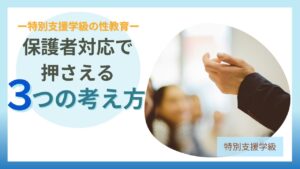
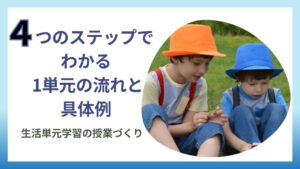

コメント