こんにちは、特別支援教育の現場で「弱視」支援に携わっている先生からご質問いただきました。
今日は、多くの方が悩むテーマ──「弱視の自立活動の年間指導計画」について、ポイントと具体例をご紹介します。
※ 本記事は、著者自身が弱視学級の担任経験はありませんが、
文部科学省のガイドライン、実践事例、全国の教育委員会の公開資料、そして視覚障害教育に関する専門論文をもとに構成しています。
もし、現場での実践例や工夫があれば、ぜひコメントやメッセージで教えていただけると嬉しいです!
まず、「自立活動」とは?
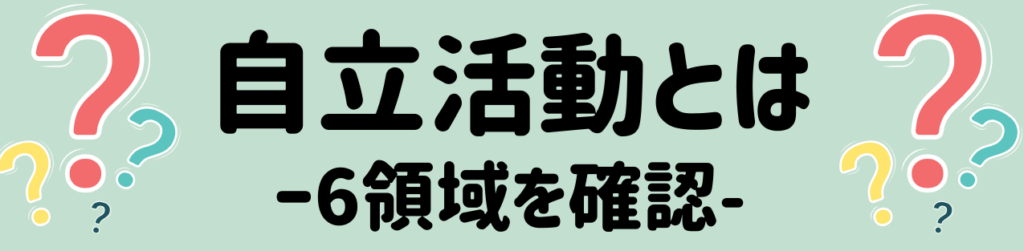

文部科学省が示す通り、自立活動は6つの領域に分かれています。
- 健康の保持
- 心理的な安定
- 人間関係の形成
- 環境の把握
- 身体の動き
- コミュニケーション
弱視の子どもたちは、視覚以外の感覚を駆使しながら生活する必要があります。自立活動では、「見えにくさを補い、自分らしく生活する力」を育むことが目標です。
年間指導計画の立て方とポイント
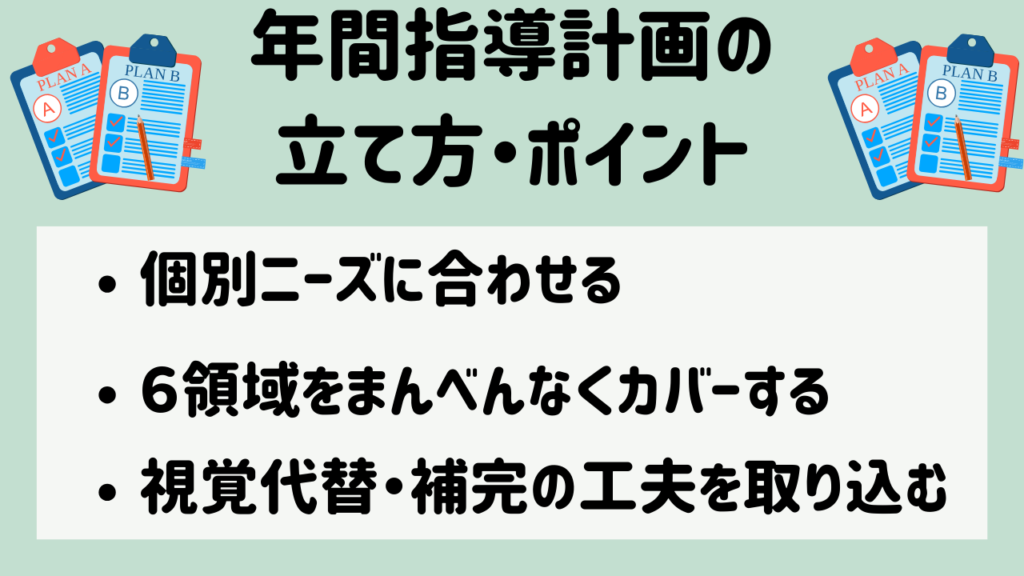
✅ ① 個別ニーズに合わせる
視力や視野、疾患の特性は子どもによって異なります。まずは**個別の教育支援計画(IEP)**に基づいて、本人の実態をしっかり把握しましょう。
✅ ② 6領域をまんべんなくカバー
どの月に、どの領域に取り組むかをバランスよく配置するのがポイントです。
✅ ③ 視覚代替・補完の工夫を組み込む
点字・拡大文字・触覚教材・音声提示など、**“視覚以外で情報を得る方法”**を少しずつ教えていきます。
📝【年間指導計画の例】(小学校低学年・弱視)
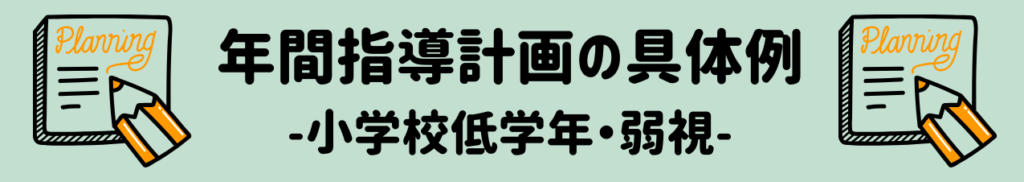
| 月 | 主な領域 | 内容の例 |
|---|---|---|
| 4月 | 環境理解・心理的安定 | 教室内の構造を触って確認/教室ルールを学ぶ |
| 5月 | 身体運動 | 白杖の基本操作と室内歩行 |
| 6月 | コミュニケーション | 拡大教科書の使い方/図の読み方練習 |
| 7月 | 健康保持 | 視覚疲労とセルフケア/適切な照明環境づくり |
| 9月 | 人間関係形成 | 声や音で相手を認識する遊び・活動 |
| 10月 | 身体運動 | 校内移動のルート練習(白杖あり) |
| 11月 | コミュニケーション | 点字カード作成体験/音声メモの利用練習 |
| 12月 | 健康・環境 | 季節による見え方の変化と対処法 |
| 1月 | 心理的安定 | 自分の「見え方」を言葉で説明してみる |
| 2月 | 人間関係 | グループ活動で「伝える・受け取る」練習 |
| 3月 | 総合 | 一年のふり返りと成果発表・自立スキル確認 |
弱視の特別支援学級での「自立活動」──年間指導計画はどう作る?のQ &A

弱視の特別支援学級における「自立活動」に関するよくある質問と、専門的な視点からの回答を紹介します。
- 視覚に頼らない活動が中心になるのですか?
-
はい。弱視の子どもは視力に負担がかかると疲れやすくなります。そのため、触覚・聴覚・身体感覚など“他の感覚”を活用した活動が中心になります。ただし、本人の残存視力を活かすことも大切なので、拡大文字や照明調整などの視覚補助も並行して活用します。
- 「白杖」の練習は自立活動で扱っていいの?
-
扱ってOKです。むしろ、自立活動は白杖のような**生活スキル(オリエンテーション&モビリティ)**を教える絶好の時間です。白杖歩行やランドマーク確認、校内移動訓練などを段階的に導入しましょう。
- 他の教科と重なる内容が多いのですが、どう区別しますか?
-
「自立活動」は“その子の生活全体を支えるための力”を育てる時間なので、教科の補完ではなく「生活力の獲得」を目的に位置づけます。たとえば「図の読み方」を扱う場合でも、情報の受け取り方の工夫を本人が主体的に学ぶことを強調しましょう。
- 年度を通して同じ活動を繰り返しても良い?
-
大丈夫です。むしろ、反復と定着が自立活動の基本です。ただし、全く同じやり方ではなく、徐々に難易度や範囲を広げるような“スモールステップ”で設計すると、達成感と自己効力感が高まります。
- 点字や拡大教材は自立活動で指導すべき?
-
はい。点字や拡大教科書、大活字教材の使用は視覚代替・補完手段の獲得という意味で非常に重要です。導入の際は、単に「読む練習」だけでなく、「それがあることでどれだけ生活が楽になるか」を実感させる工夫がカギです。
弱視の特別支援学級での「自立活動」──年間指導計画はどう作る?のまとめ
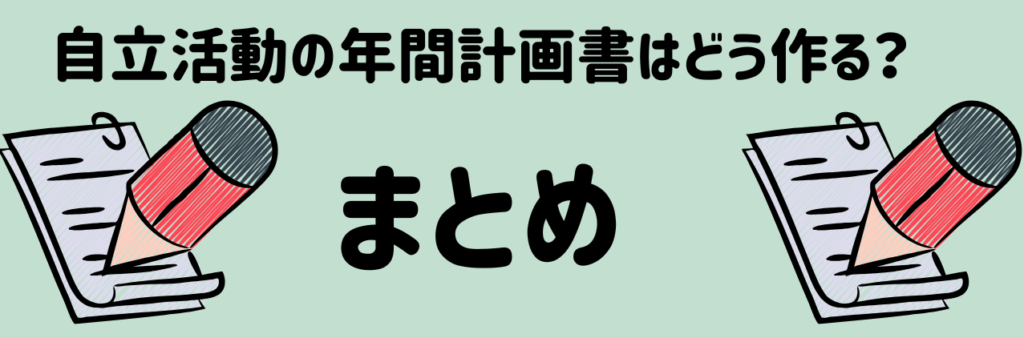
弱視児童の自立活動では、「見えないからできない」ではなく、「どうすればできるか」を一緒に考える姿勢が大切です。
- 白杖を持つこと
- 点字に触れること
- 拡大読書器を使うこと
これらは、本人にとっての「できる力」を広げる第一歩です。
「自立活動」は教科学習とは異なり、
です。
教師自身も楽しみながら、子どもと一緒に「生活をデザインする感覚」で取り組めると素敵ですね。
現場経験者の声や実際の事例も、今後さらに収集・反映していく予定です。
もし、現場での実践例や工夫があれば、ぜひコメントやメッセージで教えていただけると嬉しいです!

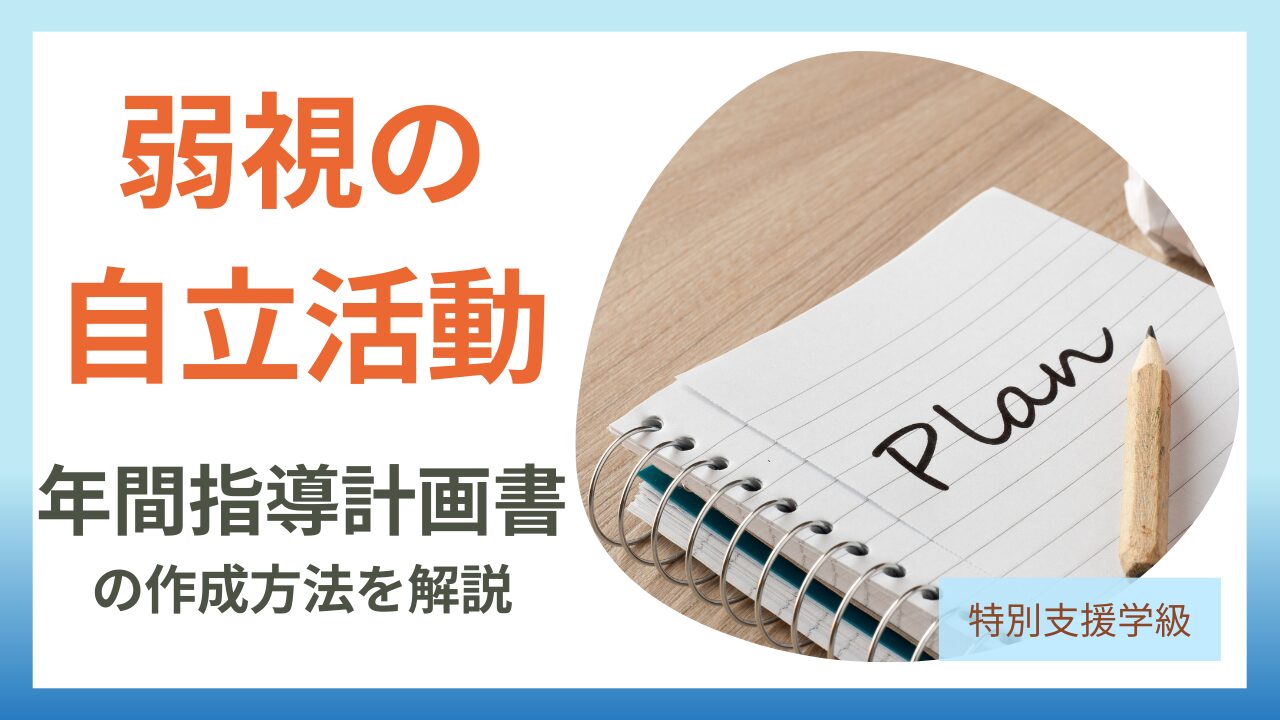




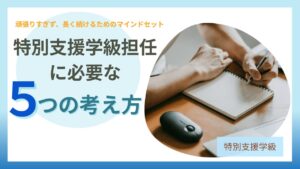
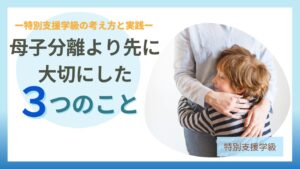

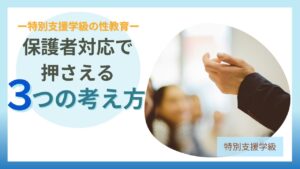
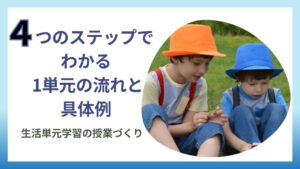

コメント