「なんであの子だけ特別扱いなの?」
―― 教室でこんなつぶやきを聞いたことはありませんか?
特別支援の現場では、子どもたちが“違い”に気づいた瞬間に、 思わず「ずるい」と感じることがあります。 けれど、その言葉の奥には「自分も認めてほしい」「がんばりを見てほしい」という気持ちが隠れています。 今回は、そんな場面から見えてきた「公平と平等」のお話。 先生の言葉が、子どもの心に届く瞬間を一緒にたどってみましょう。
実際にあった場面のこと
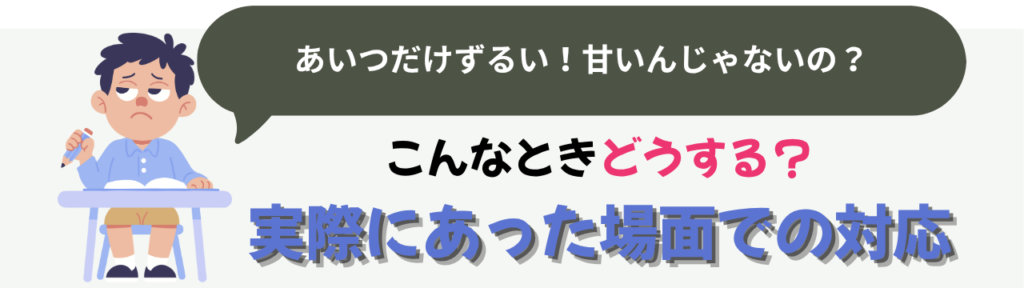
受講生からの相談です。
昨日の3校時、5年生の算数の時間。6年生のAさんが「理科は難しいから今日は行けない」と言って、特別支援の教室へ来ました。理科は内容が難しく、本人にとって負担の大きい時間。先生は理科の先生に許可を取り、3校時だけ別学習をすることにしました。
それを見た5年生のBくんが、少し不満そうに言いました。
「Aだけずるい。先生、甘いんじゃないですか。だったら僕も体育苦手だから、こっちにいてもいい?」
先生:「Bくんの気持ち分かるよ。でもね、みんな得意なこと・苦手なことは違うよね。
それぞれに合ったがんばり方があるんだよ。」
公平と平等はちがう
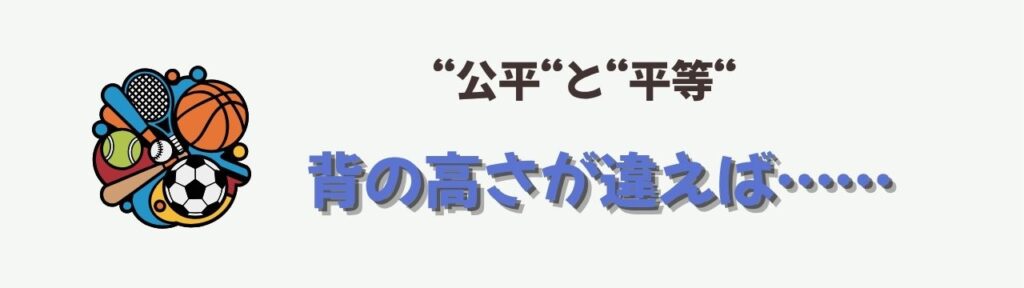
Bくんのように「同じでなければ不公平」と感じるのは自然です。でも、本当に大切なのは「みんなが同じことをすること」ではなく、「一人ひとりが力を発揮できること」。
- 平等:みんなに同じもの・同じ条件を配ること。
- 公平:一人ひとりの違いに合わせて、必要な支援を変えること。
例え話:
全員がボールの試合を見るために台に乗るとき、背の高さが違えば台の高さも変わるよね。全員が見えるようにすることが“公平”。
🎯 子どもへの伝え方のコツ
- まず感情を受け止める:「そう思うよね」「がんばってるの知ってるよ」。
- 例え話で置き換える:台・メガネ・補助輪など日常の具体例で。
- 短いクールダウン:落ち着いた後に説明すると納得が進む。
🧩 日常づくりの工夫
- 掲示:「みんなちがっていい」「がんばり方はいろいろ」を常設。
- 朝の会トーク:最近の“がんばり方”を共有する時間。
- 見取りの言語化:「〜に取り組めていたね」と具体的に伝える。
授業で使えるおすすめ教材
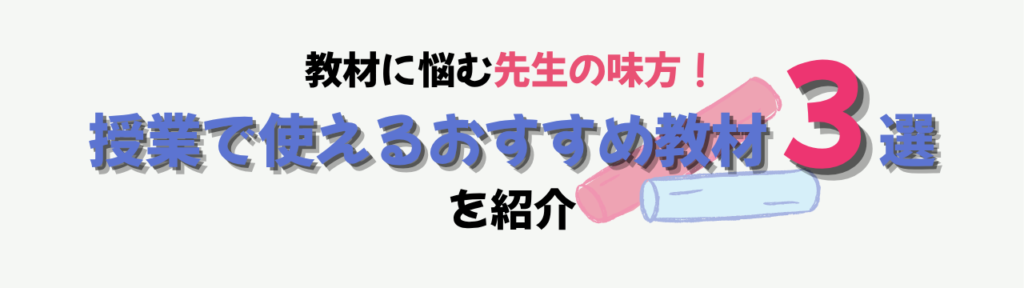
① NHK for School「ココロ部!みんなの自由な公園」
自由・ルール・公平をテーマに、子ども自身が考える構成。今回のような「ずるい」感情の背景を話し合う導入に最適です。
👉 NHK for School 公式サイト
② UNICEF「子どもの権利教育ツールボックス」
「支援を受けること=恥ずかしいことではない」という視点で学べる教材。違いを認め合う活動が豊富です。
👉 先生のためのツールボックス
③ 各自治体の人権・道徳教育資料
「公正さ」「個性を認め合う」視点が整理されており、授業のまとめや教師のふりかえりに便利です。各都道府県の教育委員会サイトで公開されています。
授業での工夫ポイント(チェックリスト)
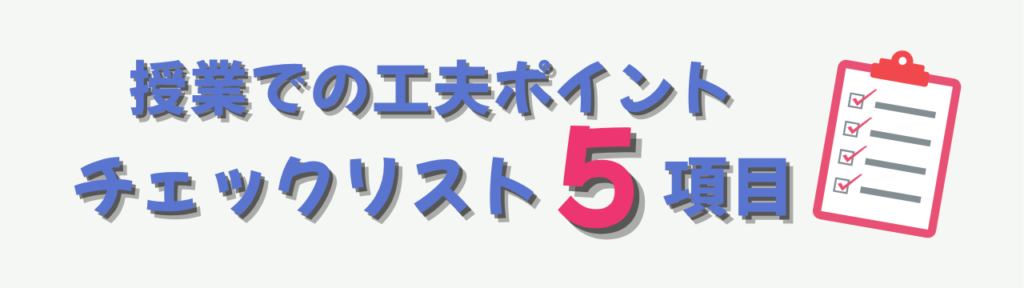
- 感情の受け止め:まずは「そう思うよね」で共感。
- 例え話の活用:台・メガネ・補助輪など、日常にあるもの。
- 対話の設計:個人→ペア→全体で“納得”を育てる。
- 見取りの言語化:「〜に取り組めたね」と具体的に称賛。
- 日常の土台づくり:掲示と朝の会で「違っていい」を繰り返す。
この5項目は「公平・平等の指導を日常でどう実践するか」を支える核になる部分です。
以下では、それぞれを現場でそのまま使える実践解説します。
① 感情の受け止め:「そう思うよね」で共感
「ずるい」「なんであの子だけ」という言葉の裏には、
「自分も見てほしい」「がんばりを認めてほしい」という思いがあります。
ここで教師がすぐに説明をしてしまうと、
子どもの気持ちは“否定された”と感じてしまうこともあります。
まずは、感情の存在をそのまま受け止めることが大切です。
例として
「そう思うよね。Aくんもがんばってるもんね。」
「そう感じたんだね。気持ちを教えてくれてありがとう。」
この一言で、子どもは「先生は自分の気持ちを理解してくれた」と安心します。
そのあとに説明を加えることで、心が開かれた状態で納得できる流れが作れます。
② 例え話の活用:台・メガネ・補助輪など、日常にあるもの
抽象的な「公平」や「支援の違い」を、
子どもが自分の経験に置き換えられるように伝えるのがコツです。
たとえば——
- 台(ジャンプ台・踏み台)
→ 背の高さが違えば、見える高さも違う。だから台の高さを変えるのは“ずるい”ではなく“工夫”。 - メガネ
→ 目が悪い人がメガネをかけるのは特別扱いではなく、自分に合った助け方。 - 補助輪付きの自転車
→ 最初は補助輪が必要でも、練習すれば外せる。支援は“助走のための道具”。
こうした日常のものを使うと、支援=不公平ではないという考えが自然に伝わります。
子どもたち自身から「じゃあ、Aくんにとってのメガネみたいなものだね!」という言葉が出てくることもあります。
③ 対話の設計:個人→ペア→全体で“納得”を育てる
「公平と平等」のようなテーマは、
先生の説明だけでは子どもが“自分ごと”として理解しにくいもの。
一人で考える → ペアで話す → 全体で共有するという流れを意識しましょう。
構成例
- 個人ワーク:「ずるいと思ったこと、ある?」をふりかえる。
- ペア対話:「どうしてそう思った?」「相手はどう感じてるかな?」を話し合う。
- 全体共有:「みんなが安心できるって、どういうことだろう?」を考える。
この流れは「話す・聞く・考える」力を育てながら、
それぞれの立場の違いを理解する実践にもなります。
④ 見取りの言語化:「〜に取り組めたね」と具体的に称賛
「頑張ったね」だけでは、子どもは何を評価されたのか分かりにくいものです。
行動のプロセスを具体的に言葉にすることで、自己肯定感を育てます。
例として
- 「“どうしてそう思うのか”を言葉にできたね。」
- 「さっきは“そう思う”って正直に言えたね。」
- 「Aさんのがんばりをちゃんと見ようとしたね。」
こうした小さな声かけが積み重なると、
「自分も見てもらえている」という実感につながり、他者の違いにも寛容になっていきます。
⑤ 日常の土台づくり:掲示と朝の会で「違っていい」を繰り返す
授業1回で「公平」は身につきません。
日常の空気として“違っていい”が感じられる環境づくりが大切です。
実践例
- 教室掲示に「みんなちがっていい」「がんばり方はいろいろ」を常設。
- 朝の会や帰りの会で「今日のがんばり発見」を1人ずつ共有。
- 学級目標の中に「ちがいをみとめる」を入れる。
- “がんばりノート”や“できたシール”など、個人のペースを可視化する仕組みを取り入れる。
こうした日常の積み重ねが、
トラブルのときに「先生の言葉を信じてみよう」と思える土台になります。
「公平・平等の指導を日常でどう実践するか」のまとめ
「公平」とは、“みんなが自分らしく力を発揮できるように支えること”。
それを伝えるには、瞬間的な対応よりも、日々の言葉かけ・場づくり・見取りの積み重ねが鍵です。
先生が子どもの心を受け止め、寄り添う姿こそ、
子どもにとっての“いちばんの教材”になります🌿
特別支援学級で子どもが「ずるい」と言うときの対応法|公平と平等を教える授業アイデアのQ&A
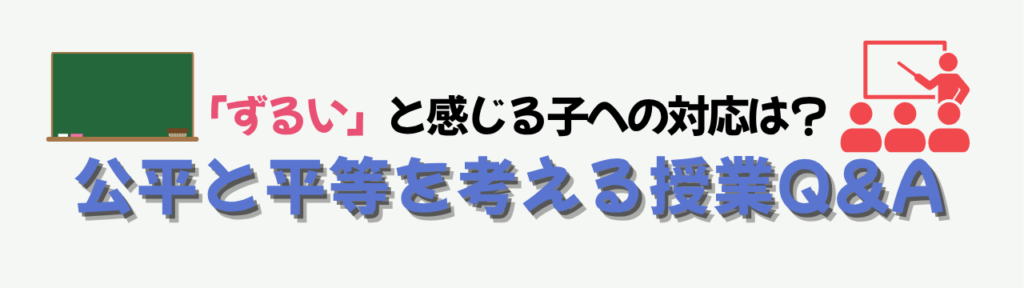
「子どもが『ずるい』と言ったとき、どう返したらいいの?」
「公平と平等の違いを、子どもにどう伝えればいいんだろう…」
そんな疑問を持つ先生はとても多いです。
特別支援の現場では、日々の小さな場面が子どもたちの「納得」や「信頼」につながります。
この記事では、先生方からよく寄せられる質問をもとに、実際の対応や伝え方のコツをQ&A形式でまとめました。
読み終わるころには、「次にあの場面が来ても大丈夫」と思えるヒントがきっと見つかります🌿
- 「ずるい」と言われたとき、どう返すのが正解ですか?
-
まずは否定せずに受け止めることが大切です。
「そう思うよね」「Aくんもがんばってるもんね」と、気持ちを認める言葉を返しましょう。
そのうえで、少し時間をおいてから「みんなが力を出せるように支援しているんだよ」と説明すると、子どもが納得しやすくなります。 - 「公平」と「平等」の違いをどう伝えればいいですか?
-
「背の高さが違うから、台の高さも違う」「目が悪い人はメガネをかける」といった、日常にある具体例を使うと伝わりやすいです。
“同じにすること”よりも、“みんなが見えるようにすること”が公平だと伝えてみてください。 - 他の子が『自分も特別扱いしてほしい』と言い出したら?
-
「先生は、みんなが力を出せるように手伝い方を変えているよ」と伝えるのがおすすめです。
“特別扱い”ではなく、“それぞれの助け方”という考え方を繰り返し伝えることで、理解が深まります。 - 授業でこのテーマを扱うとき、何年生に向いていますか?
-
5〜6年生に最も向いていますが、低学年でもイラストや映像教材を使えば十分に扱えます。
NHK for School「ココロ部!」などの映像を活用すると、発達段階に合った話し合いがしやすくなります。 - 普段の学校生活の中で“公平”を伝える工夫はありますか?
-
朝の会や帰りの会で「今日がんばっていたこと」を一言伝える、掲示物で「ちがっていい」を見える化するなど、日常に散りばめていくのが効果的です。
“公平”は一度の授業で伝えるものではなく、毎日の積み重ねで育つテーマです。
特別支援学級で子どもが「ずるい」と言うときの対応法|公平と平等を教える授業アイデアのまとめ
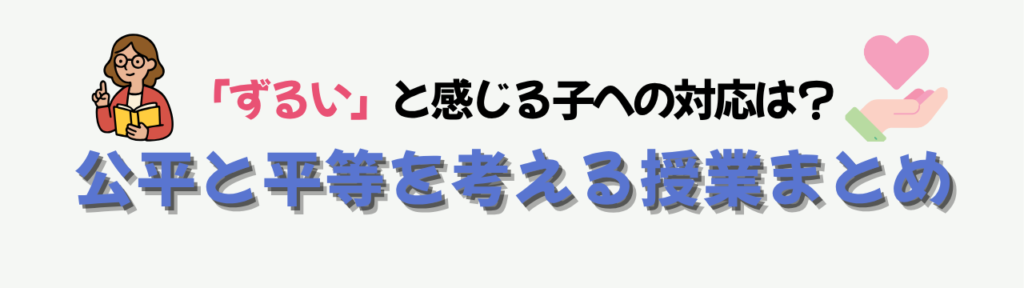
子どもが「ずるい」と感じたとき、それは“違い”に気づいた瞬間です。
その感情を否定するのではなく、まず受け止め、
「みんなが力を出せるように支援を変えているんだよ」と伝えることで、
本当の“公平”を理解するきっかけになります。
💡 授業づくりのポイント
- 平等=同じにすること
- 公平=それぞれに合った支援をすること
NHK for School「ココロ部!」などの教材を活用しながら、
たとえ話やワークを通して、子どもたち自身が“納得”できる形で学びを深めましょう。
「ずるい」という言葉の裏には、
「自分も見てほしい」「認めてほしい」という想いがあります。
その心に寄り添いながら、“違っていい”を教室のあたりまえにしていくこと――
それが特別支援学級の担任にしかできない大切な支援です。

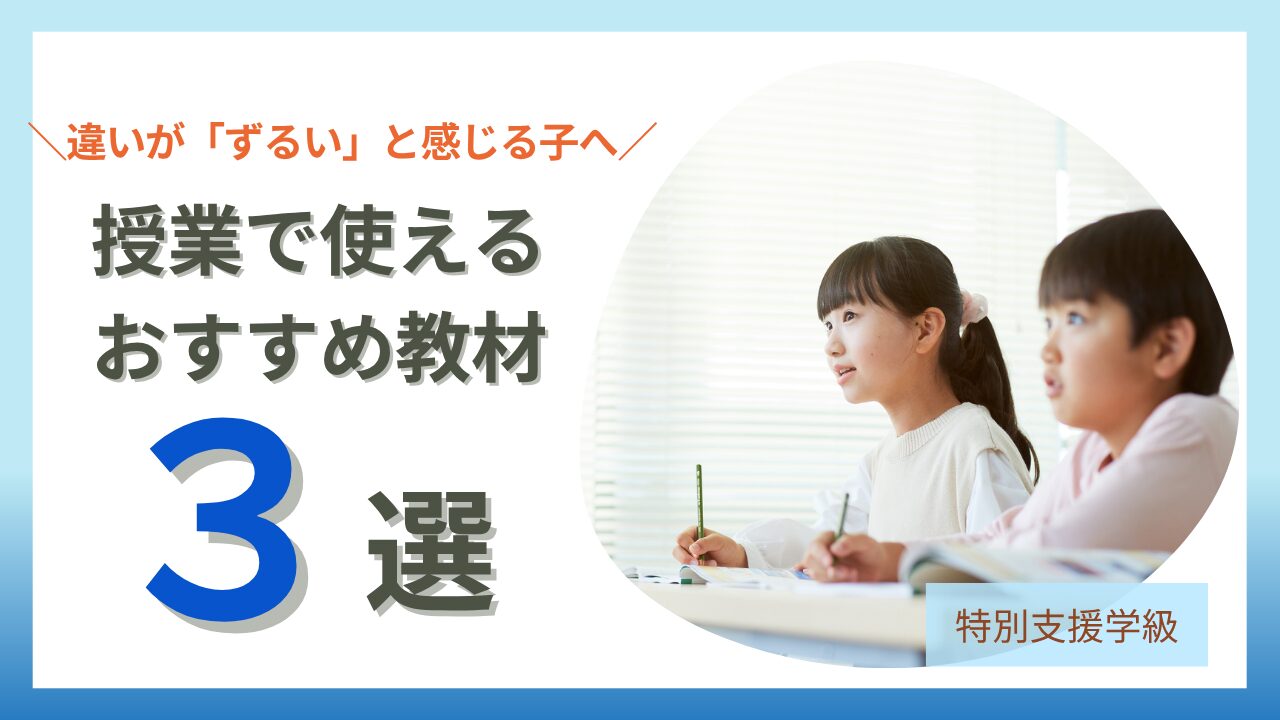


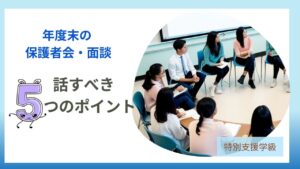
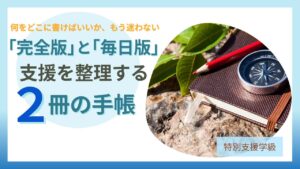
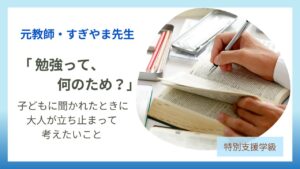

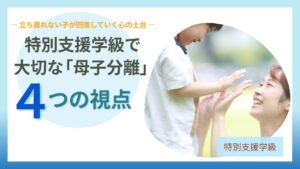


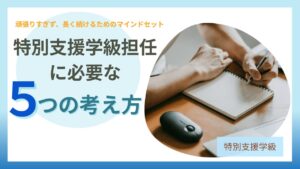
コメント