知的障害のあるお子さんを通常学級や情緒学級で学ばせたいと考える保護者との面談は、お互いの思いをすり合わせる大切な場です。
この記事では、面談前の準備から強み・課題の共有、学級選択のメリット・デメリット比較、具体的な支援プランの立て方まで、7つのポイントをわかりやすく解説します。初めての面談でも安心して臨めるよう、実例を交えながら丁寧にご紹介しますので、ぜひご活用ください。
前提条件と保護者へのお願い
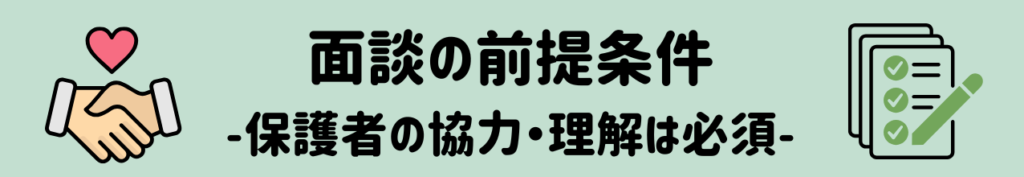
- 学校の役割と限界
- 学校では全ての支援ができるわけではありません。授業内での配慮や補習は可能ですが、ご家庭での学習環境整備や日々の声かけがないと、学びの定着は難しくなります。
- 保護者の協力が不可欠
- 宿題の取り組み状況やお子さんの変化は家庭でしか把握できない情報です。連絡帳やメールでのこまめな情報共有、家庭での学習サポートをぜひご協力ください。
- 学校-家庭-専門機関の連携
- 就学相談や療育機関の検査結果を学校と共有し、支援プランに反映します。保護者が検査結果や医療機関の提案を学校に伝えることも大切です。
これらの前提を共有したうえで、以下の7つのポイントを進めていきましょう。
1.はじめのあいさつ・面談の目的を共有

まずは感謝の気持ちを伝え、今日の面談のゴールを明確にしましょう。
- 面談にお越しいただいたことへの感謝
- 本日の目的:「○○さんの学びの場(通常学級/情緒学級)について、ご家庭の希望を伺いながら一緒に考える」
2.保護者のご希望を丁寧にヒアリング

「なぜ通常学級(または情緒学級)がよいと考えているのか」をお聞きします。
- 友だちと同じ環境で学びたい
- 学習内容の幅を広げたい
- 少人数で安心して学ばせたい など
ご家庭での普段の様子や、お子さんが楽しんでいる遊びや学びも教えていただくと、その後の提案がスムーズです。
3.お子さんの現状(強みと課題)を具体的に共有

数値ではなく「行動の様子」で説明すると、ご家庭にも伝わりやすく安心感を与えられます。
強み(できること)
- 挨拶やお返事がしっかりできる
- 興味を持った活動には集中して取り組める
課題(サポートが必要なこと)
- 長い文章の読み取りや手順把握に時間がかかる
- 集団指示への反応に遅れが出やすい
4.在籍のメリット・デメリット比較
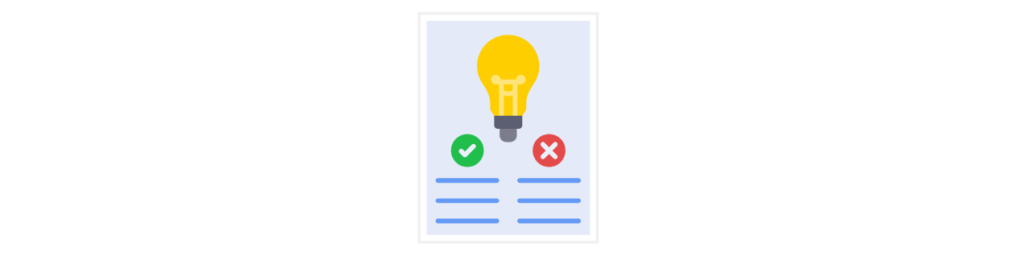
| 学級 | メリット | デメリット・懸念点 |
|---|---|---|
| 通常学級 | ・多様な友人関係が築ける・学習内容の幅が広い | ・学習進度についていけないことがある・支援体制が手薄になりやすい |
| 情緒学級 | ・少人数で安心感がある・個別支援が手厚い | ・交流できる友達の範囲が限られる・扱う教科内容が狭まる場合がある |
5.具体的な支援・配慮例のご提案

- 教室内の配慮
- 隣席に支援員を配置
- ワークシートは拡大コピーで見やすく
- 学習サポート体制
- 放課後の補習時間を設定
- 友だち同士で助け合うピアサポーター制度
- 社会性・情緒面のフォロー
- 安心できる休憩スペースを用意
- 活動時間を見える化するタイムタイマーの活用
6.トライアル期間と切り替えルールの設定

- まず1~2か月、通常学級で学んでみる「トライアル期間」を設ける
- 月ごとに面談や連絡帳で状況を振り返り、必要なら情緒学級へ移行
- 切り替えのタイミングや方法をあらかじめ合意しておくと安心
7.役割分担と今後のスケジュール
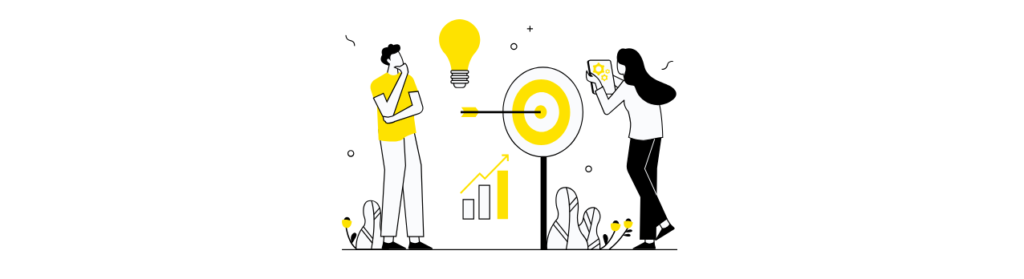
- 学校側:支援プランの実施と月末の経過報告
- 保護者:家庭学習の様子や気になる点の連絡
- 次回面談:1か月後を目安に振り返り面談を設定
知的障害児の保護者面談完全ガイド|通常学級・情緒学級希望時の7つの支援ポイントQ &A

- 面談で保護者が感情的になったときはどうすれば?
-
一度「少し休憩しましょうか」と間を置き、落ち着いてから「今大事にしたいことは何か」を問い直すと、対話の焦点を整理しやすくなります。
- 通常学級と情緒学級のメリット・デメリットを伝えるコツは?
-
表形式で比較すると視覚的に理解しやすくなります。さらに、実際の事例やイメージ写真を添えると、具体性が増して納得感が高まります。
- トライアル期間中に様子が思わしくなければ、すぐに切り替えたほうがいい?
-
まずは月1回の振り返り面談で状況を共有し、「改善できそうか」「情緒学級に移るか」を保護者と一緒に検討しましょう。安易な切り替えは混乱を招くこともあるので、合意形成を大切に。
図のように、左側に「通常学級」、右側に「情緒学級」のメリット・デメリットを整理しました。視覚情報として直感的に比較できるため、ご家庭にも納得感を持って伝えやすくなります。
通常学級と情緒学級のメリット・デメリットの事例紹介
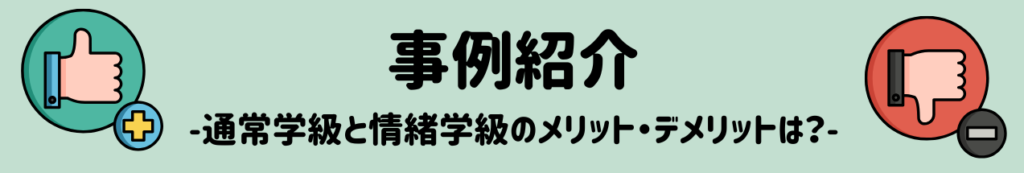
事例1:家庭でのサポートが学習定着を後押し
- 背景:Cさん(小学4年、軽度の知的障害)。学校では通常学級でトライアル中だが、家庭でも支援が必要と判断。
- 家庭での支援内容:
- 学習スペースの整備
- リビングの一角に学習机を設置し、周囲の視覚的・音響的刺激を最小限に。
- タイマーと「今日のやることリスト」を掲示し、見通しを持って学べる環境を用意。
- 音声と視覚の併用
- 国語は教科書の音声データを流しながら読み、分からない漢字はカードで確認。
- 算数ドリルは保護者が問題を読み上げ、子どもに答えを書かせる形式で取り組む。
- 成功体験の見える化
- できた問題ごとにシールを貼る「達成ボード」を用意。
- 1週間で貼れたシールの数に応じて、小さなご褒美(好きな絵本の読み聞かせなど)を設定。
- 学習スペースの整備
- 成果:
- 家での学習習慣が定着し、学校でのドリル取り組み時間が1か月で約20%短縮。
- 自分で「今日はこれだけできた!」と実感できることで、学習への自己効力感が向上。
- 保護者とのコミュニケーションも増え、家庭と学校の支援が一体となった安心感のある学びが実現。
事例2:通常学級トライアル
- 背景:Aくん(小学5年、軽度の知的障害)が「友達と一緒に学びたい」と希望
- 支援内容:
- 隣席に支援員を配置
- 授業資料は拡大プリント+音声教材を併用
- 週1回、支援員とペア学習
- 成果:
- 友達との会話が増え、授業への参加意欲が向上
- 課題の取り組み時間が当初の2/3に短縮
事例3:情緒学級で安心して学習
- 背景:Bさん(小学6年、中度の知的障害)が「少人数で落ち着いて学びたい」と希望
- 支援内容:
- 1クラス6名編成の情緒学級に在籍
- 授業は生活単元学習中心、個別カリキュラムで進行
- タイムタイマーで「次の活動」までの時間を可視化
- 成果:
- 授業中の不安や混乱が減少し、発言回数が増加
- ワークシートの完成率が80%以上に改善
このように、具体的な事例を組み合わせることで、保護者には「どうやって支援したら良いか」「どんな支援が受けられるのか」「子どもにとってどのような効果があるのか」を明確に伝えられます。ぜひ面談資料としてご活用ください。
知的障害児の保護者面談完全ガイド|通常学級・情緒学級希望時の7つの支援ポイントまとめ
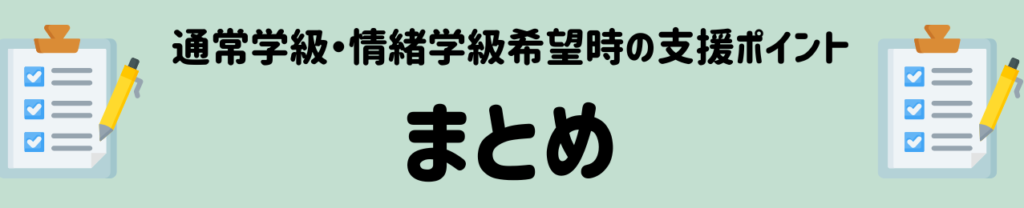
- 保護者の思いを丁寧に聞き取り、安心感を与える
- お子さんの強み・課題を具体的に共有し、共通理解を深める
- 通常学級/情緒学級のメリット・デメリットを比較提示
- 必要な支援・配慮例を具体的に提案
- トライアル期間と切り替えルールで安心感を担保
- 役割分担とスケジュールを明確化し、継続的なフォロー体制を構築
この7つのポイントを押さえれば、知的障害のあるお子さんとご家庭にとって最適な学びの場を一緒に設計できます。ぜひ次回の保護者面談でご活用ください。




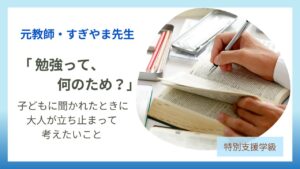

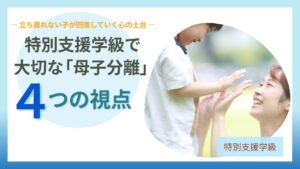


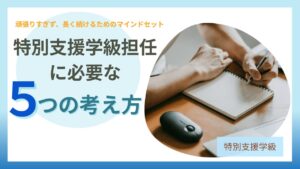
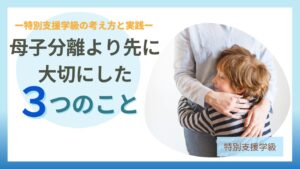

コメント