〜支援学級と通常学級をつなぐ“見えない橋”〜
特別支援学級の担任をしていると、「交流及び共同学習、どう進めたらいいのか迷う…」という声をよく聞きます。
行事や日々の活動で自然な関わりがある反面、きちんとした見通しや準備がないまま「なんとなく」実施してしまうこと、ありませんか?
そこで力になるのが「交流及び共同学習 実施計画案」です。
この計画案があることで、子どもたちが安心して楽しく交流できるだけでなく、先生同士の連携もスムーズになります。
今回は、なぜこの実施計画案が必要なのかを3つの理由に分けてお伝えします。
なぜ交流及び共同学習の実施計画案が必要なのか

1.全員が「共通の目的」に向かえるから
文部科学省は、「交流及び共同学習は、障害のある子どもの社会性や自立を育てる上で大切な機会」としています。
でも実際の現場では、活動の目的がはっきりしていないと、先生同士の認識のズレや、子どもたちへの関わり方の差が出やすくなります。
「この活動は、どんな力を育てたいのか」
「何を大切にして関わるのか」
その視点を共有するためにも、計画案が“共通の地図”となるのです。
2.活動が“行き当たりばったり”にならない
たとえば、「来週、交流やります」と急に決まった場合。
準備が間に合わず、支援学級の子も通常学級の子も戸惑ってしまう…そんなことも起こり得ます。
でも、年間を見通した計画があれば、
- どの時期に
- 誰と誰が関わり
- どんな活動を行うのか
をあらかじめ想定できるので、先生も子どもも安心です。
そして何より、活動の質が安定します。
これは支援学級の子にとって、とても大事なポイントですよね。
3.“やって終わり”にならないために
交流活動は、やればいいというものではありません。
「関わってみてどう感じたか」
「次はどうしてみたいか」
そのふり返りが、子どもたちの成長に大きくつながっていきます。
実施計画案では、活動後のふり返りの場や、担任同士の共有も大切にしています。
つまり、「次につながる学びのサイクル」をつくることができるのです。
「交流及び共同学習実施計画案」が必要な3つの理由のQ &A

- この計画案は必ず作らなければいけませんか?
-
法的な義務はありませんが、交流及び共同学習の目的や方法を明確にし、先生同士で共通理解を持つためには大変有効です。文部科学省の方針にも沿った形で、安心して活動を進めるための“道しるべ”として活用できます。
- 活動内容は学年や学校によって変えてもいいの?
-
もちろんです。季節行事、学年の発達段階、児童の実態に合わせて柔軟に計画を立ててください。計画案に例を挙げているのはあくまで参考です。無理のない形で、子どもたちの「楽しかった!」が引き出せる活動がベストです。
- 交流の回数はどのくらいが目安ですか?
-
毎日から週に3回程度を目安にすると、準備や振り返りも含めて無理なく取り組めます。大きな交流会などは学期ごとに1回実施するだけでも、関係づくりに十分効果があります。無理のないペースで、継続することが大切です。
- 支援学級の子が緊張してうまく参加できないこともあります…
-
それも大切な“学びの一歩”です。計画案の中では、「無理に関わらせない」「安心して過ごせるように見守る」ことも大切な視点として書くこともあります。事前に関係づくりや見通しの提示をしておくことで、少しずつ参加できるようになります。
- 通常学級の担任にどのように協力をお願いしたらいい?
-
計画案に「交流担任への準備物一覧」がありますので、それをもとに具体的に依頼すると伝わりやすいです。また、「この活動を一緒に作っていきたい」という姿勢で相談することで、自然に協力体制が築けます。
おわりに:先生自身の“安心”にもつながる

交流活動は、支援学級の担任だけでなく、関わるすべての先生の理解と協力が必要です。
だからこそ、この「実施計画案」は、先生同士をつなぐ橋渡しにもなります。
「やってよかったね」で終わらず、
「またやりたいね」と自然に思える関係づくりのために。
今こそ、一歩先の準備を始めてみませんか?
公式LINEでは、期間限定で「交流及び共同学習の実施計画案」をプレゼントしています。
公式LINEで「交流及び共同学習」とコメントください!

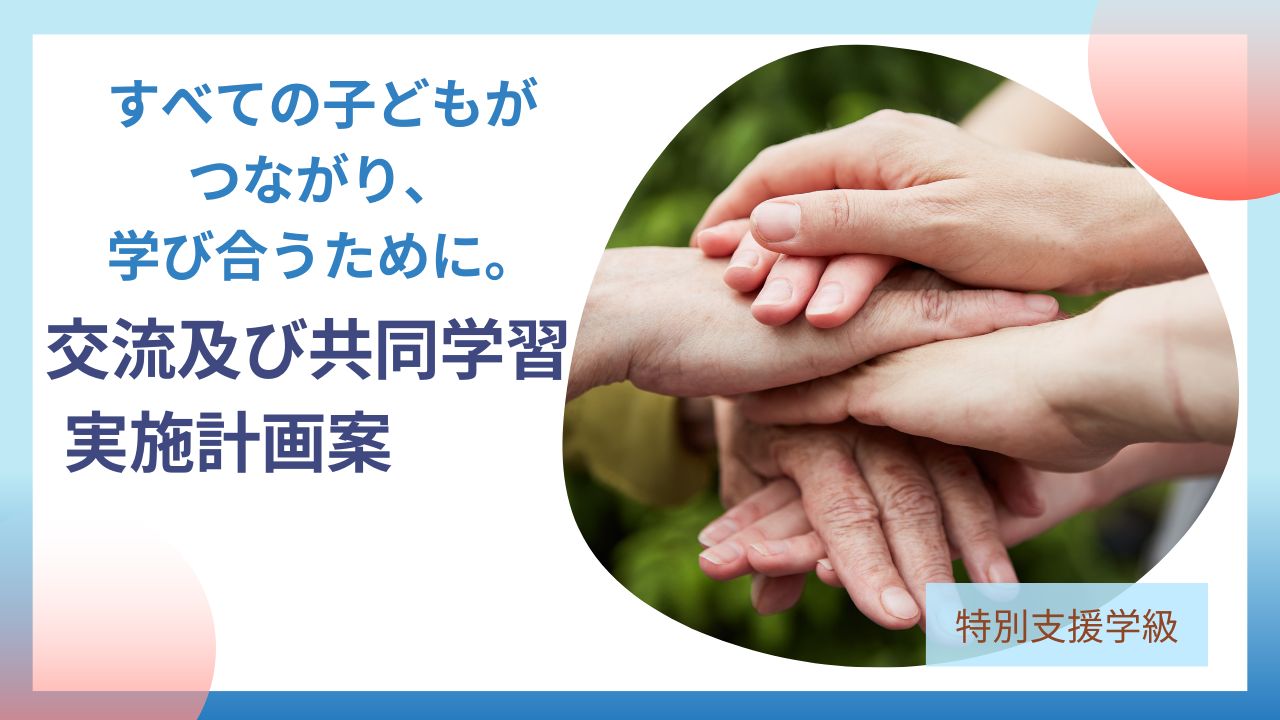


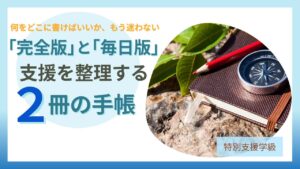
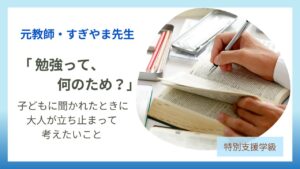

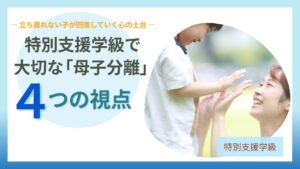


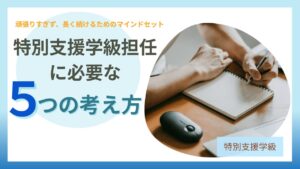
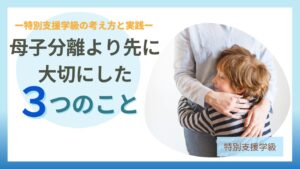
コメント