「ひらがなは読めるのに、文になるとつまずく」
「書けるようになったはずなのに、まちがいが減らない」
――そんな悩みをかかえる保護者や先生は少なくありません。
今回紹介するのは、特別支援学級の小学3年生・しょうたろうくん。
学習に苦手意識を持っていたしょうたろうくんが、「べんきょうって楽しい!」と感じるようになったきっかけがあります。
それが、私が開発した「ステップえもじカード」です。
絵と文字をいっしょに覚えることで、子どもが“あそびながら学べる”ように作られた教材です。
この記事では、しょうたろうくんとお母さんの実践インタビューをもとに、
- どんな悩みをかかえていたのか
- 「ステップえもじカード」で何が変わったのか
- 家庭や学校でどう活用できるのか
をわかりやすく紹介します。
🎥 実際のインタビュー動画はこちら
👆クリックでYouTube動画へ
「読めない」「書けない」から“笑顔の学び”に変わる実践ストーリーをご覧ください。
ひらがな・カタカナのつまずきに悩んでいた日々
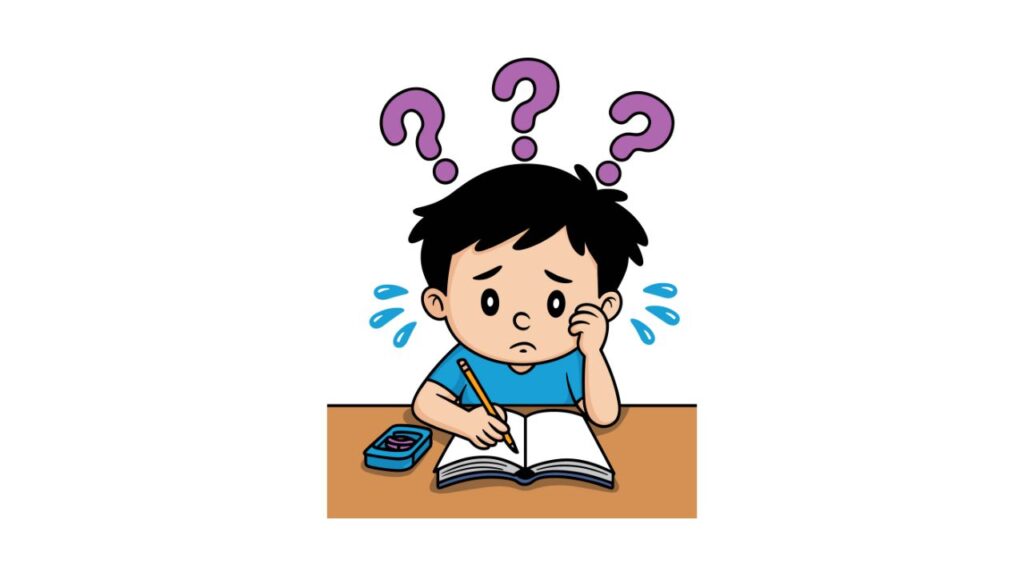
しょうたろうくんはひらがな・カタカナを書ける一方で、読み間違い・書き間違いが時々みられました。学校では漢字の学習も始まり、お母さんは「どこでつまずいているのか」「どう確認し進めれば良いのか」に不安があったそうです。
初見でワクワク! “勉強っぽくない”から続けやすい
絵もじカードを見た第一声は「なにこれ?やりたい!」。子どもにとって絵と文字が結びつくことは興味の入口になりやすく、遊び感覚で取り組めます。カードと連動したワークシートも好評で、「簡単!やりやすい!」と笑顔で進められました。
- お気に入りは「書きやすい文字のカード」
- カード+ワークシートの二段構えで「読む・書く」を行き来
- 短時間でも達成感が得られる設計
“課題の見える化”で、親の焦りが安心に変わる
カードとワークシートで学びを進めると、拗音(ゃ・ゅ・ょ)や濁音などの弱点が具体的に見えてきました。お母さんは「どこを練習すれば良いか」が明確になり、焦りが見通しに変わったと話します。
「『できているはず』と思い込んでいた部分が見直せました。今の力に合わせて安心して進められます。」
“やらされる勉強”から“自分でやりたい学び”へ
関わり方を「管理」から「共に楽しむ」へ。すると、翔太郎くんは自分から「もう少しやりたい」と言うようになりました。学びが親子の「楽しい時間」に変わると、集中力と笑顔が自然に生まれます。
変化のサイン
- 「やる?」→「やりたい!」という声が増える
- 短時間でも手ごたえ(できた!)が共有できる
- 下のきょうだいに教えるなど、学びの自発性が連鎖
実際の親子のやりとりや笑顔の変化は、こちらの動画でもご覧いただけます👇
学級&家庭での使い方:3ステップ

① 現状を知る
カードとワークシートで得意・ニガテを把握。特に拗音・濁音・促音の定着度を軽く確認。
② 小さく積み上げる
「できるカード」から着手。1日5〜10分の短時間でOK。成功体験を連続させます。
③ 遊びを混ぜる
カード神経衰弱・ビンゴ・タイムアタックなどゲーム化。家族やクラスで協力戦も効果的。
よくある質問(FAQ)
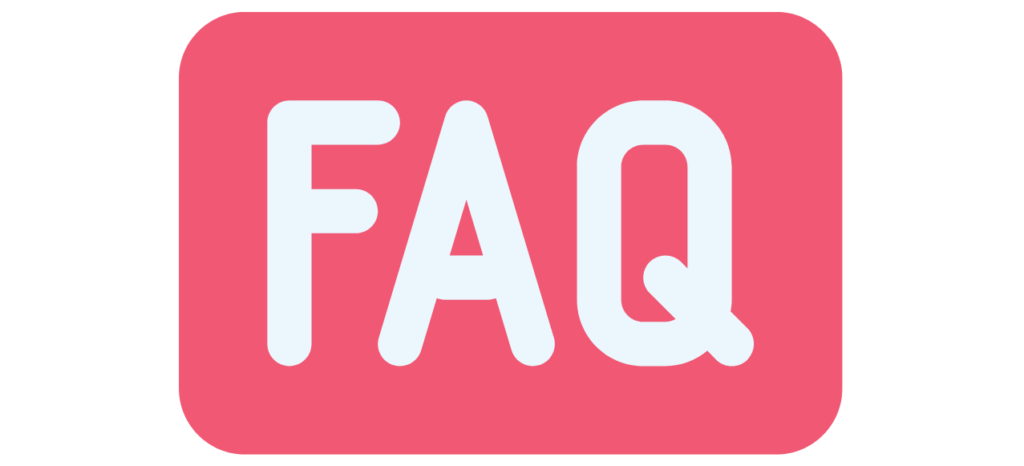
Q1. 何歳から使えますか?
A. ひらがなへの興味が出始めた時期から。年長〜小学校低学年での導入が特に効果的です。
Q2. どれくらいで効果が出ますか?
A. 個人差はありますが、短時間×高頻度で1〜2週間ほどで「読み間違いが減った」などの変化が見られることが多いです。
Q3. 学校の宿題と両立できますか?
A. 絵もじカードは補助教材として相性が良いです。宿題の前後に5分挟むだけでも集中の助けになります。
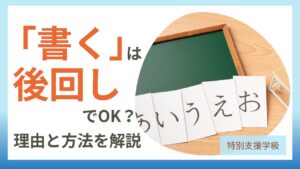
「読めない」「書けない」からの変化|ステップえもじカードで笑顔が生まれた特別支援学級の実践記のまとめ
絵もじカードは、読み書きの土台を楽しく・やさしく築くための入口です。焦らず、一歩ずつ。親子やクラスで「できた!」を増やしていきましょう。
🎁 無料プレゼント&教材のご案内
公式LINEでひらがな絵もじカード(簡易版)を配布中。
【特別支援学級】読み書きが苦手な子が“勉強楽しい”に変わった!ステップえもじカード実践インタビュー動画の概要欄にあるキーワードを送るだけで受け取れます。さらに、特別支援学級の先生向け7大特典もご用意しています。
- 年間指導計画案
- 実態把握チェック(34ページ)
- 研究授業の時短テンプレ
- 親子でできる授業参観アイデア集
- 読み聞かせにおすすめの絵本10選
- 研究授業づくりの5ステップ
- ワークシート&カードの授業アイデアリンク集




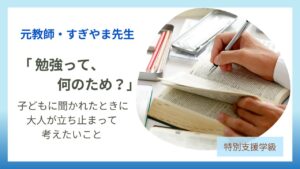

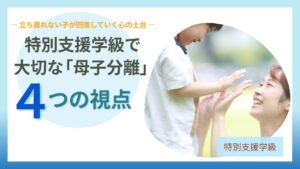


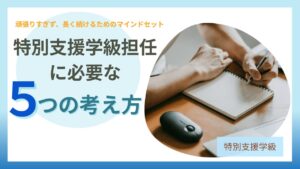
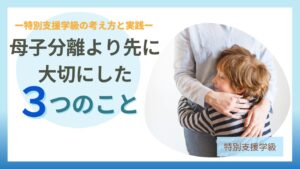

コメント