年間指導計画は、子どもたちと過ごす一年をデザインする大切な作業です。
でも実際には、
「どうやって立てたらいいかわからない…」
「毎年バタバタで、なんとなく作ってしまう…」
そんな悩みを抱えている先生も少なくありません。
私も初めて年間計画を作ったとき、
「これで大丈夫なのかな」と不安を抱えながら進めた記憶があります。
この記事では、
年間指導計画を立てるときに気をつけたいポイントと、
具体的な作り方の流れを、わかりやすくまとめました。
さらに、空白を埋めるだけで使える無料テンプレートもご用意しています!最後までお読みください!!
「もっとラクに、でも子どもに合った計画を立てたい」
そんな先生の力になれたらうれしいです。
年間指導計画を立てる際に気をつけること

年間指導計画は、子どもたちと1年間をどう過ごすかを見通す、大事な土台です。
ここで押さえておきたいポイントは、次の5つです。
1. 「子どもの実態」を最優先に考える
教科書やカリキュラムにとらわれすぎず、今のこの子たちに必要な力を見極めます。
一人ひとりの様子を思い浮かべながら、無理のない目標を立てましょう。
2. 大きな行事や季節の流れを押さえる
運動会、音楽会、社会見学など、動かせない予定を早めにおさえておきます。
また、季節ごとの体調や気分の変化も考慮して、余裕のある計画を意識します。
3. 「無理のないステップ」を意識する
最初からハードルを上げすぎないことが大切です。
小さな成功体験を積み重ねることで、子どもたちは自信を育んでいきます。
4. 柔軟に見直せるようにしておく
計画は「決して変えてはいけないもの」ではありません。
子どもたちの成長や変化に応じて、柔軟にアップデートしていきましょう。
5. 「学びと生活のバランス」を意識する
学習だけでなく、生活力や人との関わりを育てる時間もしっかり確保します。
特別支援学級なら、個々に必要な支援時間も大切にしていきます。
年間指導計画の作り方【具体例】
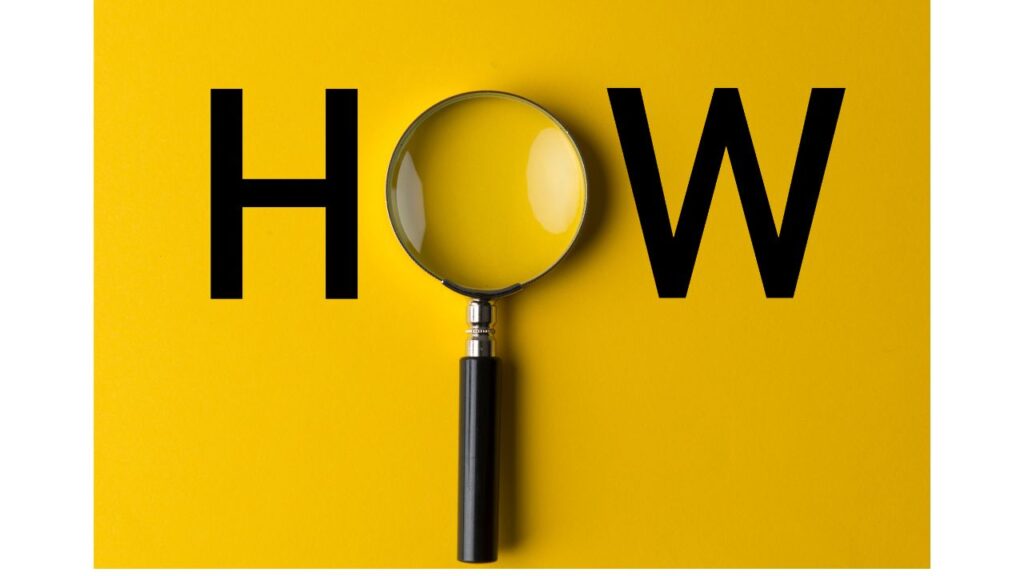
ここからは、実際に年間指導計画を立てる流れを、具体例と一緒に紹介します。
ステップ1 1年の大きなイベントをリストアップする
まず、動かせない行事や予定を書き出します。
例:
- 5月 運動会
- 10月 社会見学
- 11月 音楽発表会
- 3月 卒業式・修了式
これらの行事に合わせて、余裕を持った計画を意識します。
ステップ2 学びたい内容・育てたい力を洗い出す
次に、今年育てたい力を整理します。
例:
- 国語 → 話を聞いて自分の考えを伝える
- 算数 → 簡単な買い物ができる
- 生活 → 身の回りのことを自分でできる
- 社会性 → 友だちと簡単なやりとりができる
「教科書を全部終わらせる」ことがゴールではありません。
子どもたちができるようになりたいことを中心に考えます。
ステップ3 ざっくり月ごとにテーマを決める
行事や季節に合わせて、月ごとのテーマを決めます。
例:
| 月 | テーマ・重点 |
|---|---|
| 4月 | 新しい環境に慣れる、自己紹介ができる |
| 5月 | ルールを守って運動会を楽しむ |
| 6月 | 買い物ごっこで金銭感覚を育てる |
| 7月 | 1学期のまとめ、夏休みの過ごし方 |
| 9月 | 生活リズムを整える |
| 10月 | 社会見学に向けた公共マナーを練習 |
| 11月 | 音楽発表会に向けて表現を楽しむ |
| 12月 | ふりかえりと冬休み準備 |
| 1月 | 新しい年の目標を立てる |
| 2月 | 卒業や進級に向けた心の準備 |
| 3月 | 感謝の気持ちを伝えるまとめ学習 |
ステップ4 活動や授業のアイデアを具体的に考える
テーマが決まったら、具体的な活動や授業を考えます。
例:
- 6月(買い物ごっこ)
- 「100円以内で好きなお菓子を買う」
- 「おつりをもらう練習をする」
- 10月(公共マナー)
- 「公共交通機関の使い方を絵本で学ぶ」
- 「バスごっこ遊びでルール練習」
子どもたちが楽しみながら力をつけられる工夫を入れるのがポイントです。
ステップ5 年間をざっくり表にまとめる
最後に、見通しが一目でわかる表にしてまとめます。
こんなイメージです。
| 月 | 重点テーマ | 主な活動・行事 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 4月 | 新しい環境に慣れる | 自己紹介・学校探検 | 不安を減らす声かけを意識 |
| 5月 | ルールを守る | 運動会練習・本番 | チームで協力する体験を |
| 6月 | お金の使い方を学ぶ | 買い物ごっこ | 小さな成功体験を積み重ねる |
| … | … | … | … |
年間指導計画はこう立てる!初心者でも安心の作り方と注意ポイントのQ &A

Q1. 年間指導計画はどの時期に立てればいいですか?
A.
基本的には新年度が始まる前(3月末〜4月初め)に作成します。
ただし、子どもたちの実態を見てから調整することも大切なので、5月ごろに一度見直すことをおすすめします。
Q2. 年間指導計画は一度立てたら変更してはいけない?
A.
いいえ、途中で変更してOKです!
子どもたちの成長やクラスの状況に合わせて、柔軟に見直していくことがむしろ大切です。
Q3. 特別支援学級の場合、通常学級のカリキュラムに合わせるべき?
A.
無理に合わせる必要はありません。
「その子にとって必要な力」を育てることを最優先に考えましょう。
必要なら通常学級と相談しながら、ペースや内容を調整していきます。
Q4. すべての教科をまんべんなく取り組まないといけない?
A.
必ずしもそうではありません。
特に特別支援学級では、生活力や社会性など、学び以外の力も重視します。
子どもたちにとって必要なものを優先して、バランスよく取り組めば大丈夫です。
Q5. 計画を立てるとき、どれくらい細かく書くべき?
A.
最初から細かく書きすぎなくてOKです。
大まかな見通しと月ごとのテーマがあれば十分。
活動案などの細かい部分は、子どもの様子を見ながら徐々に決めていく形が自然です。
年間指導計画はこう立てる!初心者でも安心の作り方と注意ポイントのまとめ

年間指導計画は、「完璧な予定表」を作ることが目的ではありません。
子どもたちの成長を支える「道しるべ」として、
無理なく、楽しく、そして柔軟に考えていきましょう。
先生自身も、1年間を楽しめるような計画を立てていきたいですね🌸

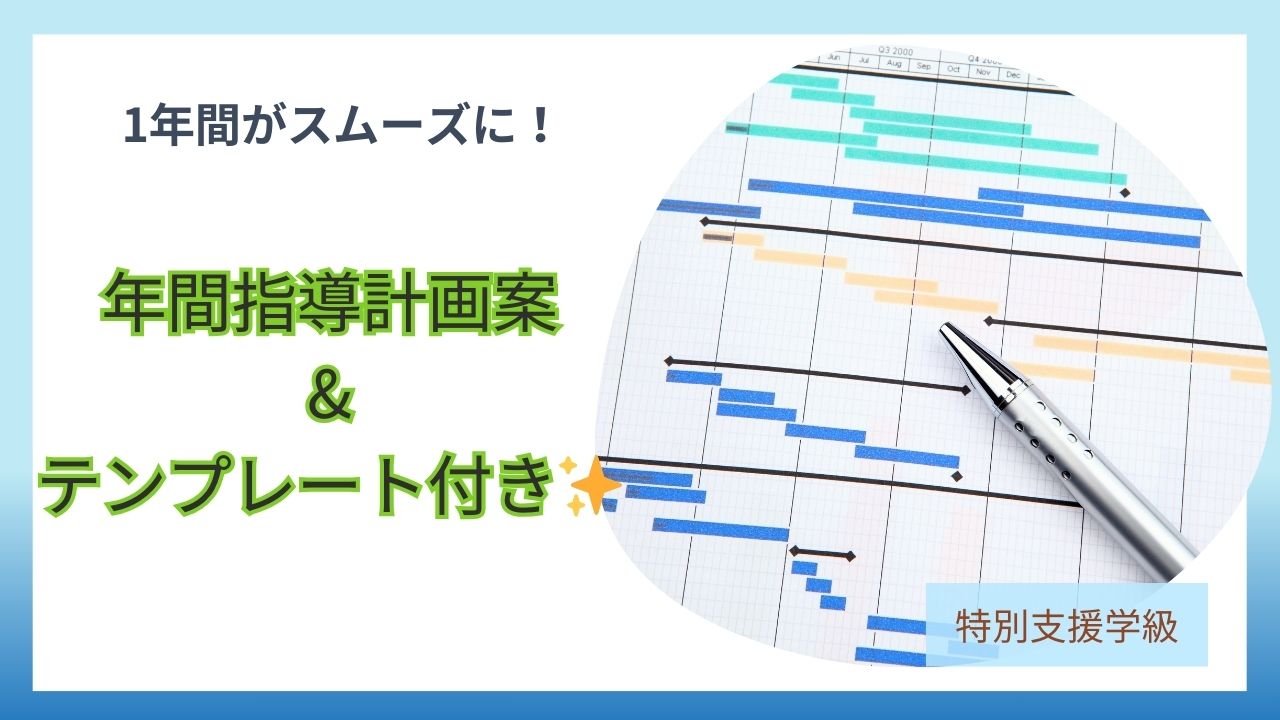



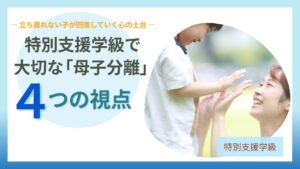


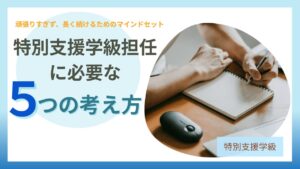
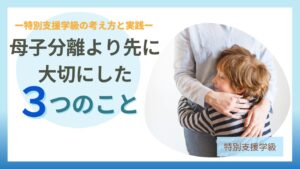

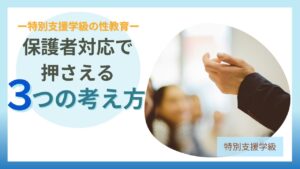
コメント