「集中できない」「落ち着かない」…特別支援学級での授業や学習後の時間に、こうした悩みを感じる先生は多いのではないでしょうか。
実は、YouTubeなどで配信されている「作業用BGM動画」を上手に活用することで、子どもたちの集中や切り替えが驚くほどスムーズになることがあります。
この記事では、特別支援学級の先生が抱えやすい悩みに合わせて、BGMの具体的な使い方と工夫をご紹介します。
 ぷーた先生
ぷーた先生この記事で紹介する動画はこちらです。かんたん指導案も最後にのせています!
【担任向け】特別支援学級で使える『20分授業・作業用BGM』集中できる環境づくりに
悩み① 集中できず、落ち着かない時間が多い
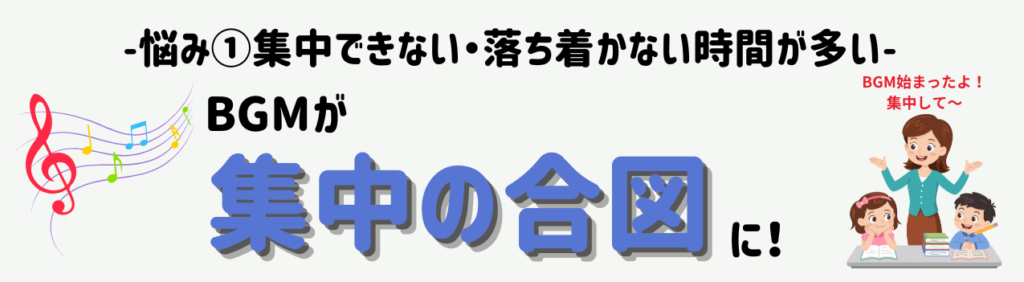
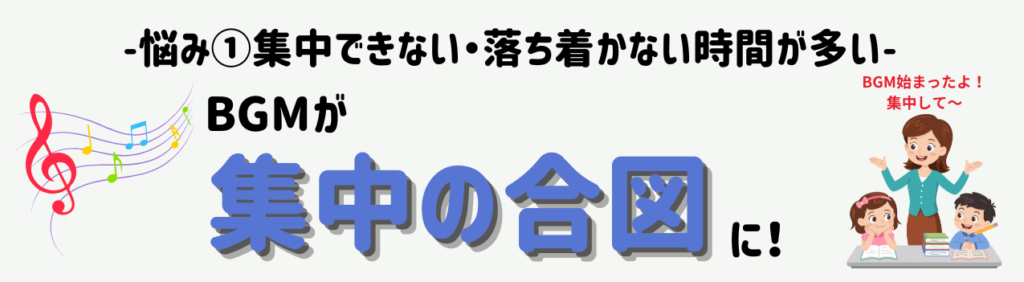
授業や作業の途中でソワソワしたり、立ち歩いてしまう子がいると、どうしても学級全体が落ち着かなくなります。
解決策:BGMを「集中の合図」にする
今回のBGM動画には、10:00で「あと10分」・15:00で「あと5分」などという字幕が出ます。
この字幕をスタートの合図にすると、子どもたちは「ここから10分だけ」「あと5分だけ」と見通しを持ちやすくなります。
- 5:00から再生 →「あと15分集中」
- 10:00から再生 →「あと10分集中」
- 15:00から再生 →「あと5分挑戦」
短時間でも「できた!」という達成感を積み重ねることで、徐々に集中が長く続くようになります。
悩み② 授業の切り替えがスムーズにいかない
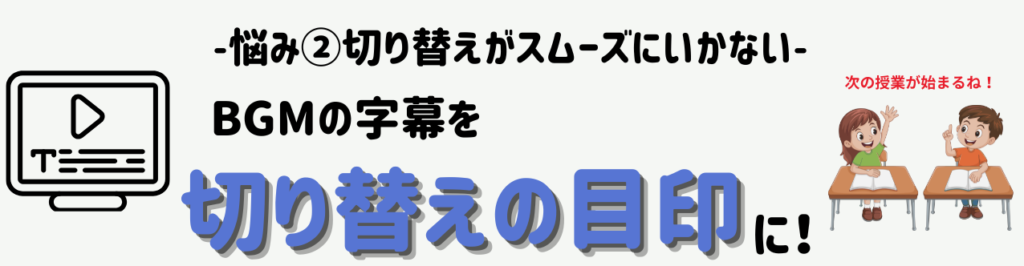
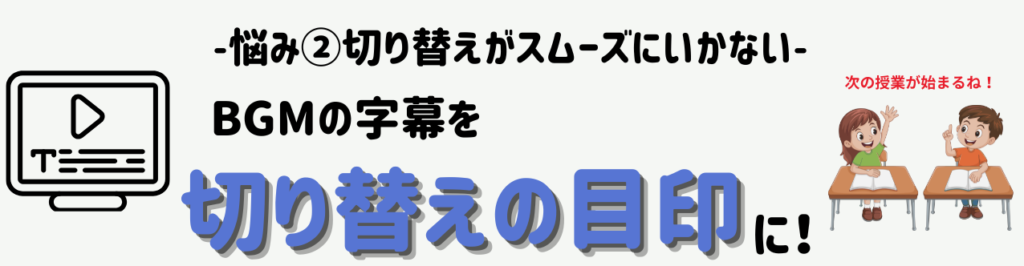
国語から算数へ、学習から帰りの会へ…。切り替えのたびにざわついてしまい、次の活動に入るまでに時間がかかることはありませんか?
解決策:字幕を切り替えの目印にする
BGMの字幕は「あと5分」の合図にも使えます。
活動の終わりが近づいたことを自然に知らせるので、教師が声を大きくしなくても、子どもたちが次の行動に移りやすくなります。
「音楽が止まったらおしまい」というルールを加えれば、子どもたちが自分で気持ちを切り替える習慣がつきます。
悩み③ ゆっくりタイムがざわざわしてしまう
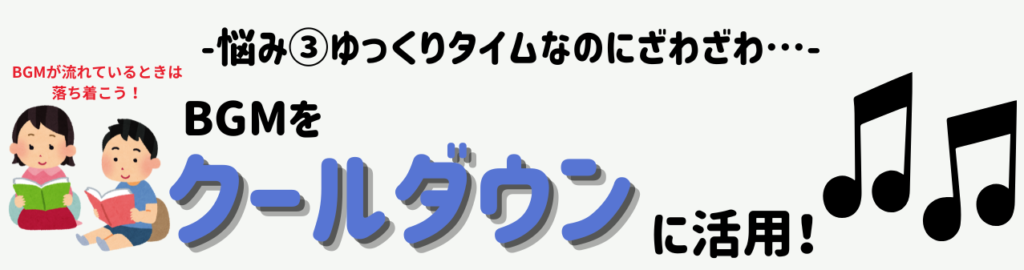
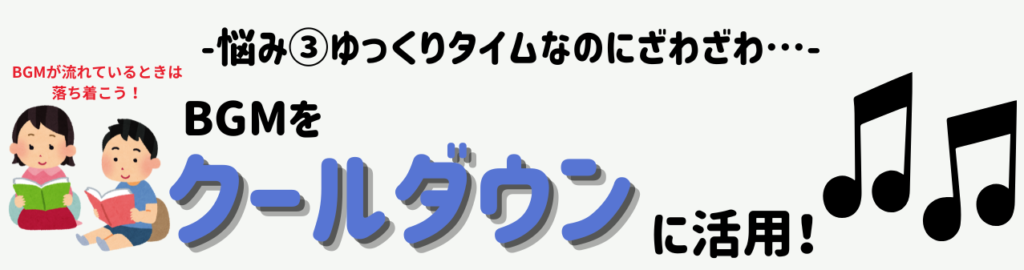
学習後の「ゆっくりタイム」は本来リラックスする時間ですが、逆にざわざわして落ち着かなくなることもあります。
解決策:BGMを「クールダウン」に活用
授業が終わったら、BGMを流して「気持ちを落ち着ける時間」を設定しましょう。
- 読み聞かせのバックミュージックに
- 日記タイムや振り返りのときに
- 気持ちが高ぶっている子のクールダウンに
- 深呼吸の時間に
BGMがあることで、教室に自然な静けさが広がり、落ち着いた空気で次の活動に移れます。
悩み④ BGMの使い方が分からない
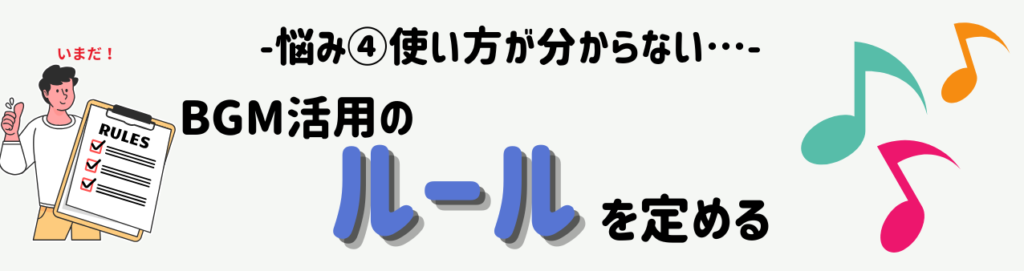
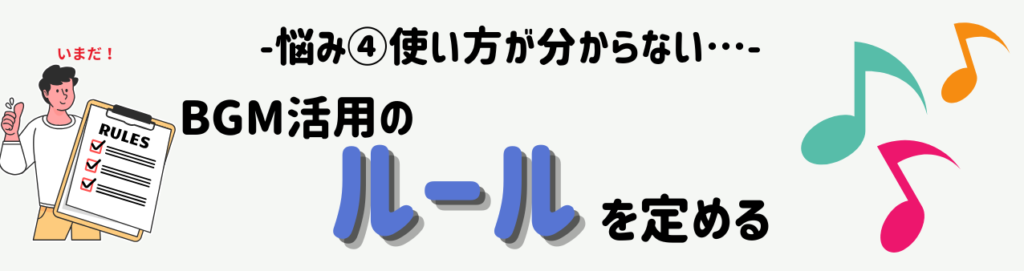
「ただ流すだけでは意味があるの?」と不安になる先生もいます。
解決策:具体的な活用ルールを決める
- 音量:先生の声が通る程度(大きすぎない)
- 曲の種類:歌詞なし(インストゥルメンタル)がおすすめ
- 聴覚過敏の子:イヤーマフや耳栓で調整
- ルール化:「音が止まったら終了」など分かりやすい決まりをつくる
こうしたルールをあらかじめ子どもと共有しておくことで、BGMが効果的に働きます。
悩み⑤ 工夫がマンネリ化してしまう
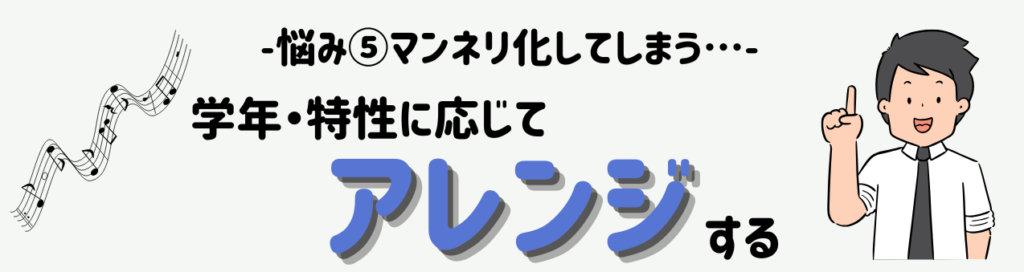
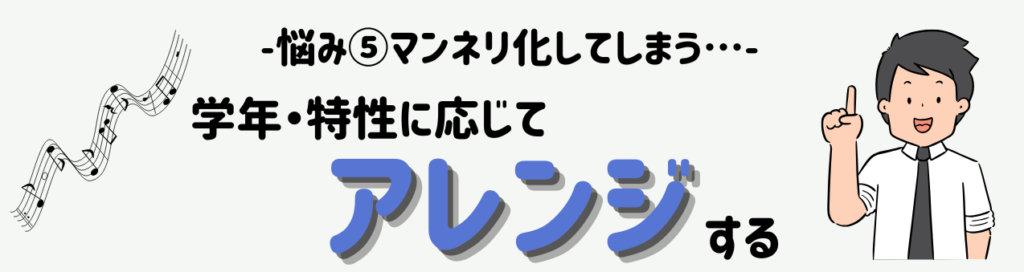
毎日の授業に取り入れる工夫がマンネリ化すると、子どもも飽きてしまいます。
解決策:学年・特性に応じてアレンジ
- 低学年:5分から始める。短い成功体験を積ませる
- 中学年:10分→15分→20分と段階的に伸ばす
- 高学年:自分で管理。家庭学習でも同じ動画を活用させる
さらに、特性に合わせて工夫することも大切です。
- 集中が続かない子 → 「あと5分」から始める
- 不安が強い子 → 字幕を一緒に確認して安心感を持たせる
- 気持ちの切り替えが苦手な子 → 終了後に「深呼吸して終わり」のルールを追加
- 聴覚に敏感な子 → 無理に聞かせず、周囲の雰囲気づくりにだけ活用
なぜBGMを授業に取り入れるのか?


BGMを流すことで、教室に自然なリズムや雰囲気をつくり出すことができます。研究でも以下のような効果が示されています。
- 着席時間が増える:子どもが席に座って作業に取り組む時間が長くなる。
- 気持ちの切り替えがスムーズになる:音楽を合図に次の活動へ移れる。
- 落ち着きが出る:リラックス効果があり、不安やざわつきが和らぐ。
単なる「BGM」ではなく、子どもの集中や安心をサポートする「学習環境づくりの道具」として活用できます。
この動画の特徴 ― 字幕をうまく活用!
今回ご紹介する動画には、10:00で「あと10分」、15:00で「あと5分」 という字幕が出る工夫があります。
これを合図として使えば、教師が時計を気にしなくても自然に時間の見通しを持たせられます。
- 短い集中 → 10:00から再生して「あと10分」でスタート。
- さらに短い集中 → 15:00から再生して「あと5分」だけ挑戦。
「時間が区切られている安心感」と「ラストスパートの達成感」を子どもに味わわせることができます。
授業での活用例(指導案イメージ)
【担任向け】特別支援学級で使える『20分授業・作業用BGM』集中できる環境づくりに
- 導入(1分)
- 「今日は音楽を使って短い時間だけ集中してみよう」と伝える。
- 動画を10:00から再生し、「あと10分」の字幕が出たところでスタート。
- 展開(5〜10分)
- ドリルやワーク、読書など静かな作業を実施。
- 15:00の「あと5分」で「もう少しがんばろう」と声かけ。
- まとめ(2分)
- 音楽が止まったら作業も終了。
- 「どうだった?」「どのくらい集中できた?」と簡単に振り返る。
学年別の活用ポイント
- 低学年(1〜2年)
→ まずは5分から。字幕「あと5分」を合図に短時間集中。 - 中学年(3〜4年)
→ 10分→15分→20分と段階的に挑戦。字幕を見て「あと少し!」と意識させる。 - 高学年(5〜6年)
→ 自分で再生位置を決めて時間管理。家庭学習でも同じ動画を使わせると習慣化できる。
特性別の工夫
- 集中が続かない子
→ 「あと5分」からスタートして成功体験を積む。 - 不安が強い子
→ 「音が止まったらおしまい」と最初に見通しを伝え、字幕を一緒に確認。 - 気持ちの切り替えが苦手な子
→ BGM終了後に「深呼吸して終わり」のルールをセットに。 - 聴覚に敏感な子
→ イヤーマフや耳栓で調整。BGMを流すのは周囲だけにし、本人には静かな環境を。
ゆっくりタイムでの活用もおすすめ!
授業だけでなく、学習が終わった後の「ゆっくりタイム」にも最適です。
- 「今日がんばったこと」を話す時間のBGMに。
- 読み聞かせや日記タイムのバックミュージックに。
- 気持ちが高ぶったときのクールダウンに。
【担任向け】特別支援学級で使える『20分授業・作業用BGM』集中できる環境づくりに
小学校特別支援学級で使える!授業・ゆっくりタイムに最適な作業用BGM活用法のQ&A


- BGMはどのくらいの音量で流せばいいですか?
A. 教師の声がしっかり通る程度が目安です。大きすぎると逆に気が散るので、子どもたちの作業音が聞こえるくらいがちょうど良いです。 -
教師の声がしっかり通る程度が目安です。大きすぎると逆に気が散るので、子どもたちの作業音が聞こえるくらいがちょうど良いです。
- 歌詞が入っている曲でもいいですか?
-
基本的にはインストゥルメンタル(歌詞なし)がおすすめです。歌詞があると子どもが口ずさんだり注意がそれやすくなるためです。
- どのタイミングで流すのが効果的ですか?
-
作業を始める合図や、学習後のゆっくりタイムがおすすめです。授業の切り替えや、ざわつきやすい時間帯にも効果的です。
- 聴覚に敏感な子がいる場合はどうしたらいいですか?
-
無理に聞かせる必要はありません。イヤーマフや耳栓で調整したり、その子だけは静かな環境で作業できるように工夫しましょう。
- 毎日使っても効果はありますか?
-
はい。ただし「流しっぱなし」ではなく、時間を区切る合図として使うことが大切です。「あと5分」、「あと10分」と区切って活用すると効果が持続します。
小学校特別支援学級で使える!授業・ゆっくりタイムに最適な作業用BGM活用法のまとめ
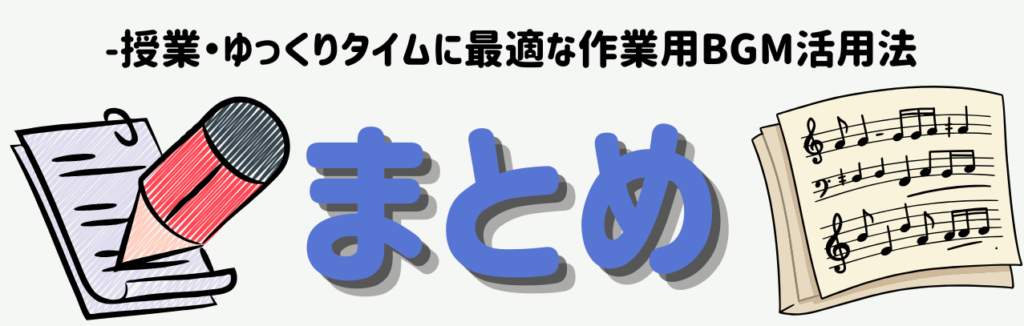
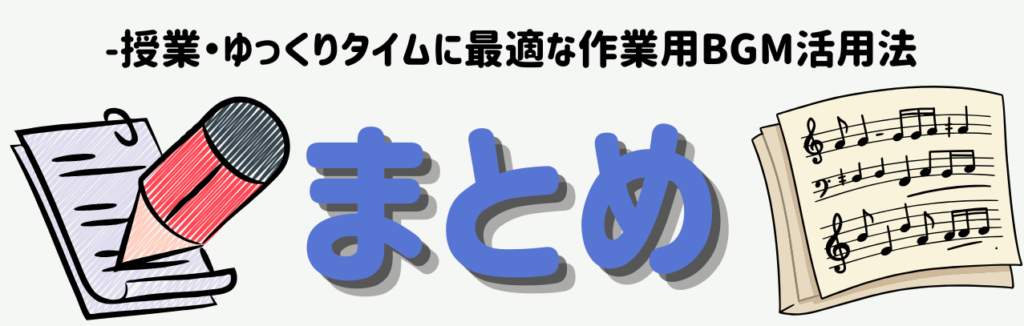
作業用BGMは、ただの「音楽」ではなく、特別支援学級の授業やゆっくりタイムをスムーズに進める「環境づくりの道具」です。
といった活用法を取り入れることで、子どもたちは見通しを持ちながら安心して学習に取り組めるようになります。
先生にとっても「静かにしなさい」と繰り返す負担が減り、授業がスムーズに進むはずです。
ぜひ、日々の授業や学習後のゆっくりタイムに取り入れて、子どもたちと一緒に「集中できた!」「落ち着いて過ごせた!」という体験を積み重ねてください。



かんたん指導案(20分バージョン) は下の▼をタップしてね
かんたん指導案(20分+深呼吸)「BGMを活用して集中しよう」
ねらい
- BGMを合図にして20分間集中する習慣をつける。
- 集中した後に深呼吸で気持ちを切り替える。
指導の流れ(約23分)
- 導入(2分)
- 「今日は音楽を使って20分集中してみよう」と伝える。
- 動画を最初から再生(20分BGM)。 - 展開(20分)
- ドリル、読書、作業学習など静かに座ってできることを実施。
- 10:00の字幕(あと10分)で「半分まできたよ」と声かけ。
- 15:00の字幕(あと5分)で「あと少しがんばろう」と励ます。 - まとめ(1分)
- 音楽が止まったら作業終了。
- 椅子に座ったまま静かに 3回深呼吸。
- 「集中できたね」「リラックスして次に行こう」と振り返り。
指導上の留意点
- 深呼吸は「息を鼻から吸って、口からゆっくり吐く」動作を見せながら一緒に行う。
- 音量は控えめにし、BGMが背景として働くようにする。
- 不安が強い子や集中が苦手な子には「5分だけ挑戦→休憩→再開」と段階的に取り入れる。




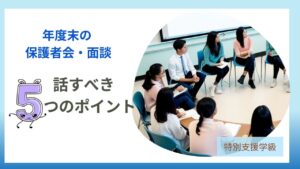
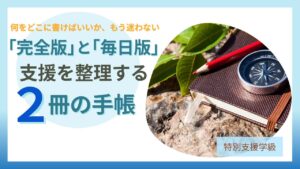
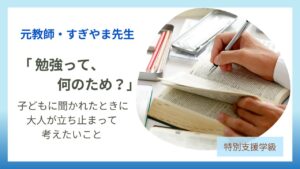

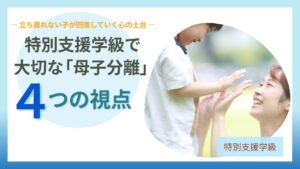


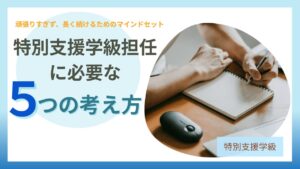
コメント